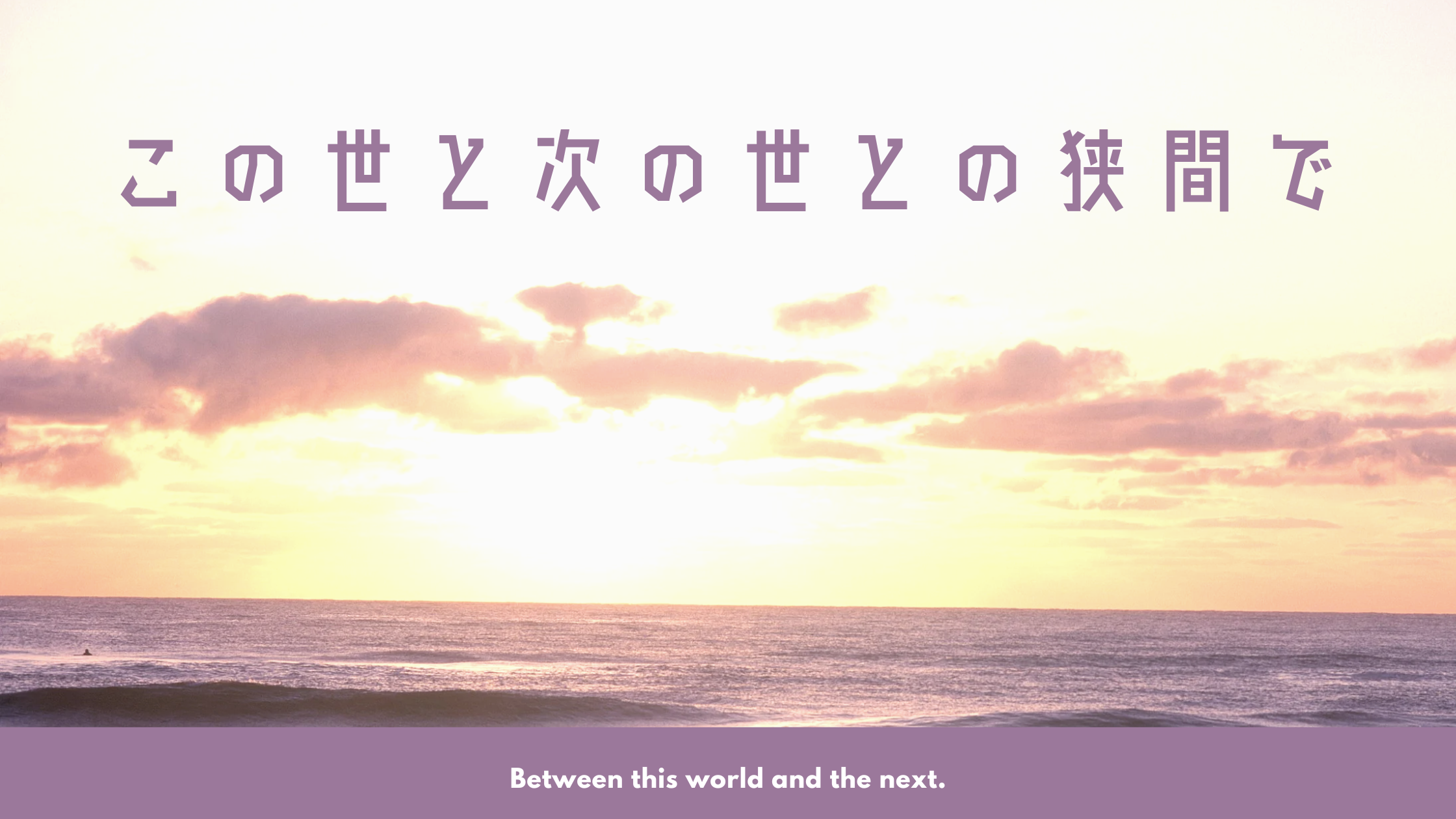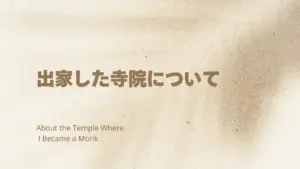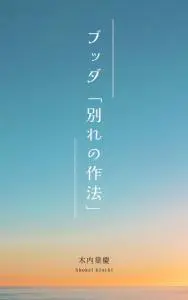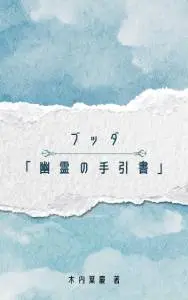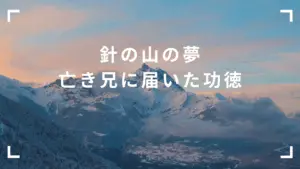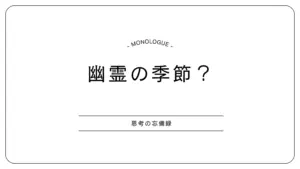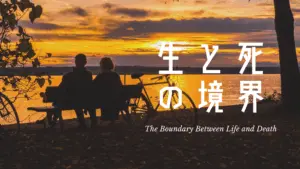更新記録:20250211
不確実性を出来るだけ無くすために、一般的に使われている用語からの変更をしています。あの世
はじめに
前回は、地獄について触れましたが、ほとんどの読者さんたちには縁のないお話しです-たぶん

ところで、何回か葬式に参列していると「この世に続く世界ってあるんだろうか?」と、ふと考えることもあるでしょう。
また、これを読んでいる方は、とりあえず目に見えない世界はあるのかな?と少しは思っている方々でしょうから、死んでも次の世界が存在するかもしれないと、ある程度は想定されているかとも思います。
一方で、「ほとんど信じていない」という方、または、「信じてはいないけど何となく」という方でも、親しい人が亡くなって、まだ傍にいるような感覚に襲われた経験を持っている方も少なくはないのではないでしょうか。
それは、親しかった故に感じることができたサムシンググレートな存在から贈られた特別な霊感だったのかもしれません。
死後の世界については生きているものにとっては、いつかこの身は終わるのですから身近な問題です。でも、一般の方の場合、酷いケガをしたり、重い病気にでもならない限り、考えることもないことでしょう。毎日の生活に追われそれどころじゃないのが実情だと思います。
生きているうちに、死後を想像することは大切です。そこから、今までの人生、これからの人生を見直すきっかけともなります。
そこで、今年ももう7月。地方の中では、7月がお盆という所もありますので、一旦、忙しい生活を立ち止まって、今回はこの世に次ぐ世界について少し想像してみることにいたしましょう。
次世界への旅立ち
次の世界とは
昭和に至るまで、多くの人々が、亡くなればすぐに天国へと行けると思っていました。今では、信じられないことですね。それは日本人の多くの人の中に、浄土信仰が根強く残っていたからだと思われます。
念仏やお題目さえ知っていればそれで十分、といったある種の誤解が蔓延していたのも、鎌倉時代の昔から続く浄土信仰が意識の根底にあったからです。ある意味、それでも良いのではなかったかと、わたしは考えています。
ところが、死んですぐ浄土とはいかないのが甘くないところです。どうやら、「甘くない」とはこの世ばかりでもなさそうです。この世から続く次の世界は、皆さんが想像している以上にはるかに遠く、あるかないかもわからない世界です。はてさて、困ったものです。
通常、人がなくなるとあの世と、しばらくはこの世の狭間に留まる
僧侶の経験からすれば、寺院の中では上記が通説です。
それって、幽霊じゃん
という声が聞こえてきそうですが、幽霊となって人の前に現れるというのは、この世への執着がかなり強い場合です。断末魔の声をあげるほど悲惨な死に方でもすれば、幽霊になるのかもしれません。
あの世とこの世の狭間には【中陰】という世界があります。
普通の人は、通常この中陰にしばらく留まる
【満中陰】という言葉を聞いた方も多いのではないでしょうか。
満中陰とは、命日から、7日x7=49日目を指します。この7日という数にも意味があって後日にでも紹介できればと思います。
寺院では、満中陰に対して【仕上げ】という隠語を使います。わたしの寺院の僧侶は、亡くなった日の故人に対して引導を渡し、次の世界へとつつがなく旅立てるよう年忌ごとに説得を続けます。
そうして、この世のつながりを断ち次世へと向かう準備を整え、満中陰の日を持って旅立ちましょうという希望を込めて仕上げと言っています。
ところが、物事そう上手くは参りません。亡くなる状況も事情も人によって様々ですし、何より、人のこころはそう簡単には割り切れるものでもありません。
次世までの道のり
では、どのくらいの時間で次の世界に行けるのでしょうか?
わたしが修行した寺院の信徒さんで平均しておおよそ30~40年、37回忌の法要をすぎてからそろそろという方が多いようです。
寺院の信徒さんというのは、こころを整えるよう日頃から心がけている方々が、俗世間よりは多少は多いはずです。加えて、年忌ごとの僧侶の供養を伴っていてもこのように平均で数十年の時間を要します。
一般の方でしたら、100年前後で行けたら早い方なのではないでしょうか。これも前世から引き継いでいる境涯やこの世の行いによって変わっていきます。
先だって記事にしたこの世にただならぬ遺恨のある古戦場の武士たちが、数百年以上も迷うというのも当然のことですね。寺院での古戦場の戦死者については、以下の記事に書いています。
中陰の世界
中陰に長く留まる要因は大きく2つになります。ひとつは、自分の人生を振り返ることができるためです。
中陰はこの世とは、次元が違うため時間の概念がありません。中陰で自分の過去にさかのぼって振り返ることもできるので、過去の自分の行いを見ながら、
なんで、あんなことしちゃったんだろう
ああすればよかったかなあ
~さん今どうしてるのかなあ
…….
こんな風にぐるぐる巡る思いがこころをかき乱し、さらにこころが混とんとしていくと自然と迷いも多くなっていきます。これは、サムシンググレートな存在が、わざとそうさせているかもしれませんね。
そして、もうひとつ何より次世への足かせとなるのは、自分がいなくなった後の様々な心配事です。
子供や孫がいれば、その成長や今後の心配
家や財産を持っていれば残したそれらの心配
そんなこの世の心残りが人にはたくさんあります。それをひとつひとつ自分の中で治めていって、はじめて次の世界へと旅立つ準備が整うのです。
最近では、終活など流行っているようです。これも、ある程度の迷いの解消の手伝いにはなるかもしれません。でも、知っていてほしいことは、物質的な整理を念頭に始めることと、こころを整えることとでは筋道が少々異なっていることです。
次世へ行くための、こころの扉を開く
物質的なものより、まずは「こころありき」です。この世の様々な事象にどっぷり浸かっていたこころは、たとえ自身のこころであってもそう簡単には変わらないものです。
死んでから取り組もうなどと悠長なことを言っている暇はありません。今生きている間が、何よりも代えがたい最適なこころの修養期間なのです。
一方、あっという間に次世へと行かれる方もまれにいらっしゃいます。ほとんどは、前世の行いやこの世の修行状況などから、こころがすでに整っている方です。
おわりに
その昔「Heaven can wait」(邦題:天国から来たチャンピオン)というウォーレン・ビーティ主演の一目ぼれ系のロマンチックな映画がありました。
その映画の設定で、あの世に旅立つ乗り物が旅客機というのは、さすがにエンターテインメント的な脚色を感じましたが、今にして思い返すと中陰の世界がそれなりに描かれていたように思います。それが、「天国へは待つことができる」映画の原題に繋がっているのでしょうね。
また、劇中で、天使が人間違いをするというのも、ちょっと考えられませんが、総じて生と死が同一線上に描かれているのは評価したい点です。
本当は映画ほど単純な世界でもないのですが、そこは娯楽映画ですから仕方のないことです。時間があったら、一度観てみると良いかもしれません。
今回も長くなりそうなので、次回に引き継ぎたいと思います。