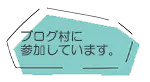はじめに
ここまで、コスパ・タイパから慈悲の変容、そして「病」や「老い」、そして「死」をめぐるいくつかの考察を重ねてきました。その中で、次第に一つの像が浮かび上がってきます。
それは、タイパやコスパといった効率性を最優先する価値観のもとで、人が孤立し、老いが社会の周縁へと追いやられ、病への取り組みが変貌し、死が語られないものとして遠ざけられているという現象です。
様々な視点から、この流れを辿っていくと、現代社会は、お釈迦さまが正面から対峙していた「生老病死」を、見えないものとして封じ込めていく構造を持っているのではないか、という疑問に行き着きました。
この記事では、「生・老・病・死」という根本的な問いに現代社会が暗黙の裡にどのように扱ってきたか、前回までの記事と合わせて総括してみました。そこから、わたしたちが失いつつあるものの正体を探ります。
(生)タイパ・コスパが生み出す「孤立した生」
「結論から言って」
「で、何が言いたいの?」
ビジネスの現場だけでなく、日常会話にまで浸透した効率化の波は、わたしたちから「待つ」時間を奪いました。即レスが当たり前となり、沈黙は気まずいものとなり、遠回りの会話は「ノイズ」として処理されます。
「タイパ(タイムパフォーマンス)」を意識して映画を倍速で視聴し、「コスパ(コストパフォーマンス)」で人間関係すら値踏みする。無駄を削ぎ落とし、最適化された人生は、一見するとスマートで賢い生き方のように思えます。
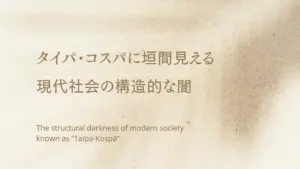
この最適化された生は、同時に人を孤立させます。タイパを追求すればするほど、他者と関わることは「コスト」になります。面倒な調整や、感情のすれ違いを避けるため、わたしたちは「個」で完結する生き方を選ぶようになりました。
「おひとりさま」「ソロ活」の隆盛は、自由の獲得であると同時に、「誰にも煩わされたくない」という孤立への渇望です。しかし、皮肉なことに、ノイズを排除した人間関係は驚くほど脆(もろ)い。
効率よくつながったはずのわたしたちは、気づけば深いところで誰ともつながれず、群衆の中の孤独を深めているのです。他者との関係は必要最小限に絞られ、苦しみや弱さは、個人で処理されるものへと変わっていきます。
この価値観のもとでは、役に立たない時間、回り道、無駄に見える関係は、次第に切り落とされていきます。
わたしたちが効率化の美名のもとに切り捨ててきた「無駄」な時間。その中には、実は人間が人間らしく生きるために不可欠な、ある重要な要素が含まれていたではないでしょうか。
それは、「思い通りにならない生の実感」です。
人間にとって一番と言って良いほど大切な「生の実感」が、ひたすら追求していく効率化の下、見えなくなってしまっているのです。
(老)老いが排除されていく社会の構造
この効率性の論理は、老いと極めて相性が悪い。老いは、成果を生まず、スピードを落とし、手間を要するからです。
そのため老いは、生活の中心から徐々に遠ざけられてきました。施設化、専門化、制度化によって、老いは「管理される対象」にはなりましたが、「共に生きる実体」ではなくなっていきます。

老いが日常から切り離されることで、わたしたちは、老いていく過程そのものを、ほとんど目にしなくなりました。
老いて機能が衰える身体は、生産性という観点からは排除されるべき対象となり、わたしたちは自分自身の未来であるはずの「老い」を、直視できない恐怖の対象として見ないようにしているのです。
(病)過剰医療と奪われる苦悩の主体性
現代において「病(やまい)」は、単なる身体の不調ではなく、テクノロジーによって、まるで機械のように「修理」されるべき対象と見なされています。
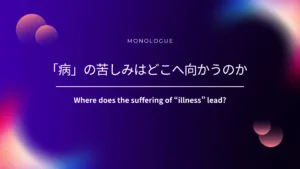
終末医療に限って言えば、病は生の一部であり、死へと向かうプロセスです。しかし、現代の医療システムは「生かしておくこと」そのものが目的化しがちです。
本人の意思やQOL(生活の質)を置き去りにしたまま、延命という名の「過剰医療」が選択される。これは、病という「思い通りにならない現実」を、科学的な数値や処置によって強引にコントロール下に置こうとする試みです。
また医療の現場においても、病院の白い壁の向こう側で、人は「固有の痛みを持つ人間」から「数値化されたデータ」へと変換されます。
治療が効率化されるほど、病を通して人が感じる不安や迷い、弱さゆえに見えてくるものは、治療の現場からこぼれ落ちていきます。それらはいつの間にか、数字やデータとして整理され、「患者の苦しみ」ではなく「管理される情報」へと姿を変えてしまうのです。
その最も大きな要因となっているのは、「早く治して復帰する」ことが正義とされる社会です。
慢性的な病や癒えない傷を抱えて生きることは「非効率」と見なされます。病むことは、生産性を止める「社会的な停滞」として忌避され、その生々しい苦悩は、他者の目から見えない場所へと遠ざけられていくのです。
(死)死を忌避し、遠ざけることで起きていること
死についても同じことが言えます。
かつて、死は生活のすぐ隣にありました。家で生まれ、家で死んでいく。それが当たり前の風景でした。しかし、死は不吉なもの、重たいもの、扱いづらいものとして、語られる前に避けられていきました。

医療や制度は死を引き受けますが、日常生活から死は姿を消していきます。死は病院や施設へと高度に外注(アウトソーシング)され、日常から徹底的に隔離されています。わたしたちは「死ぬ瞬間」を見ることがなくなり、葬儀ですら簡略化(直葬など)が進んでいます。
死を「見えないもの」にすることで、わたしたちは死の恐怖を克服したつもりになっています。しかし、本当にそうでしょうか。
例えば、葬式は、亡き人を弔うためだけのものではありません。生きているわたしたちが「死」と向き合い、それを自分の生の一側面として受け止めるための場でもあるのです。
死という「確実な終わり」を意識から排除した結果、わたしたちの「生」は輪郭を失いました。「死」を見えなくしていく一方で、生は実感を失っていきます。死を遠ざけることは、逆説的に「生きる」をも希薄にしているのです。
お釈迦さまが見据えていたものとの対比
お釈迦さまが対峙していたのは、まさに前述してきた「生老病死」でした。人として生きる意味は、それらを避けるのではなく、正面から見つめ、誰にでも等しく訪れるものとして引き受けることにあります。
だからこそ、問いは常に個人を超え、普遍的なものとして語られていました。「わたしの苦しみ」は、「あなたの苦しみ」でもあるという前提が、そこにはあったのです。
ここまで見てきて気が付いたことがあります。テクノロジーと資本主義は、この「思い通りにならないこと」をシステムの外側へ追いやろうと躍起になっていることです。
生は孤立化を進めていき、老いは美容医療で、病は高度医療で、死は隠蔽によって、見えなくしようとする。
しかし、見えなくしたからといって、苦しみが消えるわけではありません。むしろ、正体不明の「漠然とした不安」として、わたしたちのこころの奥底を蝕んでいるのが現状だと思っています。
おわりに
生老病死が人々の暮らしから遠ざかり、ブラックボックスのように扱われる状況は、デフレの時代背景も手伝って、静かに、しかし確実に速度を上げてきています。
生老病死を見えないものにした社会は、一見すると快適です。しかし、その快適さは、苦しみを共有できない構造の上に成り立っていることを知っておいてほしいと思っています。
わたしたちが今、取り戻すべきは、タイパやコスパでは決して測れない、泥臭く、面倒で、非効率な「生の手触り」そのものです。
老いに戸惑い、死を語れず、苦しみを一人で抱え込む生。
それは、個人の弱さではなく、社会構造の帰結です。
生老病死を再び可視化することは、何かを解決することではありません。ただ、それらを人生の外へ追い出さず、「共にあるもの」として取り戻していくことです。
ブラックボックスの蓋を、少しずつでいい、自分の手で開けてみること。「思い通りにならないこと」を受け入れ、その苦しみすらも味わい尽くす覚悟を持つこと。
そこにしか、効率とは別の次元で、「人が人として生を全うする」可能性は残されていないと、わたしはそう感じています。