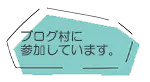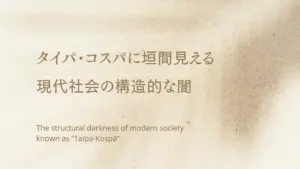はじめに
前回の記事では、現代における慈悲の変容から現代社会の課題について触れました。
他者の苦しみに寄り添おうとするとき、かつてのようには言葉が届かなくなっていること、そして「介入しないこと」が、必ずしも優しさとして受け取られない場面が増えていることについて書きました。
ところで、日常の中で、気になる場面に出くわすことがあります。
例えば、わたしと同年代かそれ以上の人と話しているとき、特に老いにまつわる話題に差しかかると、会話がふっと途切れてしまう瞬間があるのです。こちらが何か答えを用意しているわけでも、慰めようとしているわけでもないのに、どこかで「これ以上は踏み込めない」という空気に変わっていく。
みなさんは、高齢者の方々と話しをしていて、同様な感覚を抱いたことはないでしょうか?
その沈黙に触れるたび、わたしは軽い違和感を覚えてきました。老いは誰にでも訪れる出来事であるはずなのに、いつの間にか「その人だけの問題」として扱われてはいないだろうか、と。
すなわち、前回取り上げていた「わたしの苦しみは、わたしにしか分からない」が「老い」の場面で表出しているという事実です。今回は、こうした小さな違和感を手がかりに、現代社会における「老い」の立ち位置について考えてみたいと思います。
老いがどのようにして、「わたしの苦しみは、わたしにしか分からない」という前提を強めてきたのか。その経緯を辿ることで、現代社会が抱え込んでいる行き詰まりも、少しずつ見えてくるように思われます。
そのためのキーワードとして、前回同様ショーペンハウアーの「同苦」から始めてみたいと思います。
ショーペンハウアーの「同苦」とは何か
ショーペンハウアーの同苦をもう一度整理しておきます。
ショーペンハウアーは、わたしたちが苦しむのは「自分と他人は別物だ」と思い込んでいるからだと考えました。時間や場所というフィルターを通すことで、世界がバラバラに分断されて見える――彼はこの錯覚を「個体化の原理」と名付けています。
たしかに私たちは、年齢も住む場所もバラバラで、一人ひとり孤立しているように見えます。けれど、同じ「生」を営む存在であるならば、こころの奥底で共有している苦しみがあるはずです。わたしたちが感じている「壁」は、同じ人間である以上、実は幻影にすぎません。
もし、その幻影が一瞬でも消え去り、誰かの苦しみを自分のことのように感じられたなら――。
彼はその感覚を「同苦(Mitleid)」と呼びました。この一瞬の共感の中にこそ、人が救われる道があるのだと、彼は説いたのです。
本来、老いは「同苦」を生む出来事だった
かつて、「老い」は「同苦(Mitleid)」をもっとも自然に受け入れられる出来事でした。
時代や場所を問わず、老いは誰にでも例外なく訪れます。これは、人間の在り方から言えば道理であり、他者の老いを見つめることは、鏡の中に自分自身の未来を映し出すことと同義だったからです。

かつての共同体において、老いは特別な不幸ではなく、人生の不可欠な一幕であり、世代を超えて共有される経験でした。そこには説明不要の共感が成立しており、他者の老いに触れることは、自らの行く末を予見し、受容することでもあったのです。
老いの「私有化」と同苦の断絶
しかし現代において、老いはその普遍性を失い、徹底的に「私有化」されました。今日、老いは「個人の問題」や「備えの不足」、「自己管理の失敗」かのように語られ、自己責任という名の檻(おり)へと閉じ込められています。
現代における「苦しみ」の捉え方と同じ方程式が「老い」に対してあからさまに当てはめられているのです。
ここで起きているのは、「個体化の原理」の過剰なまでの強化です。かつては幻影であったはずの自他の境界線は、いまや強固な壁となり、他者の老いを「わたしの未来」ではなく「あなたの問題」へと切り離してしまった。
「老い」というのは、「苦しみ」を具体的に実体化したものと捉えられて、老いは同苦を分かち合う契機から、単に距離を置くべき対象へと変質したのです。

人が老いから目を逸らすのは、単なる冷淡さゆえではありません。老いがあまりにも直接的に、個人の努力や自己像の限界を突きつけるからです。わたしたちはその過酷な現実を否認するために、老いを生活圏の外へと押し出し続けています。
切り離されてきた「老い」
具体的に、わたしたちはどのように「老い」を隔離してきたのでしょうか。
空間的隔離:見えなくなる老い 高齢者は施設や病院へと集約され、老いていく身体を日常の中で目にする機会は激減しました。老いは人生の地続きの風景ではなく、「特別な場所で起きる非日常」となったのです。
言語的隔離:語れなくなる老い 衰えや死を口にすることは「失礼」や「不謹慎」とされ、話題に上る前に避けられます。老いを語るための作法が失われ、沈黙を選択するようになりました。
専門的隔離:委ねられる老い 老いは医療や介護の専門領域へと委ねられました。家族や隣人が日常の言葉でケアする余地は奪われ、老いは「共に引き受ける経験」ではなく、「専門家に任せるべき案件」へと処理されていきます。
概念的隔離:自己責任としての老い 健康管理や資産形成の文脈において、老いは個人の選択の結果として裁かれます。他者の困窮や衰えは「自業自得」として切り捨てられ、共感の入り込む余地は塞がれています。
そして何より、私たちには老いを語るための「生きた言葉」が決定的に不足しています。
病名や要介護度、年金制度といった事務的な記号は溢れていますが、「未来が短くなる感覚」や「役割が剥がれ落ちていく心細さ」といった、内面的な感覚を分かち合うための語彙は、もはや残されていないのです。
剥き出しになる「生存意志」
社会が「同苦」を失うとき、そこに残るのは、他者を踏み台にしてでも生きようとする剥き出しの「生存意志」です。
高齢者に対する冷淡な眼差しや、世代間の分断を煽る言説は、まさにショーペンハウアーが描いた「自らを食らう意志」の縮図と言えます。

本来、老いによる衰えは、万人に共通する「苦(ドゥッカ)」であり、それを共有することで「わたし」という執着(エゴイズム)から解放される契機となるはずでした。
しかし、現代社会は老いを「遠い他人の不運」として処理することで、この自己救済の道を閉ざしています。
まとめ
老いという現実に直面したとき、わたしたちはある事実に気づかされます。
それは、わたしたちが「他者と同じ苦しみを生きている」という共感よりも、利害関係のみを依り代として社会を築いてきたという事実です。
ハイデガーが説いた「世人(ダス・マン)」が、死や衰えを「誰にでも起こり得るが、今ここにいるわたしの問題ではない」と忘却するように、現代社会もまたシステム化によって「同苦」という人間本来の痛みを麻痺させてきました。
現代における「老い」の在り方は、まさにその麻痺を露呈させています。それは、効率の陰に隠れた、目に見えない意識下における現代版「姥捨て山」の風景に他なりません。
もし老いを、孤立した個人の問題ではなく、わたしたちが同じ流れの中で引き受けるべき「苦」として捉え直すことができれば、効率や役割を超えた、人と人とが「共に在る」ための感覚を取り戻せるはずです。