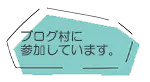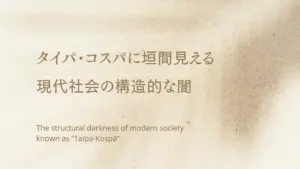はじめに
仏教の最も古い聖典のひとつとされる『スッタニパータ』。
その中でも最古層に位置づけられる第5章「彼岸道品(パラーヤナ・ヴァッガ)」を紐解くとき、現代を生きるわたしたちは、ある種の違和感、あるいは羨望にも似た感覚を覚えることになります。
そこでは、アジタやティッサ・メッテイヤといった修行者たちが、ブッダに問いを投げかけています。
老いについて、死について、世界を覆う無明について。
わたしがそこで気づかされたのは、彼らの問いの前提にある、ある種の「清々しさ」でした。彼らの問いには、主語としての「わたし」が前面に出てこないのです。
その理由として考えられるのは、修行者たちの度量はもちろんですが、人々のこころとこころとの距離が現代より近かった時代の要因もあったのだと思います。
今回は、初期仏典からみた現代の大きな課題について、様々な視点から考察したいと思います。
わたしと他者の間の距離
最初に、「彼岸道品(パラーヤナ・ヴァッガ)」における修行者たちの主語「わたし」が前面に出てこないことについて言及してみます。
以前、このブログの中で「わたし」について書きましたが、修行とは、この「わたし」を少しずつ小さくしていく営みである、という話をしました。

「彼岸道品(パラーヤナ・ヴァッガ)」に登場する修行者たちは、この「わたし」を小さくしていくことに精進してきた人々です。「わたし」を小さくしていくということは、「わたし」と「あなた」を隔てる境界線も薄くなっていくことです。
何より、その境界が薄くなければ、「慈悲」をこころに抱くことはできません。他者の苦が、薄い境界線を通して、そのまま自分の苦として感じられ易くなるからです。
彼らにとって「わたしの問題」は、同時に「他者の問題」でもありました。 ゆえに「わたしの苦しみ」は「あなたの苦しみ」へと重なり、それは特定の個人の事情ではなく、誰にでも該当し得る普遍的な事象として語られています。
これは同時に、当時の修行者が「聖者」という、人を超えた境地にあったことの証左でもあります。重ねて申し上げますが、聖者とは特殊な能力を身につけた存在ではありません。ただ、慈悲を感じ取るための繊細な機微に、深く通じているだけなのです。

そこには、「苦しみは共有されている」という、修行者たちの暗黙の了解がありました。だからこそ、ブッダの言葉は、真理をそこに「指し示す」だけで十分に機能したのです。
この意味で、「彼岸道品(パラーヤナ・ヴァッガ)」をはじめ、『スッタニパータ』は修行者たちのための書であったと言えるでしょう。
次に時代に注目してみます。「彼岸道品(パラーヤナ・ヴァッガ)」が書かれた時代から現代に目を移したとき、修行者の度量以前に、この前提は、もはや音を立てて崩れ去っています。
苦しみの「私有化」と個体化の原理
近代から現代にかけて、わたしたちの「問い」の質は、大きく変化しました。個人主義の台頭は、自由と引き換えに、わたしたち一人ひとりに「孤独な城」を与えました。
その結果、現代の苦しみは、かつてないほど強固に「私有化」されています。
こうした前提から出発する問いが、現代では当たり前のものとなっています。

ここで、19世紀の哲学者ショーペンハウアーの視点を借りてみましょう。
彼は、世界の本質はひとつであるにもかかわらず、時間と空間という認識の形式によって、世界が分断されて見えることを「個体化の原理(principium individuationis)」と呼びました。
そして、この原理が生み出す「自分と他人は別物だ」という感覚こそが、利己主義の根源であると見抜いたのです。
ショーペンハウアーにとっての救済は、この幻影を見破り、他者の苦しみを自分のこととして感じ取る「同苦(Mitleid)」にありました。
しかし、現代の病理は、この想定すら超えてしまっているように思えます。
「同苦」だけでは届かない現代の壁
かつてなら、「壁はまやかしだ」と見抜くことで、慈悲が通い合う場所まで、あなたとわたしの距離を縮めることができたのでしょう。
けれど、現代を生きるわたしたちにとって、この「個体化の壁」はもはや幻影ではありません。それは破ることのできないアイデンティティとなり、「自分だけの苦しみ」を抱きしめること以外に、自分を守る術がなくなってしまったのです。

この厚い壁の内側に立てこもる人に対し、ただ外から「壁などない」と説いたり、「あなたの苦しみはわかります」と語りかけるだけで、果たして何かが届くのでしょうか。
残念ながら、それが届くことは稀である、と言わざるを得ません。なぜなら、そこには「他者の立ち入り」を拒む強固な前提が存在しているからです。
昭和期までの宗教が、この壁を越えるために共同体の力を必要としたのは、偶然ではありません。

慈悲とは「外科手術」である
このような状況において、仏教的な「利他」は、構造的な転換を迫られています。先のナーガールジュナ(龍樹)を扱った記事で触れたように、現代においては、忌避されがちな「介入」を、いずれの教説も避けて通れなくなっているのです。
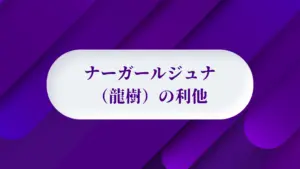
相手が「わたしの苦しみは、わたしだけのものだ」という前提に固執している以上、それを揺るがすためには、その閉ざされた領域に踏み込む行為が必要になります。
ナーガールジュナ(龍樹)が『中論』で説いた「空」の思想は、本来、実体として固着した自我を切り崩すためのものです。しかし現代において、この剣を振るうことは、少なからず暴力性を帯びることを避けられません。なぜなら、相手が守ろうとしている「わたしという殻」を、外からこじ開ける行為になるからです。
「あなたの苦しみは、あなただけの所有物ではない」
この真実を突きつけることは、現代の「他人の領域に踏み込まない」という倫理観から見れば、不作法な振る舞いに見えるでしょう。けれど、もし「介入」を恐れてわたしたちが背を向けてしまうなら、仏教をはじめとする慈愛の宗教は、もはや現代においてその役割を果たすことができなくなるのかもしれません。
おわりに
共同体の後ろ盾を失った現代の大乗において、ただ優しく寄り添うだけでは、慈悲は成立しなくなっています。 前回の記事で触れた「差し出す」慈悲の在り方だけでは、もはや届かない場面が増えているのです。
実際、一部の大乗系仏教には、分断された個と個の間に立ちはだかる「個体化の原理」という壁を、摩擦を恐れずに解体しようとする強い意志を感じさせるものも存在します。その代表的な手段として、「折伏1」を挙げることができるでしょう。
「わたしの苦しみは、わたしにしか分からない」という孤独なドグマから、人間をふたたび普遍的な地平へと引きずり出すこと。 その「お節介」とも言える介入こそが、現代における最も切実な「慈悲」となってしまっているのが現状です。
しかし、あまりに踏み込みすぎた慈悲が、容易に執着へと転じてしまうことも、前回の記事の中で、すでに述べました。それは言うまでもなく、お釈迦さまの本意からは遠ざかります。
現代において築き上げられた「個別化の壁」は、いまなお、厚く高くなり続けているのです。
- 誤った考え方(悪法)や悪人を打ち破り、正しい仏法に導くこと ↩︎