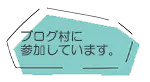はじめに
前回、中間コミュニティのカタチについて書きました。

ちなみに、この記事で表している中間コミュニティとは、個人と国家(社会全体)の中間に位置し、家族、会社、組合、地域コミュニティなど、共同体的な性格を持つ集団のことです。
日本では、江戸時代以前から強いコミュニティが作られていました。地縁、血縁、そして家付きの寺社。人々はそこから、生存の安全保障、自己の承認、そして人生の指針という「果実」を受け取っていました。
しかし、近代化と都市化によってコミュニティは次第にその姿を消しつつあります。コミュニティの最小単位である家族でさえ、その形態が危ぶまれるほどです。しかし、人が安心して自らの生活を維持していくためには、自己の承認等、上記のような欲求がどうしても起こってきます。
そのため、中間コミュニティの支えを失って“剥き出し”になった個人が、たとえば「推し活」のような形で、所属や承認といった中間コミュニティの機能を代替する場を求めている――そうした現象が、たびたび話題になります。
今回は、なくなりつつある中間コミュニティの行き先について、人々が模索している状況についてです。中間コミュニティについては、これが最後となります。
「再興」としての擬似コミュニティ
近代の共同体にほころびが見え始めていた頃、新興宗教に代表される戦後から高度経済成長期にかけて隆盛した新興の共同体は、失われた「村」や「家族」の再現を試みていたと思えるところがあります。
大まかに言って、共同体が担っていた機能には、次の2点があると思っています。
- 承認の場: 自分の話し(苦しみや悲しみ)を聴いてくれる仲間がいる。
- 役割の付与: 組織内での活動を通じて「自分は必要とされている」と実感できる。
これらの新興的な共同体は、この2つの性格を有しながら、中間コミュニティの弱体化によって、そのつながりや手応えを失いつつあった人々が、もう一度その果実を手にしようと描いた、いわば「再興の夢」でした。
そこには、確かに全人格を包み込むような濃い結びつきと、揺るぎないアイデンティティを得られるという感覚がありました。
しかし、とりわけ新興宗教の分野では、いわゆる「カルト的」と呼ばれる要素が、人権侵害や、宗教二世・三世が抱える苦悩、さらには社会との摩擦を生み、その影響を現在にまで引きずっている側面も否定できません。
当時を振り返れば、それは、崩れかけた拠り所としての共同体に、必死に手を伸ばそうとしていた姿でもあったのだと思います。
「憧憬」すら持ちえない世代の登場
現代の新しい世代は、もはやその「重い共同体」への憧憬(あこがれ)すら持っていません。彼らにとって、かつての共同体が提供した連帯感は、時に「同調圧力」や「拘束」という名のコストとして映ります。
家族を含めた共同体が「コスト」として意識されるようになった背景には、長く続いたデフレの影響も、無視できない要因としてあります。
成熟した資本主義社会に差し込み始めた陰りを、いち早く敏感に感じ取ってきた新しい世代は、その仕組みそのものを、自分の人生にまで重ね合わせて生きざるを得なかったのではないでしょうか。

そう考えると、個人の選択として語られがちな生き方の背後にある重さに、どこかやりきれない気持ちを覚えてしまいます。
町にも、会社にも、そして家族にさえ、
かつて期待されていた役割や機能を、
もはや自然には求めにくくなっている。
すべてがコストや効率の物差しで測られる世界を前にして、
この感覚を、わたしたちはいったい何と呼べばよいのでしょう。
断片化される代替物
中間コミュニティという概念そのものが忘却の彼方へ去ったとき、人々は何に同じ拠り所を求めているのでしょうか。そこには「代替」という言葉では括れない、モザイク状の断片化した世界が広がっています。
かつての共同体が担っていた機能は、今や以下のような社会的・政治的な流れへと解体・吸収されています。
- 「推し活」という名の情緒的セーフティネット
-
全人格を預けるのではなく、特定の対象にのみ情熱を注ぎ、同じ価値観を持つ者と「ほどよい距離」感で繋がることで自己の存在意義を確認していく活動と言えるでしょう。
- デジタル・部族主義と政治的正義
-
無関心化と過熱化が顕著な世界です。過熱化する現象は、SNS上のアルゴリズムによって形成される「意見の共同体」を基にしています。共通の敵(悪)を作ることで、一時的な万能感と結束感を得る。これはかつての選民意識の変容した姿かもしれません。
- 機能的に外部化された「繋がり」
-
悩み相談はAIやカウンセリングへ、助け合いは行政サービスやギグワークへ。コミュニティの機能は「サービス」へと置き換わり、情緒的な手触りは失われました。
代替機能の行方
中間コミュニティという「再興の夢」が潰え、すべてが個人の「自己責任という名の亡霊」へと収束していく現代。わたしたちは、かつてないほど「自由」であり、同時に「脆弱」です。
人々は「自由の享受」を旗印に、自己実現の欲求を満たそうと試みていますが、共同体という緩衝材が無くなってしまった社会において、そう単純で簡単な話しではありません。
中間コミュニティの果実に飢えることも、既にそれを再興しようと足掻くこともなくなったわたしたちは、剥き出しの意識で世界と対峙せざるを得ないのです。
「中間コミュニティへの憧れを持ちにくい世代が、これからどこへ向かうのか」を考えるとき、問題になるのは、宗教か非宗教か、右か左か、といった二項対立ではありません。もっと根源的で人間の生きる土台となるほど重要な課題なのです。
まとめ
人が求めているのは、「自分の居場所」「役割」「承認」「助け合い」「善悪の基準」、そして「ある程度見通しの立つ未来」といった、本来は中間コミュニティの中に束ねられていた、細かく断片化された機能です。
問われているのは、それらが、どこで、どのように満たされるのか、という点に尽きます。
その代替がうまく機能すれば、人は生活を整え、人との関係を無理なく広げながら、自分なりの幸せに近づいていくことができます。しかし、その時間軸はとても短く、その移ろいを想えば絶えず不安定であると言わざるを得ません。
一方で、代替がうまくいかなければ、依存や分断といったかたちで、別の歪みを生み出してしまうこともあります。
こうした分岐は、働き方や教育、福祉、情報環境といった、社会全体の設計にも大きく左右されます。
ただ、中間コミュニティがあらかじめ用意されていないという状況は、ある意味で、一人ひとりがどのように選び、どう生きていくかが、これまで以上にシビアになったことを意味しているとも言えるでしょう。
今回、二回にわたって中間コミュニティについて考えてきて、最終的に行き着いたのは、この問題が、社会制度の話にとどまらず、わたしたち一人ひとりの在り方や生き方へと、ますます強く収束している、という事実でした。
何かに守られているという実感を持ちにくい世界の中で、丸裸で放り出されたわたしたちは、それぞれが自分の足場を探しながら、手探りで生きていくことになります。