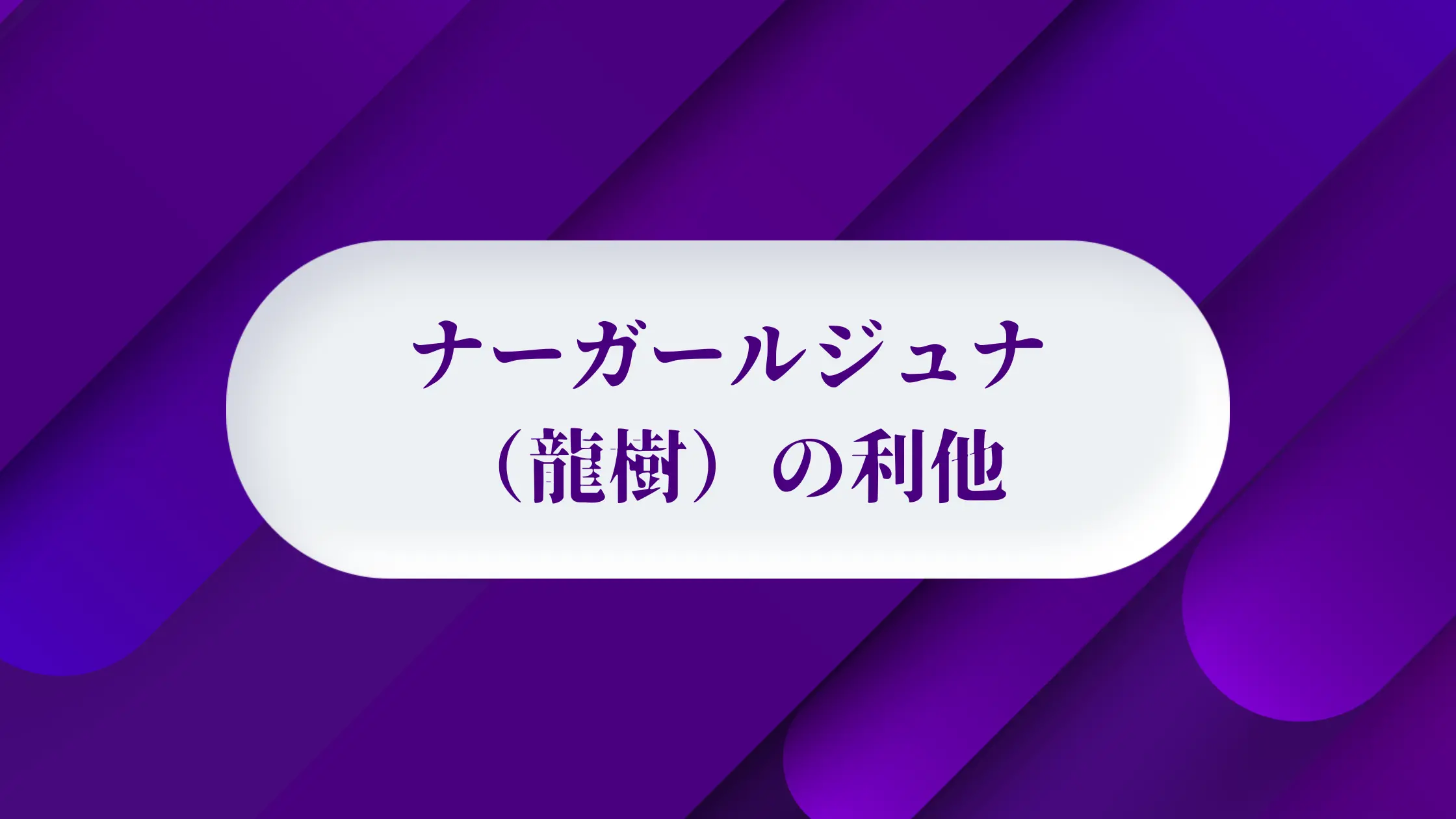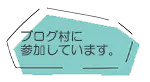はじめに
ナーガールジュナ(龍樹)をご存知でしょうか。
仏教界隈も少し奥へ入っていかないと、なかなか出会わない名前かもしれません。大乗の祖とも呼ばれ、「中観」の思想で知られる、紀元後2〜3世紀頃の論師です。伝説は多く残っていますが、詳しい生涯についてはわかっていません。
中国で儒教的な枠組みと本格的に混ざり合う以前の大乗の流れの中で、彼の議論は中核の一つとして受け継がれてきました。いまなお、その徹底した思索に惹かれる人は少なくありません。

わたしもまた、龍樹の思想には注目しています。とりわけ縁起の論理そのもの以上に、そこから浮かび上がってくる「無我」——自己を固まりとして掴まない方向性は、わたしが意図することなく行き着いたお釈迦さまの思想の捉え方に近いものがあります。

今回は、中観の体系化者で大乗の一潮流に強い理論的背骨を与えたナーガールジュナ(龍樹)について、その大乗の思想の基になった利他について簡単になぞりたいと思います。
問いを差し出す
最初に、仏教の2つの大きな流れ「大乗(だいじょう)」と「小乗(しょうじょう)」いう言葉を簡単に整理しておきましょう。
大乗とは仏教用語で、「大きな乗り物」を意味します。自分ひとりの悟りにとどまらず、他者――仏教では「衆生」と呼ばれる存在――とともに目覚めていくことを理想とし、誰もが悟りへと向かう可能性を持つ、という考え方に立つ仏教の流れのひとつです。
また、この大乗における「他者の救済」のことを「他人を利する」ことから「利他」と称しています。
これに対して「小乗」とは、主に自己の解脱や悟りを重視する立場を指して用いられてきた呼称で主に南伝仏教の流れにある宗派を指しています。「自分ひとりが乗る小さな乗り物」という比喩には、大乗側からの視点、やや批評的・相対化されたニュアンスが含まれている点も、併せて知っておくとよいでしょう。
この二つの流れに、どちらが正しい・誤っているという優劣があるわけではありません。
いずれも、お釈迦さまの教えをどのように受け取り、どう生きるかという解釈の違いであり、それぞれが長い時間の中で磨かれ、形づくられてきたものです。
さて、ナーガールジュナ(龍樹)の語る縁起と空は、ときに人を突き放しているかのように冷たく見えることがあります。「すべては空だ」と言われると、誰かの痛みや生活の手触りまで、消えてしまいそうに感じるからです。
けれども、もし縁起についてさらに洞察していけば、そこで起こるのは無関心ではなく、むしろ逆です。
世界が相互依存でできていると見えてくるほど、「わたし」と「あなた」を隔てていた硬い境界が緩んできます。
すると、他者の苦は、遠い出来事ではなくなっていきます。この考え方は、大乗が大乗たる由縁の基礎になりますし、昨今の南伝仏教(便宜上小乗)の大乗化?の動機にもなっていると思われます。
利他、すなわち「人助け」とは尊い行いです。ただし、ここで注意したいのは、利他が「介入」になってはいけない、ということです。何を持って「利他」とするか?宗教全体を通して言える、とてもデリケートで難しい部分です。
誰と誰とが有縁・無縁であるかなどは、もとより、分かるはずがありません。
他者を変えようとし、相手の人生に踏み込んで操作しようとするなら、それは別の支配であり、新たな執着を生みます。そうなれば、反対に縁起の理解と辻褄が合わなくなってきます。
砕いて言ってしまえば、目に前で倒れ掛かっている人がいれば、迷いなく手を差し伸べますが、誰かれなく「あなたは救われなくてはならない」という志向は、縁起の観点では、あまりに「慢(Māna(マーナ))」、傲慢というわけです。
では、辻褄の合う利他とは何でしょうか。ここにナーガールジュナ(龍樹)の真意があります。
それは、相手をこちら側に引き寄せることではなく、相手の中にある“固まり”を、相手自身がほどけるように手助けすることです。言い換えるなら、「答えを渡す」のではなく、「問いを差し出す」ことです。

たとえば、人が苦しむとき、その火種はしばしば出来事そのものではなく、出来事に貼りついた“決めつけ”にあります。「こうに違いない」「自分はもう駄目だ」「あの人は絶対に変わらない」——。
こうした言葉は、こころを守る鎧のようでいて、同時に、こころを締めつける鎖にもなります。
わたしが僧侶であったとき、大乗の中にいると、どうしても相手が必要とする「答え」を探そうとしてしまいます。他方で、人と関わる尺度は時代を経るほど複雑で難しくなってきています。
このような時代にあって、複雑さを増す一方の人々の機微を思えば、神通を以てしても限度があることは、わたし自身が身をもって経験してきました。結局、たとえ人のこころにある「決めつけ」に本人以外が気が付いたとしても、それを破ることは、当の本人にしかできないのです。
縁起の視点から見た利他
こころを締め付ける鎖を外すために必要なのは、正論でねじ伏せることではありません。
相手が自分の握り方に気づけるような、やわらかな問いです。たとえば、こんな具合です。
- 「いま、何が起きたのでしょう?」(事実に戻る)
- 「その出来事に、どんな意味を乗せましたか?」(解釈に気づく)
- 「もし別の見方が一つあるとしたら、何でしょう?」(余白を開く)
この三つの問いは、相手のこころを“矯正”するためではありません。
相手が、相手自身のこころの動きを観察し直すための、「入り口」を作り出すためです。
その入り口を通して、こころは「選択」を取り戻す可能性があります(あくまで可能性です)。
言い返す前に、決めつける前に、あきらめる前に、ほんのわずかな余白を提示するのです。
その余白の中で、こころは自然に姿勢を変えます。
つまり、相手に何かを信じさせることではなく、相手の「気付き」に期待するのです。
縁起の視点から、利他を観ると、相手の自由が保たれる距離の中で、相手の内側に行動やこころの反応の前に「選択」の自由を回復させること。これにつきます。
まとめ
縁起を生きるとは、他者に踏み込むことではなく、他者が自分自身へ戻れるように、問いを添えることなのだと思います。

ナーガールジュナの思想から派生した「縁起と慈悲とのコイン表裏一体」の考え方は、大乗と南伝仏教の一部とに利他の正当性を与えるとともに、大乗が出来ることの境界線をも示しています。
このナーガールジュナの引いた境界線については、わたしも同じ思いです。還俗(僧侶を辞した)に至った理由のひとつでもあります。
そのため、わたしがこのブログで実現したいのは、かすかな縁でつながっている人を、安易に突き放すことではありません。むしろ、ネットという距離感だからこそ可能な、つながりの濃度を越えないかたちでの「問い」を、そっと差し出すことではないかと思っています。
縁起は、私たちの性格や気質に及ぶだけでなく、人との関わり方や、そこから生まれる思いの癖にまで及びます。差し出された「問い」を受け取るかどうか、それを生かすのか、あるいは手放すのかも、すべてはそれぞれの縁起に委ねられています。その意味で、わたしたちは本来、とても自由です。
ただし、自由には人によって様々な「色」が付いています。色のついた「自由」については、一度立ち止まって見つめ直す必要もあります。いま握りしめている自由が、実は役割や評価から逃れるための「仮の自由」ではないのか。
「真に自由である」ためには、その色のついた自由を、手放す覚悟が求められます。どの自由を選び、どの自由を降ろすのか。そこにこそ、わたしたちの器量が問われているのだと思います。