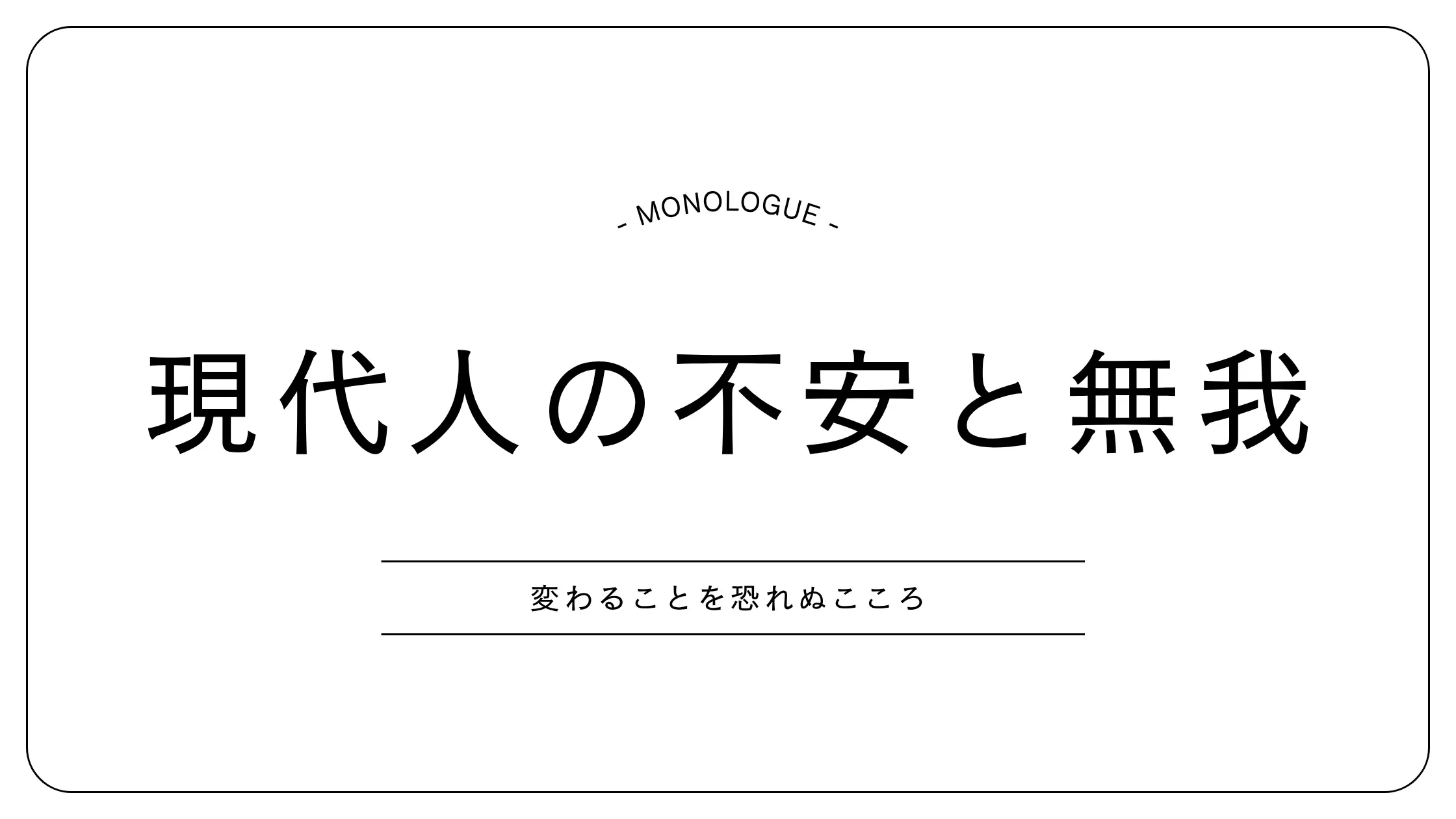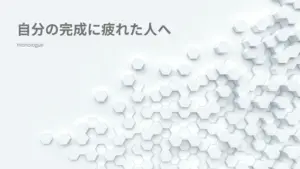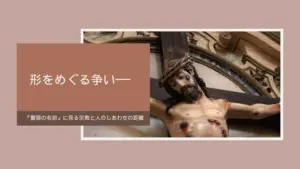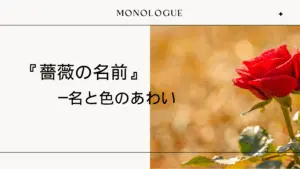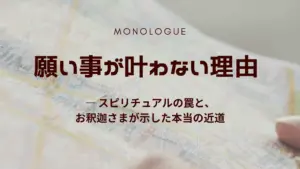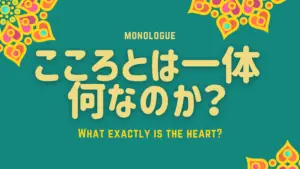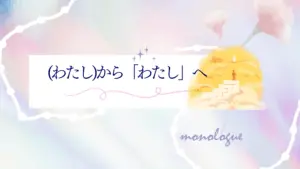はじめに:現代の「我」の重さ
近代以降の人間は、「我」を中心に世界を見てきました。
SNSに映る「わたし」、成果によって評価される「わたし」、
他者と比較され続ける「わたし」。
わたしたちの社会は、「自分」という確固とした存在を
維持し続けることを前提に成り立っています。

しかし、その「我」は本当に確かなものなのでしょうか。
「我思う、ゆえに我あり」と語ったデカルトは、
思考する自分を存在の根拠としました。
けれども、その思想は、いつしか「我」を中心に据えすぎるあまり、
変化を恐れ、他を受け入れられないこころの形を生み出してきたのではないでしょうか。
お釈迦さまの説かれた道は、それとは正反対の方向にあります。
そこでは、「我」という観念をほどき、
変化を受け入れる智慧―すなわち「無我」の理解が語られています。

今回の記事では、デカルト的な「我の確立」と、お釈迦さまの「無我」の思想を対照しつつ、
もう一度お釈迦さまの思想をおさらいしておこうと思います。
その上で、現代における「我の不安」と「変化の恐れ」を見つめ直したいと思います。
我を保とうとする現代人
人は、自分を変えることに強い抵抗を覚えます。
それは不安定な世界の中で、自我という拠り所を求める本能です。
だがその「拠り所」は、同時に「檻(おり)」となります。
「わたしらしくありたい」「自分を失いたくない」と言うとき、
わたしたちはすでに「我」という幻を守ろうとしています。


デカルトの哲学は、理性によって確実性を求めました。
しかしその確実性は、変化する世界を拒む方向にも働きました。
思考によって確立した「我」は、
思考の外側にある「絶えず変化を繰り返していく生きた現実」から目を逸らしてしまったのです。
これが、我執(わたしに固執)する萌芽です。
五蘊の観察―お釈迦さまの実証
お釈迦さまは、この「我」の実体を問い続けられました。
その洞察は『相応部経典(五蘊相応)』に明確に示されています。
「色は無常である。無常なるものは苦である。
無常で苦なるものを我と見ることはできない。」(Samyutta Nikāya 22:59)
ここで説かれる「色(しき)」とは身体的存在を指します。
同様に、「受・想・行・識」もまた刻々と移ろう現象であり、
どれ一つとして恒常ではありません。
お釈迦さまは、わたしたちが「自分」と呼ぶものが、
実際には変化し続ける五つの働きの束でしかないことを示されました。

つまり、わたしたちが「これが我だ」と掴もうとするその瞬間に、
我はすでに移り変わっているのです。
「我」は固定的な実体ではなく、
縁起の中で条件的に現れる一時的な表象にすぎません。
つかの間の姿を「自分」と呼んでいるだけなのです。
縁起の理法―すべては関係の中にある
お釈迦さまが説かれたもう一つの核心は「縁起」です。
「これあれば、かれあり。これなければ、かれなし。」(Samyutta Nikāya 12:1)
この一句に、存在の相互依存の原理が凝縮されています。
わたしたちが「我」と呼ぶものも、
その縁起の網の目の中で一瞬立ち現れているにすぎません。
他や他者との関係なしに存在できる「我」など、どこにもないのです。
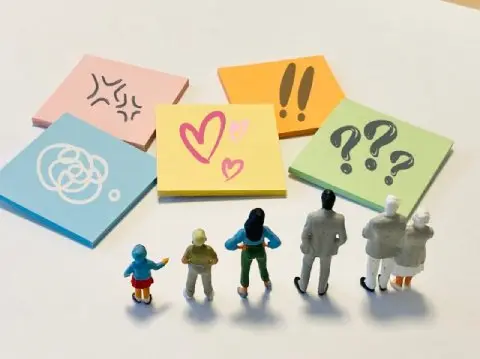
現代社会における孤立や同一性の不安は、
この縁起の理解を失ったことに起因しているといえるでしょう。
個が過度に独立したものと見なされる社会では、
人は他とのつながりを見失い、
変化の中で自己を見いだす力を失ってしまいます。
転生―魂ではなく「意識存在」の流れ
お釈迦さまはまた、生死を超える「転生」についても説かれました。
だがそれは、魂という恒久の存在が移動するという思想ではありません。
『中部経典(Mahātaṇhāsankhaya Sutta)』には、
生命の継続が「識(意識)」の因縁によって成り立つと説かれています。
「識が止まるところに、名色(精神と身体)が成り立つ。」
すなわち、「意識存在」としての働きが次の縁へと伝わり、
その流れが新たな生命を形づくります。
縁という糸が解かれては、紡がれていくように、
紡がれたところに意識は宿り、また解かれ意識は解放される―
ここに、固定的な我の不在と、
それでも続いていく存在のダイナミズムが見えます。

修行としての変化
信仰は「何かを信じる」ことを求めますが、
修行は「ありのままを観る」ことを求めます。
お釈迦さまの道を司る思想は、外に神や救いを求めるのではなく、
自らの内に生起する「我のはたらき」を観る実践でした。
『ダンマパダ』にはこうあります。
「自らをよく整える者に、他の者が何をなし得よう。
自ら整えられたこころこそ、まことのよりどころである。」(Dhammapada 160)
変わることを恐れず、
その変化そのものを修行として受け入れる。
そこにこそ、お釈迦さまの説かれた「無我」の智慧が息づいています。
「我を変える」ことは、「我を滅する」ことではなく、
因縁の流れの中で自己を新たに見出し生きることなのです。
瞑想はこの場面で真価を発揮します。
おわりに―「我思う」から「法を見る」へ
デカルトの思想は、思考する我を存在の根拠としました。
お釈迦さまの仏説は、その我を観察し、
思考の奥にある「変化し続ける法」を明らかにしました。
現代社会における多くの苦悩―不安、孤独、比較、承認欲求―は、
固定された「我」を信じすぎることから生じています。
ここに人生における苦しみが生まれます。

無我の智慧とは、その執着を解き、
変化する世界のままに生きるための実践知です。
「我思う」の世界は、思考の内に閉じています。
「法を見る」世界は、思考を超えて開かれています。
お釈迦さまの思想は我の解放と言えます。
我を守る生き方から、我を観る生き方へ。
その一歩が、まさに修行の始まりなのです。