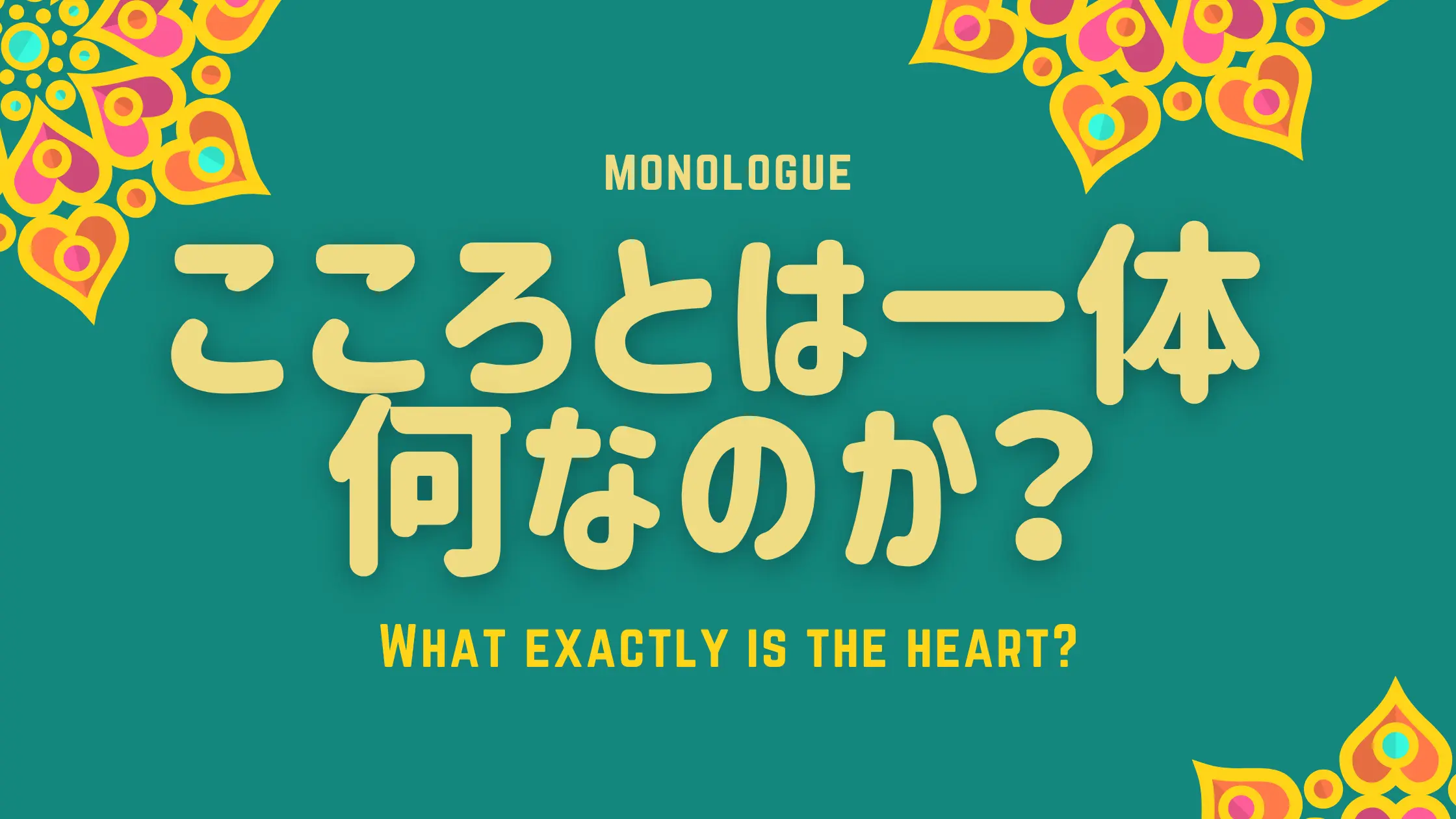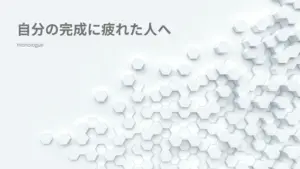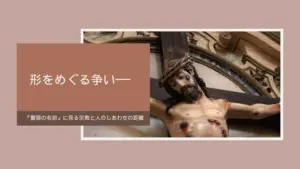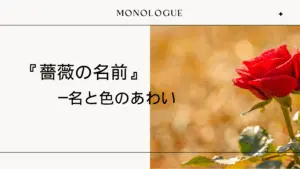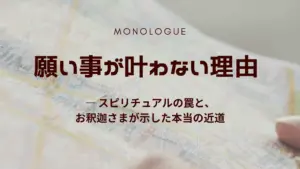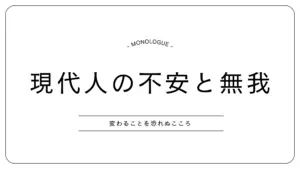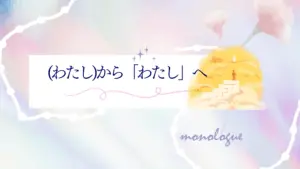はじめに
私たちは、誰かに自分の意志を伝えるとき、言葉という道具を使います。しかし、その言葉が通じるためには、互いにある程度の共通した経験や概念を持っていることが前提になります。そうでなければ、同じ言葉を使っても、意味がまったく伝わらないことがあります。
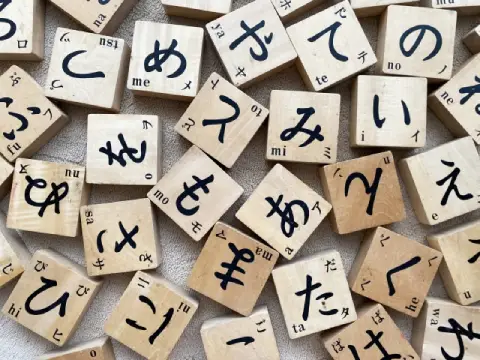
たとえば、異なる言語や文化圏の人に「食べる」という、人間の基本的な欲求に関わる言葉を伝える場合、身振り手振りを交えれば、何とか理解してもらうことができます。けれども、そこから一歩進んで、「甘い」「辛い」「渋い」といった味の感覚を伝えようとすると、途端に難易度が上がります。味覚は主観的なものですし、文化や経験によって感じ方も表現の仕方も違うからです。
さらに、もっと抽象的で形而上的な概念・・・たとえば「無限」や「善」といったもの・・・を伝えようとしたとき、その困難さは一気に増します。これらは目に見えず、感覚でも掴めないため、言葉だけで完全に共有することは、ほとんど不可能に近いのです。
形而上的な概念にはさまざまなものがありますが、その中でも、わたしが特に関心を持っているのがこころです。こころという言葉は、誰もが知っているようで、実はとても曖昧です。あるようでないような、不思議な存在。しかも、そのこころという言葉の意味は、人によって、状況によって、まるで違ったものになります。
これから少しずつ順を追ってこころについて考えていこうと思います。理由としては、自分の中でその意味をはっきりさせておくため、そして曖昧なまま語ることで誤解を招かないようにするためです。
記事内では、こころとカッコ付きのこころを使い分けています。それは、一般的に広く使われている「こころ」と、わたしが感得したこころに相当する概念とは異なるとわかったからです。
その違いが分かり始めたのは、決定的な過去生を経験して以来、ここ最近のことです。それでも、このブログで「こころ」使い続けてきたのは、大乗仏教で僧侶をしていた頃持っていた「こころ」の概念の方を引きずっていたためです。
今更感が強いこころですが、わたしが感得していった知見を改めて書き留めておこうと思いました。
「こころ」:一般的に使われている概念
こころ:わたしが知見した概念
言葉と概念
わたしは、テレビ番組を観ることはないのですが、先だって、妻が歴史好きなことから受動喫煙のように受動観覧した番組がありました。

その日、どんな番組を観ていたのかは定かではありません。けれども、たまたま耳に入ってきたその番組は、「暴れん坊将軍」でおなじみ、徳川吉宗の時代の米(コメ)政策について扱っていました。昭和のテレビ世代としては、つい懐かしさもあって、そのまま見入ってしまったのを覚えています。
番組の中で、解説者がこう語っていました。
「当時は“需要”や“供給”という概念がなく、米が豊作になると値段が下がるという仕組みが理解されていなかったのです。」
つまり、現代では当たり前のように語られる「供給が需要を上回ると、価格が下がる」という原理が、当時の人々にはピンとこなかったというのです。
今では「需要と供給」という言葉を知らない人はほとんどいません。経済の基本として、多くの人がその仕組みを大まかに理解しています。しかし江戸時代には、そもそも「需要」「供給」という言葉そのものが存在していませんでした。少し調べてみると、「供給」に近い意味を持つ語は一応あったようですが、その使われ方は現代とは少し異なっていたようです。
それでも、当時の中には、感覚的に価格の動きを理解していた人もいたのかもしれません。ただし、それはあくまで“肌感覚”の範囲であり、言葉として共有するのは難しかったでしょう。
共通の言葉がなければ、他人に説明することも、議論することも、仕組みとして整理することもできません。
このことから改めて感じるのは、言葉の持つ力です。言葉があるからこそ、私たちは「見えない仕組み」や「抽象的な概念」を理解し、他者と共有することができるのです。つまり、何が起こっているのか、どう対処すればよいのかを考えるためには、まずそれを表す“適切な言葉”が必要なのです。
ところが、このような共有作業をこころという言葉では行われてきませんでした。それはなぜでしょうか。
こころの居所
こころという言葉
お釈迦さまは、実はこころという言葉そのものについては直接言及されていません。仏説には、人の内に沸き起こる「思い」や「感情の働き」についての考察は多くありますが、そうした思いが“どこから生じるのか”、つまりその根源にあたるものについては、明確には語られていないのです。
では、お釈迦さまが生きた時代に、こころに相当する言葉は存在していたのでしょうか。
サンスクリット語に見る「こころ」
古代インドを起源とする言語には、広く使われていたサンスクリット語や、仏典で用いられたパーリ語があります。ただし、紀元前のお釈迦さまの時代に、実際にどの言語が日常的に話されていたのかは、はっきりしていません。サンスクリット語やパーリ語だったという説もあれば、ドラヴィダ語族など、別の言語であった可能性も指摘されています。
当時のインドは、多くの部族や民族が混在する広大な地域でした。通信手段もなく、村同士の交流も限られていた時代です。そのため、地域ごとに異なる方言や言語がいくつも存在していたと考えられます。
ここでは、日本で比較的なじみのあるサンスクリット語を、当時話されていた仮の言語として考えてみましょう。
「hṛdaya(フリダヤ)」──“こころ”の源
サンスクリット語には、現代の「こころ」に近い意味をもつ**hṛdaya(フリダヤ)**という言葉があります。日本では「真言」として知られることもあり、「般若心経」の「心」に相当する語がこの hṛdaya です。もともとの意味は「心臓」あるいは「感情の出どころ」であり、文字通り“心の臓”を指していました。
日本語の「こころ」もまた、「心臓」を由来として発展した言葉です。感情や思考など、人間の内面を表す象徴として拡張されていった点で、サンスクリット語との共通性が見られるのは非常に興味深いことです。
紀元前のインドでも、こうした“感情の中心”を意味する言葉が存在していたのは確かでしょう。しかし、その言葉に込められた意味が、こころと同じであったかといえば、そうではありません。
お釈迦さまの「こころ」は言葉を超えていた
少なくとも、お釈迦さまが生きた時代において、hṛdaya はこころの概念を完全に表していたわけではないと、私は考えています。当時の人々にとってそれは、感情や生命の中心を指す言葉に過ぎず、わたしたちが今使う「こころ」──意識や思索、精神のあり方まで含めた概念──と同じようなものだったことでしょう。
言い換えれば、お釈迦さまの持っていたこころとは、どんな言語にも完全には置き換えられない“言葉を超えた領域”にあったのだと思っています。それは現代の日本語だけでなく、他のあらゆる言語でも同じことが言えるでしょう。
この「言葉ではとらえきれないこころ」について、次節ではさらに深く考察していきたいと思います。
こころの難しさ
現代では、「こころ」という言葉を、ごく当たり前のように使っています。特にサービス業や商品宣伝などでは、「こころ」を付加価値として使う表現があふれています。
たとえば――
「こころを込めて作りました」
「こころを添えてお届けします」
こうしたフレーズは、テレビCMや広告の中でも日常的に目にします。

けれども、「こころ」という言葉そのものは、とても曖昧です。何となく優しい響きを持ち、ふんわりとした印象のまま使われてきました。
一般的に「こころ」という言葉は、思いやりや優しさなどの柔らかな感情、あるいは意志や信念の源といった意味で理解されているように思います。
このブログでもたびたび触れていますが、現代では「モノを消費する」だけでなく、言葉までも消費する時代になっています。
言葉の消費とは
「言葉を消費する」とはどういうことでしょうか。
それは、言葉に自分なりの簡単なラベルを貼り、浅い意味づけをしてしまうことです。そして、その行為が習慣化している状態を指します。
人は曖昧な言葉に出会うと、不安を感じます。だからこそ、自分なりの定義を与えて“理解したつもり”になる。
この「理解した気になる」行為こそが、言葉を“消費”している状態なのです。まるで、次々と新しいモノを買い替えるように、言葉もまた“使い捨て”になってしまっています。
そうした中で、「こころ」という言葉も例外ではありません。
その本来の意味を深く考えることなく、便利な装飾語として使われ続けてきました。優しさや温もりを象徴する言葉として、誰もが好んで使う一方で、その曖昧さの中身は問い直されることがほとんどありません。
つまり、日本において「こころ」は、明確に定義されないまま、ただ“心地よい響き”として消費され続けてきたのです。今更、消費され続けてきた「こころ」について問い直す余地は、もはや存在していません。
「拈華微笑」に隠された真意 ― 以心伝心を超えて
10大弟子のお一人である魔訶迦葉(まかかしょう)尊者の拈華微笑(ねんげみしょう)という逸話をご存じでしょうか。下記に簡単な注釈を添えておきます。
お釈迦様が説法中、蓮の花をひねり見せたところ、弟子たちの中で一番弟子の迦葉尊者だけがその意味を悟って微笑み、お釈迦様は仏法の核心を迦葉尊者に伝えたという逸話。
~google AIより
わたしは、十大弟子の逸話は、事の真偽はともかくとして重要な意味があると思っています。拈華微笑は一般的に以心伝心を表しているとされています。

「以心伝心(いしんでんしん)」という言葉は、仏教や禅の世界を象徴する表現として知られています。しかし、わたしが僧侶として寺院にいた頃の経験から言うと、それは特別なことではなく、むしろ日常的な感覚でした。
当時、私の師匠である住職には、わたしの考えていることがまるで筒抜けのように伝わっていました。まだ口にしていないのに、心の中を見透かされるような感覚――それが当たり前のようにあったのです。ですから、師弟関係における「以心伝心」という言葉には、特別な神秘性を感じていませんでした。
この逸話はしばしば、「以心伝心の象徴」として語られます。しかし、わたしが言いたいのは、この話は単なる以心伝心を表すものではないということです。
お釈迦さまと十大弟子との関係において、以心伝心はおそらく日常的なことだったでしょう。それでも、なぜその中で摩訶迦葉だけが微笑んだのか。そこには、もっと深い意味が隠されているように思えてなりません。
蓮の花は、泥の中で育ちながらも清らかな花を咲かせることで知られています。このことから仏教では、「この世(=泥水)の中にあっても、自らを浄化し、花を咲かせる存在であれ」という譬えがよく用いられます。
もし、お釈迦さまがその譬えを伝えたかっただけなら、花を摘む必要はなかったでしょう。言葉で説明すれば済む話です。しかし、お釈迦さまはあえて言葉を使わなかった。そこにこそ、「拈華微笑」の核心があるのではないでしょうか。
拈華微笑には確かに以心伝心の要素があります。けれども、それは表層的な部分にすぎません。
以心伝心の背後には、**“言葉の限界を超えて真理を共有する”**という、さらに深い意味が潜んでいます。そのことを踏まえながら、次回はこの摩訶迦葉尊者が感得した「真意」とは何だったのかについて、さらに掘り下げてみたいと思います。
こころの発現
最初に、紀元前インドにおけるhṛdayaという言葉について書きました。当時に使われていたこころに該当する言葉がhṛdayaではなかったかもしれませんが、いずれにせよお釈迦さまが持っていたこころに相当する言葉はどんな言語にもなかったと思います。
それを感得し示したのが魔訶迦葉尊者だったのです。すなわち、言葉にならない「こころ」に近い概念を迦葉尊者だけが感得していました。
言葉にならない概念ですから、以心伝心以外、伝える方法はありません。逸話の真意は、以心伝心そのものではなく、言葉にならない概念=こころです。
ここからはあくまで推測ですが、お釈迦さまが捻華で見せた花を愛でる「こころ」。これが、辛うじて、言葉にならない概念=こころに近かったのだと思います。そうして、魔訶迦葉尊者は「こころ」に近くても遠い概念である真のこころを伝える際に、微笑んでみせたのです。
こころはどこにある?
ところで、皆さんは「こころ」がどこにあるのか、考えたことはありますか。
多くの方は、脳の中にあると思っているでしょう。あるいは、こころを想うときに胸に手を当てる習慣から、心臓あたりにあるのではないかと考える方もいるかもしれません。後者の考え方は、日本語の「こころ」という言葉の語源に沿ったイメージでもあります。
ここからは、私が感じ取った、とても繊細で理解しにくい話になります。
実は、こころは脳の中にも、体のどこにも存在しません。
わたしたち一人ひとりのこころは、この世のどこかにあるわけではなく、死後に赴く中陰以降の世界に通じているものです。
そのため、現世の人々のほとんどは、こころが他の世界に通じていることを知りません。
もともとこころは、この世の物理的な場所や概念として存在していないのですから、場所や定義を言葉で表そうとしても、どうしても曖昧になってしまいます。
つまり、こころを脳や心臓に限定して考えることは、あくまで便宜的なイメージに過ぎません。
こころとは、言葉や物理的な現象ではとらえきれないものであり、この世を超えた世界とつながる存在なのです。
言葉や思考だけで理解しようとすると曖昧になってしまう――だからこそ、こころについて考えることは、非常にセンシティブで奥深い営みなのです。
「こころ」の経緯
ここで、改めて「こころ」を時系列にして簡単に振り返ってみましょう。
仏説を伝えるキーワードのひとつとして「こころ」が誕生しました。仏教界隈で「こころ」が使われるようになると、徐々に仏教界から世間に漏れ出していきました。
やがて、独り歩きしはじめた「こころ」は、概念も曖昧のまま社会の中でひたすら消費されてきたのではないかとわたしは考えています。
こうして、「こころ」は曖昧な意味のまま、人の感情の中でもデリケートな表現を司る便利な言葉として広く知れ渡っていったのです。
まとめ
こころに該当する意味や概念はありません。
だから、こころの真の意味やカラダの具体的な場所が特定できないのです。こころとは、人が死んだ後の世界に通じている目に見えない経路です。
例えば、慈悲とは「こころ」からの発露ではありません。この世にはないこころを通して慈悲があります。善い人が当たり前のように共感している概念です。善い人とは以下に説明しています。
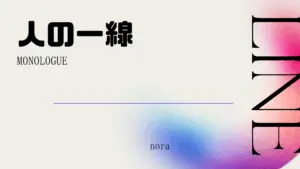
わたしは、これまでこころを言葉にならない概念とは知らずに「こころ」を使っていました。そのことについて、長らく大乗仏教に属していた影響から気が付いていなかったことになります。
人は「こころ」を持ちながら、こころの感得へと長い時間をかけて変化していく生命体です。こころが繋がっている目に見えない世界について詳細はわかりません。わかることはありません。
お釈迦さまが伝えたかった思想はたくさん残っています。その大本はこころです。そこから、無我、煩悩の滅徐、無常観、慈悲、起塔供養とこの順番で広がっていきます。起塔供養から始まりこころへとたどり着く道のりが仏説の常道だと、わたしは気付きました。
こころ←無我←煩悩の滅徐←無常観←(慈悲)←起塔供養←「こころ」
わたしの場合、慈悲を出家後塔の下で感得しましたが、もともと持って生まれた人もいます。
しかし、最終到達点であるこころに関しては該当する言葉や概念がないために仏説には残ってはいません。拈華微笑という真偽不明な逸話に辛うじてその痕跡が見て取れます。わたしたちが普段使っている「こころ」という言葉は、本意のこころとは似て非なるものだったのです。
今回は少し難しかったと思います。言葉にできない概念を伝えることは最初から無謀だとも思ったのですが、書き残しておきたかったので挑んでみました。