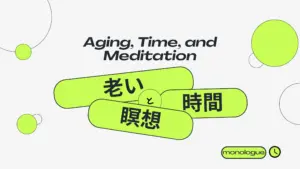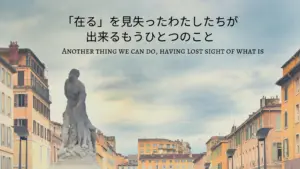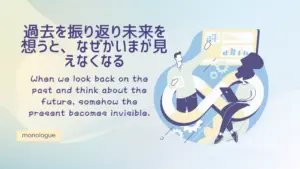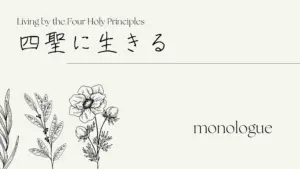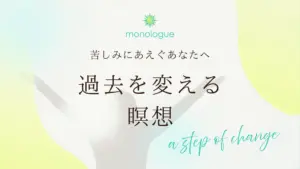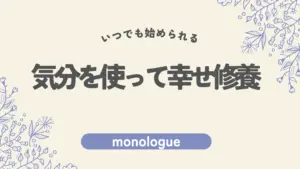はじめに
誰しも老いは訪れます。
「老いとどのように向き合って生きるか」は、人生の最後に待ち受ける最大のテーマのひとつでしょう。
わたしも例外ではなく、老いの真っただ中にあります。
心境はともかく、肉体の面からいえば、腰やひざの痛み、頭痛や自律神経の不調など、どこかしら具合の悪い日が続いています。
最近の研究によれば、老化は人生の中で二度、急激に進む時期があるそうです。
最初は44歳、次は60歳前後。この時期に分子レベルの老化が一気に進み、疾病リスクも増大すると言われます。

以前の記事で「老・病・死」について触れましたが、
この中で、生きている内に自分の中にある死の垣根を超えることは特異点であることを説明していますが、老いについてはあまり取り上げることがありませんでした。
今回はこのうち「老い」に焦点をあて、社会との関わりの中で考えてみたいと思います。

社会性を持った老い
老いの認識
人は生まれる場所や時を選べないように、老いもまた避けることはできません。
肉体的にも精神的にも、老いは厳しい現実を突きつけてきます。
お釈迦さまの教えの中でも、四苦「生老病死」は大変大きな問題です。仏典にも多く取り上げられています。
それは、生と死に比べれば老いは通過点にすぎません。しかし、実際目の前に「老い」が立ち塞がってくれば、通過点に出来ないほど大きな問題です。
そのためでしょうか、現代社会では、老いがまるで「克服すべき敵」であるかのように扱われています。
人々は老いを恐れ、避け、否定しようとします。
社会と高齢者
日本社会は、子ども連れの人や身体障がい者など、いわゆる「社会的弱者」に対してさえ、まだ十分に寛容とは言えません。そのためか、老いはしばしばネガティブなものとして見られています。
かつての日本では、老人は知恵を蓄えた人生の先達として尊敬されていました。
しかし現代では、老いは「忌むべき現象」として扱われ、アンチエイジングが一大産業となり、「若く見える」が最高の褒め言葉になっています。

このような社会通念を変えることは、もはや容易ではありません。
老いを否定的に捉える空気が、老年者には現実として、若者には将来への不安として、ますます深く染み込んでいます。
高齢者と空気
自分の老いを受け入れられない人が増えています。
根本には、「身体に対する認識の拒絶」があります。
衰えゆく身体を受け入れることが、できなくなっているのです。
現代社会は生産性を最優先します。
「役に立たない者は人にあらず」——そんな無意識の思想が蔓延しています。
人々が行き交う街の中で、高齢者がよろめくだけで、迷惑そうな視線を向けられることさえあります。

メディアは「生涯現役」という耳障りの良い言葉を繰り返します。
その背後にアンチエイジング産業の影がちらつくのは、考えすぎではないでしょう。
けれども、生涯現役などあり得ません。
人は必ず衰え、身体は不具合を抱えるようにできています。
にもかかわらず、人々は外見も内臓も、いかに壮年期を引き延ばせるかに血眼です。
極論すれば、その答えは「壮年期のまま死ぬこと」しかありません。
20世紀末以降の日本社会には、「若さこそ価値」という空気が装置のように組み込まれてしまいました。
無常観を失った社会では、「若さ」という幻想が支配的な価値観となっているのです。
答えは今にある
以前の記事で、現代人が「今」に執着し、今を上塗りして生きている姿を描きました。
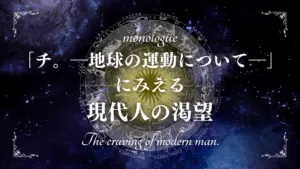
しかし、老いに直面する人にとっての「今」は、そこにある「今」とは違います。
決定的な違いは、着目点が外にあるか、内にあるかです。
外に向かう今は、老いを隠す手段を探すだけ。
内に向かう今は、老いる自分そのものを見つめる行為です。
外へ答えを求めれば、老いを消そうとする方法ばかりが増え、かえって老いへの執着を深めます。
けれども、内にある「今」を見つめれば、そこに本当の静けさが現れます。
そのための心構えを挙げるなら、次の三つです。
- 過去の自分と比べないこと(「去年の自分はもっと元気だった」などと言わない)
- 良い未来を期待しないこと(「また歩けるようになるかもしれない」と願いすぎない)
- 悪い未来を恐れないこと(「このままだと寝たきりになるかもしれない」と思い詰めない)
過去と未来を手放すとき、はじめて「今の自分」が見えてきます。
まとめ
一般的に35〜65歳が中年期、65歳からが老年期とされます。
けれども、老いとの出会いはその前から始まります。
人に頼ることを恥とする風潮の中で、私たちは「支え合うことの自然さ」を忘れてしまいました。
赤子が人の手を借りて育つように、老人もまた人の助けを借りて死を迎えるのです。
それは恥ではなく、人としての自然な姿です。

自分でできることが減っていく中でも、
バランスの取れた食事、適度な運動、そして「怒らず、謙虚に」過ごすこと。
「実るほど頭が下がる稲穂かな」の言葉のように、素直な柔らかさを保ちましょう。
そして、他人を見下すような人とは距離を置いて構いません。
「身体が動かないな」「物忘れが増えたな」と感じたら、
それを嘆くのではなく、いまの自分をそのまま受け入れること。
老年期は「今の自分」を見つめ直すための、貴重な時間です。
瞑想とは、まさにその「今の自分」を観る練習でもあります。
老いに向き合うことは、日常において瞑想している自分を生きることです。
老いの答えは、すべて自分の中にある。
答えを求める必要はありません。
老いを否定する社会通念や外の価値に惑わされず、
衰えていく身体と静かに語り合いながら、
その過程そのものを「答え合わせ」として生きる。
そこにこそ、人間としての最も深い成熟があるのです。