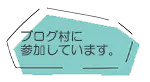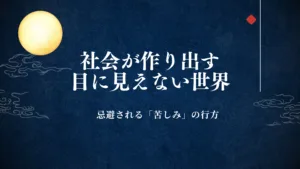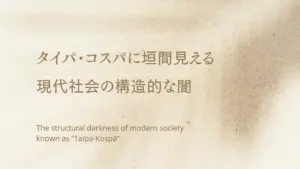はじめに
「「チ。―地球の運動について―」という漫画・アニメ作品をご存じでしょうか。
15世紀ヨーロッパを舞台に、地動説を受け継いでいく人々の物語です。わたしは普段、地上波のテレビをほとんど観ないのですが、娘が帰省した折に、横でアニメ版を一緒に眺める機会がありました。

この作品が世間でどの程度知られているのかは分かりません。ただ、社会・経済ともに、ある種「恣意的な停滞」を続けている現代日本において、少し大げさに言えば、いまだからこそ生まれるべくして生まれた作品なのではないかと感じたのです。
今回は、この作品をきっかけに、現代日本社会について考えてみたいと思います。
日本社会の3つのキーワード
日本には、人々の間でいつの間にか共有され、自然発生的に作り出されてきた社会現象とも言うべき、次の3つのキーワードが潜んでいるとわたしは考えています。
- 継承と持続性の欠如
- 世間から空気へ
- 気遣いから忖度へ
一方で、「チ。―地球の運動について―」に描かれているのは、厳しい制約の中でも、自らの信念のために命を賭して生きる人々の物語です。そこには、上記のキーワードと真逆の世界観が息づいています。
伝統や文化をはじめ、大地とのつながり、人と人との結びつきさえ捨て去り、ついには無常観そのものを失ってしまった現代日本社会の姿は、若者たちを中心に、深い閉塞感と無気力を植え付けています。
若年層の抱く絶望感は、昭和生まれであるわたしの想像をはるかに超えています。
少々大げさに聞こえるかもしれませんが、この作品を観ていると、そんな日本の現状がよりくっきりと浮かび上がってくるように思えるのです。
日本の現状
失われた継続性
天動説は英語で geocentrism(地球中心説)と呼ばれます。
神への信仰と結びつくことで、実に500年以上もの長きにわたり、人々の「常識」として受け入れられてきた世界観です。
500年といえば少なくとも7世代以上にわたります。その長い時間を支えてきた通念を覆すことが、どれほど大変であったかは想像に難くありません。
作品の中では、当時禁忌とされた地動説が、人から人へ、姿や形を変えながら受け継がれていく様子が描かれています。
対して日本では、昭和から平成にかけて、土地に根ざし連綿と受け継がれてきた思想や文化よりも、「新しい社会通念」を優先し続けてきました。

わたし自身、1970年代後半、ちょうど高校入学の頃から、世の中の底がすっと抜けてしまったような奇妙な感覚を覚えていました。
その後、言葉にしようのない不気味な不安感が、じわじわと大きくなっていったことをよく覚えています。
なぜそう感じるのかを考えないまま過ごしてしまいましたが、「一体あのとき何が起きていたのか」と真剣に思い始めたのは、還暦を過ぎてからのことです。
<今>の台頭
伝統や伝承されてきたものが身の回りから消えていくと、人々は拠り所を失います。
受け継ぐべきものが見当たらず、未来へ託すべきものも手元にないとき、価値判断の基準のすべてが「今」に押し込められていきます。
こうして、現代は、「今」がただ連続していくだけの、継承性に乏しい世界になってしまいました。
数日前の出来事さえ、わたしたちのこころにはほとんど残りません。
世代を超えて受け継がれていく伝承は、現代日本では風前の灯火です。
人々は、SNSのタイムラインの更新に追い立てられながら、「今」という怪物の口の中へ、新しい出来事を次々と放り込み続けています。
承認欲求や自己満足・達成感を得るために、神経をすり減らしながら生きているのです。
主要メディアもそれに歩調を合わせ、日々移り変わる趣味嗜好を垂れ流し続けています。
積み重ねることができないということは、
「後の世代に手渡せるものが何もない」ということです。
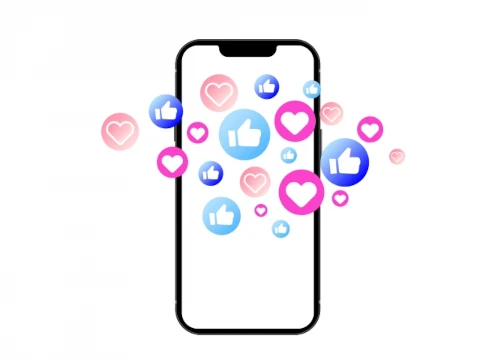
継続性の欠如は、そのまま生きる土台の欠如を意味します。
土台を失った社会は、不安感と焦燥感を絶えず生み続けます。
さらに、数十年にわたるデフレマインドが、若者のこころの奥底にまで影を落としてきました。
政治経済的な“フラットな世界”の中で生まれ育った世代は、タイパ(タイムパフォーマンス)とコスパ(コストパフォーマンス)を至上命題とし、恋愛さえコスト計算の対象としてしまう——そんな、何とも寂しい現実が日本を覆い尽くしています。
不安で乾ききったこころは、餓鬼のように「今」を食い散らかし、さらに自らを蝕んでいきます。
空気の正体
「場の空気」という概念を、日本社会の文脈から最初に本格的に取り上げたのは、山本七平だと考えています。
空気感そのものは昔から存在していましたが、それを社会心理として言語化したのは近現代のことです。
わたしが幼い頃には、「空気」ではなく**「世間」**がありました。
世間の目は至るところに存在し、善悪はともかくとして、人々の行動に一定の制限と方向性を与えていました。
この「世間」は、日本の村社会的な意識から育まれてきたもので、
ある程度の共同体と、連続した文化がなければ形成されえない拠り所でもあります。
ところが、前節で述べたような「今」の台頭とともに、「世間」の形成が追いつかなくなりました。
そこで、**瞬間的に生成され、その場を支配する「空気」**が、世間の代替品として幅を利かせ始めたのです。
コロナ禍を思い出してみてください。
一人の学者の提唱した説をマスコミが増幅し、日本全体の「空気」が一変しました。
同様の例は他にも数多くあります。
現代日本においては、「場の支配力」という点で、もはや空気は世間の比ではありません。
なぜなら、現代の日本には「今」しかなく、
「空気」こそが、その“今”を大雑把に支配できる唯一の見えない権力者となってしまっているからです。
こころと伝承
「チ。―地球の運動について―」に描かれた時代には、神と教会が強大な権力を持っていました。
人々が天動説を信じようが、地動説を信じようが、
庶民の日々の暮らしの中には、なお受け継がれていく「何か」が堅固に存在していた時代です。
それは、信仰であり、伝統文化であり、家業としての職であり——
枚挙に暇がありません。
それらを礎として、人々は**「強いこころ」を持って生きていました。**
若い世代は、そうした「何かを受け継ぎながら生きる時代背景」を作品の中に敏感に感じ取り、
ある種の羨望を抱いているようにも思えます。
場と時間を超越した物語は、自分たちが生まれたときから当然のものとして受け入れてきた
**「家畜化された社会」**を、一時的にでも相対化して見つめ直すための装置なのかもしれません。
人にとって大切なのは、
「何が正しいか・間違っているか」だけではなく、
世代を超えて信じたいと思えるものが、自分の中にあるかどうかです。
山河を削り、どこへ行っても同じような街並みを作り続ける日本では、
万人の心の土台であるはずの**「大地」そのものが大きく損なわれてきました。**
土台を失った現代人は、「今」に固執していきます。
そこにしか拠り所が見当たらないからです。
学歴・偏差値・職業といった“ラベル”を偏重し、
人間の根源的な営みさえ「コスト」として計算してしまう——
その背景は、ここに集約されているように思います。
「今」を上塗りし続ける世界は、結局のところ、苦しみしか生みません。
でも怪獣みたいに遠く遠く叫んでも
また消えてしまうんだ
~「怪獣」(サカナクション)より
『チ。―地球の運動について―』の主題歌の一節です。
この物語と歌詞には、かすかな希望でさえも未来に託しながら生きることの尊さが、静かに滲んでいるように思います。
まとめ
日本における古い伝承や伝統が、かつての形で復活することは、もはやほとんど期待できないかもしれません。
しかし、「土台をつくるこころ」そのものは、一人ひとりの内側に宿るものです。
周囲に土台となるものが見当たらないのであれば、
それぞれが自分のこころの中に、自らの手で築いていくほかありません。
希望を見出しにくい政治・経済の状況や、
刹那的な「今」にこころを揺さぶられ続ける日常に、翻弄され過ぎてはいけません。
時代を超えて息づく命の根源は、無常観にあります。
無常観を自分自身のものとしていくことは、
「今」への執着をゆるめ、
すべての出来事を “受け継いでいく”視点を持つことでもあります。
「今」に依存すればするほど、未来はぼやけていきます。
いつまでも「今」にしがみつくのではなく、
自分を解放し、自分を基礎とした新しい世界観を静かに立ち上げていきましょう。
そして、その世界観から生まれる内側からの幸福の波動を、自らの手で育てていくのです。
お釈迦さまの説かれた「塔を起てる」とは、
本来、そうした内なる土台と無常観を、自らの中に建てる行為なのだと、わたしは理解しています。