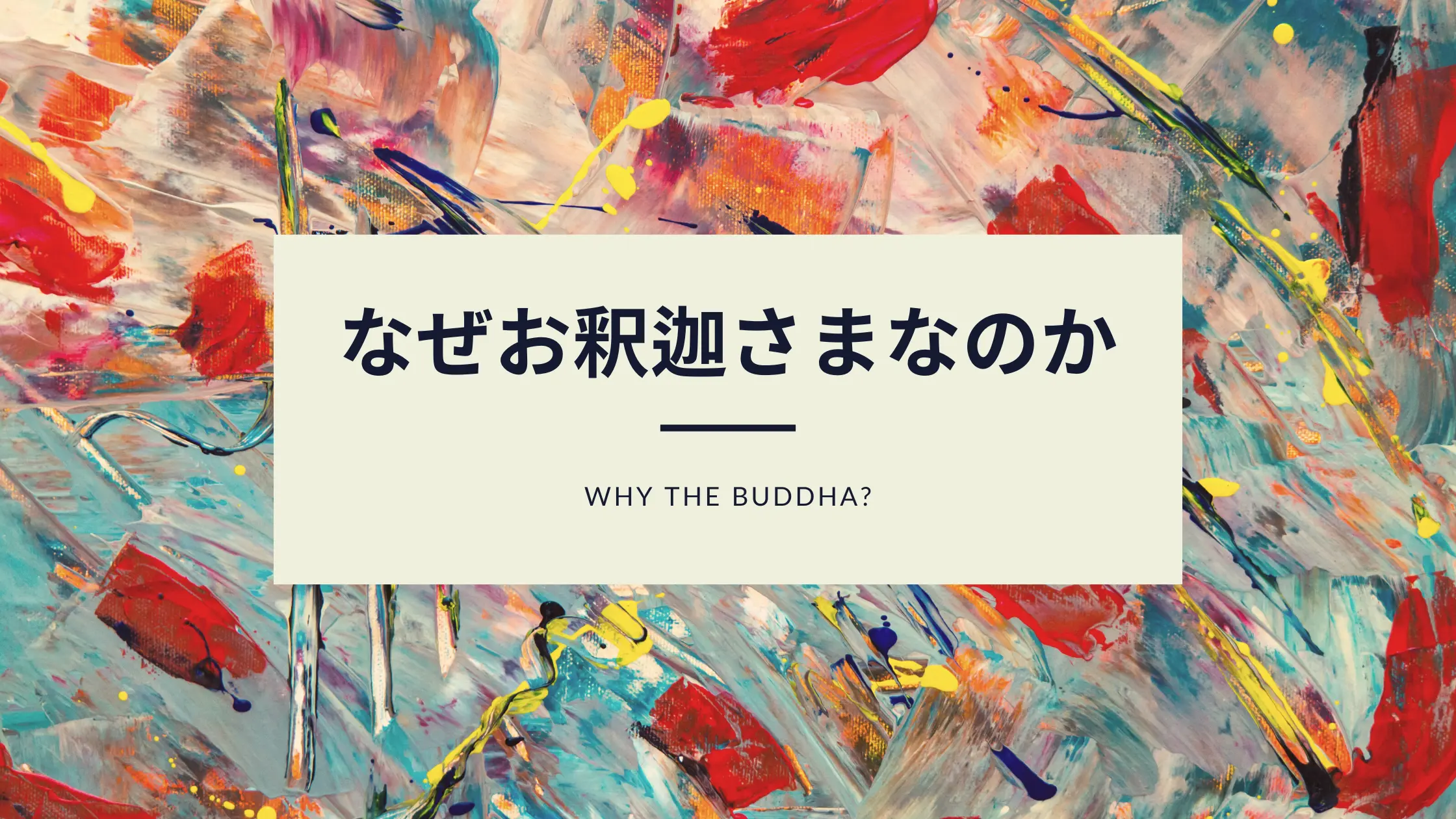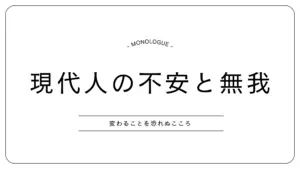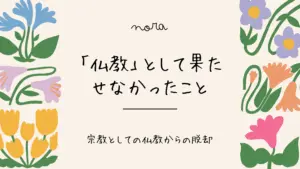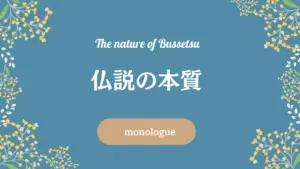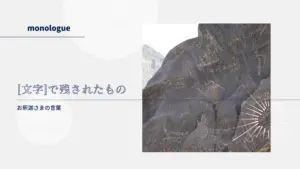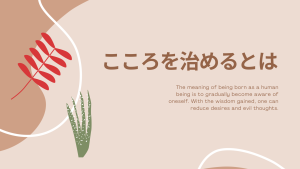はじめに
お釈迦さま――。
そのお名前を知らない方は、きっとほとんどいないでしょう。
けれども、その思想となると、詳しく知る人は少ないかもしれません。
この記事は、そんな「名前は知っているけれど、よくわからない」という方に向けて書いています。
神仏はこの世にたくさんおられます。
それなのに、なぜわたしはお釈迦さまを信奉しているのか?
不思議に思う方もいるでしょう。
有名な神社の神さまでも、近所のお稲荷さんでも、あるいは大日如来や阿弥陀如来でもいいのではないか―と。
もちろん、それでも構いません。
信じる気持ちは自由です。
どんな神仏であれ、そこに「敬うこころ」があるなら、それは尊いことです。
(もっとも、わたしも最初からお釈迦さま一筋だったわけではありませんが……笑)
そんなわたしがお釈迦さまと出会ったのは、出家して間もない頃のことでした。
まるで何かに追い立てられるように寺の門をくぐった先で、ふと目にしたご本尊が「仏塔」だったのです。
そこから、わたしとお釈迦さまとの縁を取り戻していく過程が始まりました。
とはいえ、そこでいきなりお釈迦さまを信奉するようになったわけではありません。
寺院の教義は難解で、正直なところ、長年信仰を続けておられる信徒さんの中にも、その真意を深く理解している方は少ないように見えました。
わたし自身も、最初のうちは「お釈迦さまの思想とは一体何なのか」と戸惑いながら過ごしていました。
けれども、住職の説法に何度も耳を傾け、お釈迦さまの智慧を少しずつ噛みしめながら、日々修行と研鑽を積んでいくうちに――ある瞬間、決定的な過去生の記憶がよみがえったのです。

その出来事を境に、お釈迦さまの言わんとされたことが、言葉を超えて腑に落ちるようになりました。
それは理屈ではなく、まるでこころの奥底で、長い眠りから目覚めるような感覚でした。
今回は、なぜわたしがお釈迦さまを信奉するのか、その理由を大きく二つにまとめてお伝えしたいと思います。
これは、過去生から続く、時空を超えたわたしの信条です。
その前に少しだけ整理しておきたいのは、仏教の中でのお釈迦さまの位置づけについてです。
ご存じの方も多いと思いますが、お釈迦さまは大乗仏教において「仏(ほとけ)」、あるいは「如来(にょらい)」として尊ばれています。
ただし、宗教や宗派によってお釈迦さまへの理解や信条は少しずつ異なります。
大乗仏教、特に法華経の世界観では、「如来」とは、人の到達し得るはるか先の境涯を指します。
まずは、この「如来」という言葉の意味からお話しをはじめてみましょう。
如来とは
如来の正式名称は、
~如来・應供(おうぐ)・正徧知(しょうへんち)・善逝(ぜんぜい)・世間解(せけんげ)・無上士(むじょうじ)・調御丈夫(じょうごじょうぶ)・天人師(てんにんし)・佛(ぶつ)・世尊(せそん)
といいます。
まるで「寿限無」のように、息の長い名前ですね(笑)。
ちなみに、お釈迦さまのお命を狙い、浄土真宗の悪人正機の代名詞とも言うべき提婆達多(ダイバダッタ)も、長い時間を経て成仏した後は、
天王如来(てんのうにょらい)・應供~佛・世尊
と呼ばれています。
わたしにとっては、この天王如来のほうが、阿弥陀如来よりも身近に感じられる存在です。
この長い名は、パーリ仏典の『相応部』にも記されています。「如来の十号」と呼ばれ、十の称号それぞれが、人が修行によって歩む過程を示しているのです。
つまり、「如来」とは単なる尊称ではなく、人の到達しうる究極の境地そのものを指しています。
そして、仏になるということ——「成仏」とは、私たちが普段使っているような「死後に安らかになる」という意味ではありません。
仏(ほとけ)について
長い人類史の中で、仏はこれまでにお釈迦さまを含め八仏が出現したと伝えられています。
そして、次の九仏目が、遥か遠い先の時代に出現する「弥勒菩薩」となります。
その引継ぎ役となられるのが魔訶迦葉尊者です。以下は、彼の入滅の地に訪ねた際の記事です。
これは、法華経から離れたわたしの**仏(ほとけ)観**となりますが、
人はそもそも仏には成れません。因縁が違うのです。
一方で、仏となる「もと」——つまり**仏の種(仏種)**は、誰の中にも宿っていると仏教は説いています。
その真意をすべて理解することは難しいですが、わたしはこう考えています。
「成仏」することはできなくとも、仏へと向かう方向性をもって生きることはできる。
信じるかどうかに関わらず、人として避けては通れない道がそこにあります。
そして、この道こそ、現世の利益(りやく)を超えたところで、最も理にかなった生き方だと感じています。
なぜお釈迦さまなのか?
第一の理由:地上に生きた“人”としての如来
お釈迦さまは、実際に地上に存在された人間でした。
そして、人としての生を歩み、苦しみ、悟りに至った唯一の如来です。
同じ如来であっても、大日如来や阿弥陀如来などは、そのお名前や偉大さこそ知っていますが、
その由来や生涯については、ほとんど明らかではありません。
きっと彼らもまた、私たちの遥か遠くで、見えない世界の中において重要な役目を担っているのでしょう。
しかし、お釈迦さまは違いました。
人としての痛みを知り、人として迷い、そしてそこから悟りへと至った方なのです。
だからこそ、わたしは如来の中でもお釈迦さまに、最も強い親近感と信頼を覚えます。
人としての道を歩まれたからこそ、わたしたち人間の道しるべとなる存在なのだと思うのです。
他方で、この経緯を持って、「誰でもやがては悟り仏となれる」
ーこのような誤解が生じていることをわたしは懸念しています。
これは、後日記事としてまとめたいと思っています。
第二の理由:言葉として残された“生きた思想”
もうひとつの理由は、お釈迦さまの言葉が今も残っているということです。
その多くは、弟子たちによる口伝として伝えられ、後に経典となりました。
たとえば、大乗仏教の仏典として有名な『法華経』や、原始仏教の記録であるパーリ語仏典。
今では、それらの貴重な資料を自由に読むことができる時代に、私たちは生きています。
これは、ほんとうに幸運なことです。
「人として、どう生きればよいのか?」
誰もが迷いやすいこの混とんとした世界で、
お釈迦さまは如来として、人の言葉で、生きる指針を残された唯一の存在です。
その言葉に触れるたびに、わたしは「人としての原点」に立ち返ることができます。
そこに、他のどんな神仏にも感じられない温かさと真実味があるのです。
まとめ
お釈迦さまを、なぜわたしが信奉しているのか——
少しは伝わりましたでしょうか。
お釈迦さまの言葉の中には、まるで人として生きてきた感想のような響きさえ感じます。
人として生きることは苦しみではあるが、とても豊潤(ほうじゅん)である。
この一言に、わたしは深く心を打たれました。
わたしのお釈迦さまへの信奉は、「信仰」とは少し違います。
お釈迦さまご自身も、人々に思想への傾倒を促したのであって、
ご自身への帰依を求めたわけではありません。
お釈迦さまの残された言葉には、今なお時代を超えて響く力があります。
それは、単なる教義や宗教の枠を超えた、「生きることそのものへの洞察」です。
だからこそ、願わくは——
できるだけ多くの方に、お釈迦さまの言葉に触れていただきたい。
そして、人として生きている“いま”という時間の中で、
その言葉の持つ温もりと光を感じ取ってほしいのです。