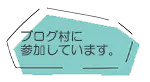はじめに
遠い昔、お釈迦さまは人のこころに焦点をあてた思想を説かれました。やがて有志の人々が、自身を高め、より良い生(せい)を求めて集い、そこに仏教のはじまりが生まれました。
仏教とは「仏の教え」と書くように、お釈迦さまの思想が「教え」となり宗教化したものです。
ところで、わたしはこの「教え」という言葉に、僧侶であった頃から違和感を覚えていました。どこか気取りがあり、他を寄せつけない排他性が漂うからです。
このため、このブログでは「教え」という語をできるだけ使わず、お釈迦さまの残されたものを「思想」や「言葉」、さらには「発見」と呼んでいます。この「発見」という表現は、インドの政治家・思想家であるアンベードカル博士の言葉に倣ったものです。
最初に申し上げておきますが、わたしは仏教という宗教体系を「失敗だった」とは考えていません。仏教には、仏説を伝えることだけではなく、人のこころを癒し、拠り所となる側面もあるからです。
ただしそれとは別に、お釈迦さまの思想が本来どのようにあるべきかを、宗教の枠を超えて改めて考えてみたいと思います。
仏教化の意味
まず「宗教」という言葉の定義を見てみましょう。
一般に、人間の力や自然の力を超えた存在への信仰を主体とする思想体系、観念体系であり、また、その体系にもとづく教義、行事、儀礼、施設、組織などを備えた社会集団のことである。
— Wikipediaより
宗教の枠組みは、概ねこの説明に尽きるでしょう。ではこれを仏教に当てはめ、こころの面に焦点を当てて考察してみます。
地球上の生きとし生けるものは、犬や猫をはじめとする動物界を含め、いずれも自己を鍛えるために存在しているといえます。その中でも人間は、もっとも豊かな経験と可能性を与えられた存在です。
しかし現代社会では、その尊い機会を享楽のためだけに使う人々も少なくありません。経済的には資本主義、政治的には個人主義が進展するにつれ、その傾向は強まっています。
娯楽や嗜好品に囲まれ、楽して生きたいと願うことが当たり前になりました。
「どうせ死ぬのだから楽しく」と言いながら、実際には死と真剣に向き合うことを避け、「楽」という言葉にすがる—そんな姿を多く見てきました。
けれども、快楽だけに生きるのは虚しい。
こころに柱を立て、自らを磨く気概があれば、快楽そのものの質を変え、別の次元の「楽」に到達することもできます。
それでも欲望中心の生き方が改まらないのは、人が「死後も因果が続く」という真理を理解できていないからでしょう。経済を優先し、こころの問題を後回しにする現代社会の構図そのものです。

多くの仏教団体が、自己統制のシステムを構築して修養を試みてきましたが、残念ながらこころの課題を真正面から扱う仕組みは、仏教界の外にはほとんど見られません。
信仰ではなく、もっと多面的にお釈迦さまの思想を育む道があってもよいのではないでしょうか。
「教え」と仏教
仏教の形骸化
「仏教とは何か」と問われたとき、思い浮かぶのは位牌、数珠、仏像、伽藍、庭園など、目に見える形が多いでしょう。

しかし、目に見えぬ「こころ」の側から仏教を見つめると、その痕跡を見出すのは難しい。ありがたい仏像の前で手を合わせても、お釈迦さまの思想そのものが心に生きていないのです。

頂戴する「教え」
仏教は「こころ」に重きを置きます。人が「人生は苦しい」と感じるのもこころであり、これをどう扱うかがすべての核心です。
「無我」「無明」「無常」「四諦」など、仏教が掲げる言葉は数多くありますが、その根本は「いかにして苦から自由になるか」という一点に尽きます。

ただし、それを理解し体得するには長い時間が必要です。
人は楽して生きたいからこそ修行が要る存在であり、そのためにこそ、この地球という学びの場があるのです。
修行は苦しみではなく、生を深く味わうための道。
しかし多くの人は、苦しみを避けるための信仰へと傾きました。鎌倉時代の「念仏を唱えれば成仏できる」という思想の登場は、その流れの象徴です。
こうして、日本の仏教は「教え」よりも「信仰」へと重心を移しました。
信仰とは、自分の拠り所を外に求めること。けれどもお釈迦さまは、生前、神への信仰も自身への帰依も求めませんでした。信仰は人を救おうとする慈悲の一面もありますが、こころの鍛錬という本旨からは遠ざかってしまったのです。
サンガからの変化
お釈迦さま在世当時の「サンガ(僧団)」こそ、仏教の本質を映す鏡でした。そこでは、戒律を守る出家者と、彼らを支える在家者の間に、清らかな相互関係がありました。
当時の布施とは金銭ではなく、残飯や宿の提供でした。現代では不可能な行為かもしれませんが、それほどに質素で、現実的でした。出家とは「家(世間)を出る」ことであり、それ以上でも以下でもありません。
今の時代こそ、むしろ出家の意義は大きいとも言えます。現代社会はこころをせわしくし、自分を見つめる余白を奪うからです。
当時のサンガには祈祷や葬儀はありませんでした。
祈ることよりも、死者の地で瞑想することこそ修行だったのです。
そして何よりも大きな違いは、いまや肝心のお釈迦さまがいらっしゃらないことです。
お釈迦さまは金色の像となり、最上段に祀られました。

その前で「ありがたや」と手を合わせても、思想はこころに届きません。像の前で頂くだけでは、こころの進化は起こらないのです。
政治と宗教
「政治と宗教は人を分け、芸術と文化は人をつなぐ」
——ある思想家の言葉を思い出します。
わたし自身、宗教の現場で十余年を過ごす中で、教義を共有しない人々との隔たりを感じ、淋しさを覚えたことがあります。宗教は政治とよく似ています。
共通点は三つです。
- 大衆の観念的劣化とともに、初期の尊い理念が失われていく
- 教団(政策集団)の維持が主目的となる
- 結果として人と人を分断してしまう
政治や宗教による「世界統一」は、美辞麗句に過ぎません。歴史がそれを証明しています。で、世界を統一しようというのは詭弁でしかありません。それは、これまでの歴史を見ればわかることです。
文化としての再構築
お釈迦さまの時代のサンガは、確かに宗教的な性格を帯びていました。しかし本来、そこにあったのは生きるための文化です。
イギリスの批評家マシュー・アーノルドは、文化を以下のように定義しました。
「人間の精神的向上を示す言葉」
お釈迦さまの言葉もまた、宗教の「教え」ではなく、人の精神を磨く文化として伝わるべきだったのではないでしょうか。
まとめ
自動車の運転は、動画を見れば理解できますが、実際にハンドルを握ると難しいものです。そのために教習所があり、試験があります。
お釈迦さまの言葉も同じです。聞けば誰もが納得できる。しかし、実践するのは容易ではない。
そして仏教には、その「試験」にあたる実地の仕組みが存在しませんでした。結果として、思想はあやふやなまま風化していったのです。
お釈迦さまは人知を超えた存在でありながら、決して神ではありませんでした。
その思想を宗教という檻に閉じ込め、祀り上げてしまったのは、わたしたち人間です。
仏教の根本分裂が起きた時点で、その衰退はある意味で必然でした。
教義の正誤ではなく、縁をもって人と人を結ぶというお釈迦さまの思想こそが要(かなめ)であるべきでした。
現代、仏教は多くの国で衰微しています。それは誰のせいでもなく、避けられない流れです。
けれども、もしお釈迦さまの思想を「文化」として育んでいたなら、今ごろもっと豊かに人々のこころに生き続けていたのではないか——そう思わずにはいられません。