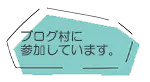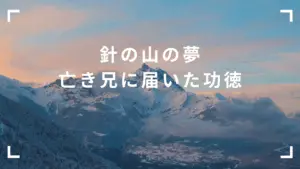注意)以下の記事には、生死に関わる微妙な内容が含まれています。
特に気の弱い方や神経質な方、霊感の強い方は、
ご注意下さいますようお願いいたします。
寺院のあるところ
わたしが出家した寺院は、数百年前の激しい戦いで数千人が命を落とした古戦場の地に建っています。巻き添えになった民衆を含めれば、その数は一万人を超えていたかもしれません。
当時は、倒れた人々を一人ひとり手厚く葬る余裕もなく、屍が累々と横たわる場所であったことでしょう。
その地にご縁をいただき、半世紀ほど前、深い山林を切り開いて寺院が建立されました。境内の外側には、いつ誰が建てたとも知れない五輪塔が今も点在し、大雨が続けば、その痕跡が土砂とともに境内へ流れ込んでくるほどです。
寺院建設の最中にも、目に見えない世界としか言いようのない出来事が、筆舌に尽くしがたいほど重なりました。
供養塔
建立当初、この一帯には、武士たちの気配が濃厚に残っていました。
当時の僧侶たちが厨房で食事をしていると、血まみれの武士が窓に張りついて覗き込んでいた——そんな話が語り継がれています。
わたしが出家した頃には供養も進み、だいぶ落ち着いていましたが、それでも同じ年に得度した方が「夜中にふと目を開けると、甲冑姿の武士が添い寝していた」という体験をしています。
境内には、寺院が建立した大きな供養塔がいくつもあります。出家当初、わたしは毎朝5時過ぎに起き、供養塔や納骨堂を巡ってお茶と水を供え、読経して回っていました。まだ暗く見通しの悪い山道を、大きなヤカンを両手に抱えて一時間ほど歩き続けるのです。
その頃には、霊がよく現れる場所も大体決まっていました。とはいえ、暗闇の中でわたしが本当に怖かったのは、霊ではなく、イノシシと鉢合わせすることでした。
武士の霊たちについて
甲冑を身にまとい、あたりをさまよう武士たちの多くは、亡くなって数百年を経た今もなお、「戦いは続いている」と信じている存在です。
彼らは本来、自らの意思で供養塔へ入り、供養を受けることもできます。
ただし、供養塔には「門番」のような存在がおり、そこへ入るには、この世への未練を断ち切り、その門番の許しを得なくてはなりません。白装束をまとい、未練なき意志を示して初めて、供養塔に迎え入れられるのです。
多くの方は、「人は死ねば自然とあの世へ行く」と思っているかもしれません。
しかし本来、それほど単純なものではありません。
ちなみに、僧侶の出家得度とは、「この世への未練を断ち切り、生きたまま自分の葬式を挙げる」ような行為でもあります。
そういう意味で、僧名とは本来、亡くなったときに授かる戒名に相当する名前なのです。
武士たちの未練
迷い続ける武士たちは、主君への忠誠心か、武士としての誇りか、あるいは意地か——いずれにせよ強すぎる思いが、彼らを戦いの場に縛りつけています。これもまた「こころの癖」の一つと言えるでしょう。
戦国の武士たちは、常に裏切りと死が隣り合わせの世界に生きていました。血で血を洗う日々の中で形成された心の緊張は、並大抵のものではなかったはずです。その極限状態で刻み込まれた癖が、数百年を経ても解けないことは、むしろ自然なことかもしれません。
その一方で、そうした時代を生きながらも、供養塔に入ることができた武士たちもいます。
そこには、現代人が失いつつある「覚悟」や「こころの強さ」もあったのでしょう。
むしろ、欲望にまみれ、この世への未練ばかりが肥大した現代人の方が、あの世へたどり着くのに、戦国の武士以上の時間を要するのではないか——そんな風に感じることもあります。
おわりに
戦い続けることで幸せになれるはずもないのに、固くこわばった信念にしがみつき、さまよい続ける存在たち。
そうした姿を見ると、人間という生き物の切なさ、哀しさを痛感せずにはいられません。
今回は、わたしが過去に出家した寺院のある土地の事情を、ほんのさわりだけお話ししました。
いま風に言えば「事故物件」と言える場所かもしれません。しかし、たまたまそこに建てられたのではなく、あえてその地を選び、その歴史と向き合う場として寺院が建立されたこと——そこに大きな意味があります。
語るべきことは、まだ数え切れないほど残っています。
長くなってしまいますので、今回はこのあたりで区切りとし、次回は「目に見えない世界」について、もう少し掘り下げてお話ししてみたいと思います。