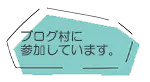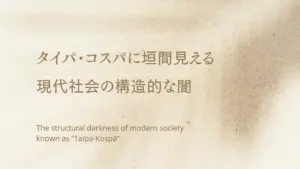はじめに
故郷で、大正生まれの母と暮らしていた頃のことです。わたしはある種の「喪失」を目の当たりにしていました。
土地固有の記憶を宿した食べ物や暮らしの品々、さらには原風景としての情景までもが、均質化された都市郊外の風景――いわば「コピペされたモザイク」へと、次々に塗り替えられていったのです。
古くから続いてきたものが、音もなく消えていく。わたしと母はその変化を、すぐそばで見つめていました。
それは、わたしと母の思い出が少しずつ薄れていくというだけの話ではなく、「ここに在る」と確かめられる場所と時間――自分の生を支えてきた枠組みそのものが、消滅していく過程でもあったのです。

町は、絶え間なく前へ前へと進んでいきます。けれどその速度は、ときに個人の来歴や、日々の暮らしが育んできた「手触り」さえも置き去りにしていきます。
家族が歩んできた歳月さえも剥ぎ取るように変貌していく街並みを前に、母がふと見せた寂しげなまなざしを、わたしは今でも忘れることができません。
「なぜ、すべてを壊してしまうのだろう」 「どうして、すべてを新しくしなければならないのだろう」 「なぜ、人との距離はこんなにも遠くなってしまったのだろう」
わたしはこれまでの人生を、これらの「問い」と向きあって生きてきたと言っても過言ではありません。そして辿り着いたのが、現代社会における「生きる手触りの喪失」という切実な事実でした。
現代社会における「生老病死」のブラックボックス化とは、これから育っていく世代の問題である以前に、すでに生きてきた人々からも、「生きる手触り」を奪っていく出来事でした。
これまで向けてきたまなざしの先に見えてきたこのような結末を基にして、「問い」の大切さと、わたしたちがこれから出来ることを述べたいと思います。
既定路線にまで高められた空気感
それは、単なる「個人のこころの持ちよう」では太刀打ちできないほど、社会構造そのものがお釈迦さまの思想とは真逆の方向へ、強固にシステム化されている現状を物語っています。
その基になっているものは、かつて「豊かになるための手段」であった効率化が、現代では「社会に留まり続けるための条件」に変容していったためです。
つまり、現代社会というシステム化されたベルトコンベアーから降りることが、そのまま「置き去りにされてしまうのではないか」という不安と、常に背中合わせであったのです。
お釈迦さまは、生老病死(苦)を「人間の本質的な属性」として認め、それと共に生きる道を示しました。しかし現代社会は、あらゆる苦しみを「まだ解決されていない技術的課題」として扱います。
「孤独」はマッチングアプリで、「老い」はエイジングケアで、「病」や数値化された医療で、「死」は延命技術や(将来的な)デジタル保存といったように。 このように「苦」がすべて「技術的に解決できるはずのもの」に分類されてきました。

そのため、解決できない苦しみ(自然な老いや死)を抱えることは、単なる「管理不十分」や「努力不足」と認識されるような空気感が社会全体に漂っています。
わたしがとても居心地がよくない要因と思っているのが、この既定路線にまで高められている空気感です。
「内省」の時間を奪い続ける情報の嵐
元来、人間の「生老病死」の苦しみは、自身に取り込んで、受け入れていくものです。しかし、この「受け入れましょう」という言葉が、現代の文脈では「弱音を吐いている」かのように響いています。
他方で、生きていくための智慧は、静寂の中での深い洞察(内省)から生まれます。しかし、現代社会は生産性の下、わたしたちの「隙間時間」まで削ろうとするシステムが作り出されてます。
その背後で基本的な役割を果たしているのが、広告やSNS、そして絶え間なく届く通知といった情報の仕組みです。

わたしたちの意識は常に「外側」に向けられ、消費と反応を繰り返すよう作り直されています。「自分の内面を見つめる」行動そのものが、現代の環境下では、後ろ向きであると捉えられ、その社会通念が深刻な退化といっていいほど人間力の低下を引き起こしているのです。
個人で克服しようとする努力が、次の瞬間には別の「刺激的な情報」に上書きされ、血肉になる前に流されてしまうのが現状です。
非力な個人
わたしは、このような現代社会に埋没してしまっている「生きる手触り」を取り戻すことが肝要だと信じています。
しかし、現代社会という巨大な要塞に対して、わたしたちが提示できるどのような処方箋でも、「爪楊枝で城壁を削る」ような頼りなさを秘めています。
一方で、病理があまりに巨大で「全能」を謳うからこそ、対抗策は「非力」で「小さく」なければならないとも思っています。
- 「効率」に対抗する「無駄」
- 「全能」に対抗する「弱さ」
- 「加速」に対抗する「立ち止まり」
これらは、現代のシステムから見ればまさに「価値のないゴミ」に見えます。しかし、そのゴミの中にこそ、システムがブラックボックス化した「人間としての生老病死のリアリティ」が隠されています。
立ち位置を見定める
現代社会における市場経済のシステムは自らの欲求のために突き進む巨大な生き物です。生み出してきた病理があまりに進んでいるため、もはや「社会全体を癒す処方箋」を作り出すことは不可能に近いでしょう。
そう考えると、個人が出来ることは「新たに社会を治すための薬」を編み出し広めることではなく、巨大なシステムという監獄から、人間としての尊厳を取り戻すための「亡命ガイド」を示すことだと言えます。
社会が「もっと速く、もっと強く」と叫ぶ中で、もし居心地の悪さを感じているならば、「そうだ、自分はこれほどまでに不自由な世界にいたのだ」と気づくこと。
すべてに追いつこうとしなくていい。 そして、「追いつく必要のないもの」を、勇気を持って見分けること。
その小さな気づきと決断こそが、社会というブラックボックスの中に閉じ込められた「あなたの生きる手触り」を照らしていく、最初の光になるのではないでしょうか。
問いの意味
わたしが長いあいだ抱えてきた「問い」は、あまりにも速く流れていく社会の中で、こころが追いつかないまま、宙に浮いていました。
追いつけないこころを抱えたままでいると、いつしか考えることそのものが止まり、頭の中が空白になっていく。そんな状態を、どこかで「これでいい」と受け入れてしまっている自分に、ふと気づいて、はっとしたことが何度かあります。
けれども、出家というかたちで、自分自身と向き合う時間を取り戻す中で、「老い」に直面したわたしは、それらの「問い」をあらためて「問い直す」機会を得ました。
そして次第に、お釈迦さまの智慧や、先人たちが紡いできた思想さえも覆い隠すほどの巨大なシステムの中に、自分自身が置かれている状況を見いだせるようになっていったのです。
まとめ
わたしの「問い」に、はっきりとした答えはありません。
それでも、問い続けることそのものが、生きているという手触りを、こちらへ引き寄せてくれる力になる――そのことを、わたしは信じています。

わたしの場合、「老い」をきっかけとして、その先に連なっていく「病」や「死」、さらには若い頃から抱え続けてきた「問い」が、再び浮かび上がってきました。これまで、それらを一つひとつ、「自分の生き方」に落とし込んできました。
市場経済の加速に身を委ね、次々と現れる新しい事象に満たされた世界で、不足なく生きる人々もいるでしょう。若くて健康体であるならばなおさらです。
しかしその一方で、「老い」は誰にでも訪れてきます。「老い」という現実に直面したり、「病」や「死」と対峙せざるを得なくなったとき、わたしたちの内には、それまで蓋をしていた根源的な「問い」が芽生え始めることがあります。
何が「問い」を呼び起こすかは、人それぞれです。ただ、自分の内側に生まれた問いを、あきらめずに抱き続けること。それこそが、何より大切なことだったのだと、いまは感じています。