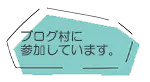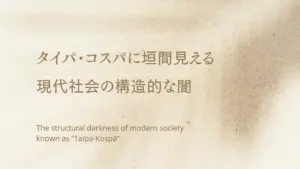はじめに
今回は、わたしが、この社会に抱き続けている違和感に関することと、行き過ぎた市場経済に警鐘を鳴らしていた思想家についていくつか紹介しておきます。
そして、なぜそれらの思想がわたしたちに浸透しなかったのかを考察してみます。
社会への違和感
わたしたちは、清潔で整えられ、便利に設計された世界に生きています。とりわけ日本は、その恩恵を日々の暮らしの隅々にまで行き渡らせてきた国だと思います。
それでも、わたしは若いころから、どこか居心地の悪さを抱えたまま生きてきました。
「これほど豊かな暮らしの中にいて、何を贅沢なことを言っているのだろう」
そんな思いで、自分の中に芽生える違和感を、打ち消すようにしてきた時期もあります。
わたしの場合、出家に至るまで、内省を軸にした生活を送ってはいましたが、その居心地の悪さの理由を、あらためて掘り下げようとはしてきませんでした。どこかで、言葉にすることを避けていたのかもしれません。
ただ、寺院を離れた後も、社会と接するたびに、「このままで本当に良いのだろうか」という感覚が、完全に拭い去られることはありませんでした。

確かに、内省の末に行き着いたお釈迦さまの思想から見れば、そこから自然に立ち上がってくるはずの社会のあり様と、現実の社会とのあいだには、大きな隔たりがあります。
「それが五濁悪世だ」と言ってしまえば簡単ですが、わたしが感じていた違和感は、その乖離だけでは説明しきれないものでした。もっと奥深いところにまで入り込んだ、社会の病理のようなものがある――そんな感覚を、拭いきれずにいたのです。
つまり、お釈迦さまの思想そのものに触れる前に、現代社会が生み出した別の困難が、取り巻く大きなベールとなって、大きく立ちはだかっていると感じ始めていたのです。
思想家に出会った経緯
それでも、わたしは、その感覚を誰かに投げかけたり、疑問として口にしたりする機会はほとんどなく、問いを発すること自体が、どこか避けられているような空気がある――その社会のあり様にも、わたしは長く違和感を抱いてきました。
そうした社会への感覚を、少しずつ言葉に落としていくうちに、ひとつの事実が見えてきました。それは、清潔さや便利さが増していくことと、「生の手触り」が濃くなっていくこととは、必ずしも同じ地平に並んでいない、ということです。
むしろ近年では、両者が互いにすれ違う方向へと進んでしまうような状況さえ、目立つようになってきています。
そして、この「すれ違い」については、早い段階から警鐘を鳴らしていた思想家が、決して少なくなかったことも分かってきました。市場経済が盲目的に進んでいく現代社会に、疑問を抱いていたのは、どうやらわたし一人ではなかったのです。
警鐘を鳴らした思想家たち
市場経済が社会の隅々まで浸透していく過程で、「人間の尊厳」や「生の在り方」が変質してしまうことに、早い段階から警鐘を鳴らしていた思想家たちがたくさんいました。その中からいくつかを簡単にご紹介いたします。
興味のある方は調べてみると良いかと思います。
- マイケル・サンデル(Michael Sandel)
-
現代で最も有名な政治哲学者の一人です。著書『それをお金で買いますか』の中で、彼は「市場経済(経済活動を組織するツール)」が「市場社会(あらゆるものに値札がつく生き方)」へと変貌してしまったことを批判しました。
- フィリップ・アリエス (Philippe Ariès)
-
『死を前にした人間』(1977年)や『図説 死の文化史』(1983年)は、西欧における死の表象と儀礼の変遷を多くの図像資料から分析し、近代における「死の隠蔽」傾向を示した。
- カール・ポランニー (Karl Polanyi)(紹介済み)
-
労働(人間)や土地や貨幣のようなものは本来“商品ではない”のに、市場社会はそれらまで商品として扱わざるを得ず、その歪みが共同体や暮らしの基盤を壊すと警告しました。
あわせて読みたい 自分の「在る」を取り戻すために 自分の「在る」を取り戻した先に「幸せ」は見えてきます。「社会の外へ出る」ことなく、市場経済が作り出してしまった構造に流されることなく、余白を日常の中に残す方法について書いてみました。
自分の「在る」を取り戻すために 自分の「在る」を取り戻した先に「幸せ」は見えてきます。「社会の外へ出る」ことなく、市場経済が作り出してしまった構造に流されることなく、余白を日常の中に残す方法について書いてみました。 - ミシエル・フーコー(Michel Foucault)
-
権力は外側から人を押さえつけるだけでなく、わたしたちの内側に入り込み、「自己管理」や「自己投資」を当然のことにして、人が自分自身を“企業”のように扱う主体へ変えていく、と描き出しています。
こうした警鐘は、決して一部の悲観論ではありません。むしろ「便利さ」や「豊かさ」と引き換えに、何が次第に失われるのかを、先回りして言葉にした試みでした。にもかかわらず、なぜその声は、わたしたちの生活に十分届かなかったのでしょうか。
市場経済への希望と欲望
市場経済が走り始めた近代において、発展が「豊かさへの希望」と結びついていたことです。そのことについては、わたしの体験という狭い範囲からではありますが、以下の記事でも触れています。

そして、実際、生活が楽になり、物が手に入り、寿命も延びていきます。多くの人にとって、変化はまず“恩恵”として体験されました。近代を経て、人々の希望が一通り叶ってくると、それが次第に「欲望」へと変わっていきます。
「欲望」という強力なエンジンを得た市場経済は、急速に発展していきます。
市場経済が得意なのは、「待たせないこと」です。
人の尊厳や共同体のようなものは、時間をかけて築くしかありません。けれど、市場が提供する快適さは、ボタン一つで手に入るほど分かりやすい。だからこそ、わたしたちはそちらに流されやすくなります。
短期的な快楽が、次第に進んでいった長期的な人間性の喪失から染み出してくる不安というものを覆い隠してしまったのです。
時間の錯誤と空気
市場経済における問題は、ゆっくり進んでいきます。
社会の根が傷むとき、崩壊は派手な音を立てません。気づいたときには、暮らしの手触りや人間関係の作法が、別の規格に置き換わっている。しかも、その変化は「個人の努力不足」や「自己責任」として処理されがちです。

本来は構造の問題なのに、わたしたちは自分の内側だけを責め、こころの疲弊を“自分のミス”として抱え込みます。すると警鐘は、社会批評などではなく、自分に向かうベクトルとなり、生活の現場から遠ざかっていってしまいました。
気がついたときには、誰もその本質に触れようとさえしなくなっています。わたしが、言葉にして問うことをしなくなっていった理由の一端がここにあると思われます。
市場経済が加速させる変化の激しさは、人々の追随を許さず、あらゆる深刻な問いを「古い話題」として大衆の空気の中に埋没させ、陳腐化させていくのです。
まとめ
現代では、情報の流れそのものが、警鐘を受け取りにくい形になりました。
短い刺激、分かりやすい成功談、すぐ役立つハウツーが優先され、時間のかかる問い——「人間の尊厳とは何か」「この豊かさは何を削っているのか」——は、後回しにされます。
警鐘は“正しさ”よりも“耳あたりの良さ”で選別され、目に触れる前に沈んでいく。こうしてわたしたちは、仕組みの外ではなく、仕組みの中で忙しく生き続け、気づかないまま、仕組みが望む形に自分を調整してしまいます。
本ブログの焦点は、まさにこの点にあると思っています。
市場経済そのものを否定するのではなく、わたしたちがいつの間にか「測れるもの」へと還元され、こころの居場所や、暮らしの手触りや、人との間合いを失っていく過程を、できるだけ具体的に言葉にしていきたい。
そして、警鐘が聞こえなかったのはわたしたちが鈍いからではなく、聞こえにくくなる条件が社会の側で整っていたからだ、という視点を共有したいのです。
そこから先に、失われたものを回復する道筋——大げさな変革ではなく、日々の暮らしの中で取り戻せる小さな転換——を探っていきたいと考えています。