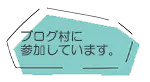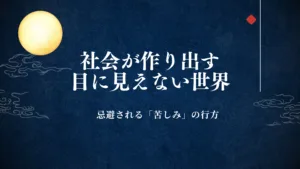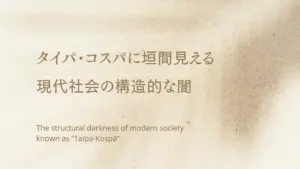はじめに
気がつけば、2025年も終わりに近づいています。
近所には生協の店舗があり、地元の食材が豊富で年末の食材をそこで買い求めるのが、
ここ数年のわたしの習慣になっています。
店内を見渡すと、買い物に訪れているのは、
ほとんどが六十五歳以上の方々です。
この地に越してきた当初から利用してきた店ですが、
年末特有の賑わいは、少しずつ薄れてきたように感じます。
あと五年ほど経てば、
この店も、いつの間にか姿を消してしまうのかもしれません。
福岡は、比較的人口の流入が多い都市だと言われていますが、
それでも、全体としては人口が確実に減りつつあることを実感しています。
さて、近代から現代にかけて、日本の暮らしは変わりました。
町内会、寄り合い、近所の顔見知り。用事がなくとも交わされていた挨拶や雑談。そういった大小の「中間コミュニティ」が、少しずつ痩せていったのです。
その変化は、単に“便利になった”“自由になった”という話では終わりませんでした。
人が平穏に暮らすために必要だった、目に見えない緩衝材が、薄くなってしまいました。

一方で、上で取り上げたような中間コミュニティのよさを知っている人ほど、
その居心地の良さを大切にしたいという思いが強くなる傾向があります。

ですが、古い体質の組織が、しがらみとして感じられると、
そこから距離を取りたくなる人も少なくありません。
今回は、中間コミュニティの可能性について書いてみたいと思います。
中間コミュニティの役割
たとえば昔は、転びそうな瞬間に、誰かが手を伸ばしてくれました。
大げさな救済ではありません。言葉一つ、視線一つ、ちょっとした手伝い。
それらが、誰かの暮らしの「荒れ(ノイズ)」を、小さく食い止めていたのだと思います。
「中間コミュニティ」に限定されず、こうした社会全体に年齢層の垣根を超えた緩やかなつながりが形成されていた時代でした。これは、昭和後期以降の世代から見れば、
昭和前・中期生まれの人間が抱く、どこか懐かしさを帯びた憧れのように映るかもしれません。
しかし、わたし自身の実感としては、
少なくとも中学生の頃までは、
中間コミュニティは平穏な暮らしを支えるために、
表に出ることは少なくとも、陰に日向に確かに機能していました。
また、「昭和」という時代区分をいったん外してみても、
わたしの娘が小学生だった頃までは、
町内会・子ども会もまだ何とか形を保ち、夏祭りやささやかな行事が行われていました。
その規模は決して大きくありませんでしたが、
同じ町に住む子どもや親の顔を互いに知っていることと、
まったく知らずに暮らすこととでは、
その後に感じる距離感に、確かな違いがあったように思います。
たとえ一時的で薄い縁であっても、
同級生たちのその後をどこかで聞いたり、大きくなった姿を思い起こすとき、
そこには、確かに共有されていた時間の重みがありました。
近年では、家族を持つ人も次第に減り、
子どもが人と人とをつなぐきっかけになる場面も、
少しずつ少なくなってきました。
これは、家族や子を持つことの良し悪しの問題ではありません。
そうした変化の積み重ねの中で、
町のあり方そのものが、次第に姿を変えてきたのです。
困っている人が見えにくい。
見えても、踏み込んでよいのか分からない。
そして人々も、助けを求めるより先に、孤立していく。
さらに厄介なのは、この社会が「価値観の多様化」という名のもとに、
同じ場所で暮らしながら、互いの“前提”を共有しづらくなっていることです。

何が正しいか、何が大切か。そこから始めた瞬間に、会話は分裂しやすくなる。
だから私たちは、つながりを欲しながら、つながりを恐れるようになりました。
ここに、現代社会、特にここ10年の大きな不安定さがあります。
距離感の再考
中間コミュニティの中で、価値観を共有しようとしたり、
温度感を揃えようとしたりすると、関係は一気に濃くなります。
一見すると、それは望ましい姿に見えるかもしれません。
しかしその一方で、先の記事で触れた例のように、距離を保ちたい人、静かに関わりたい人は、
次第に居心地の悪さを覚えるようになります。
仲の良さは、関係を深める力であると同時に、
合わない人を外へ押し出してしまう力も持っているのです。

よく考えてみれば、私たちは誰かと深く分かり合わなくても、日常を営むことができます。
顔を知っている、名前を知っている、困ったときに思い浮かぶ。
たったそれだけの関係でも、人は社会の中で孤立せずに生きていける。
かつて自然に存在していた中間コミュニティは、
この「薄いけれど切れない縁」を無理なく保っていました。
では、どうすればよいのでしょうか。
もし、いま改めて中間コミュニティをつくり直すとしたら、
必要なのは壮大な理念でも、熱い連帯感でもありません。
仲良くならなくていい。価値観を共有しなくていい。関わり方に濃淡があっていい。
目的はただ一つ、生活がほんの少し円滑になること。
それ以上を求めた途端、関係は重くなってしまいます。
そして何より大切なのは、「関わらない自由」を最初から内包していることです。
参加しない人、距離を取る人、一時的に抜ける人。
そうした選択を問題にしないだけで、コミュニティは驚くほど軽やかになります。
属するか、切るか、という二択から、人は解放されるのです。
まとめ
中間コミュニティは、居場所である必要はありません。
むしろ、仕事と家庭から少し違う方向にある「余白」のようなものであれば十分です。
普段は影のようにあって、必要なときだけ、ふっと立ち上がる。役割が終われば、また戻る。
そのくらいの存在感が、いまの社会にはちょうどいいのかもしれません。
仲良くはないけれど、それでも、完全には切れていない。
そんな関係が一つあるだけで、人は社会から零れ落ちずに済みます。
中間コミュニティとは、人を縛る場ではなく、戻ってこられる場所であるべきなのでしょう。
わたしの住む町内では、保護者の負担感が大きくなったことから、
子ども会がなくなってしまいました。
その事情は理解できますし、尊重されるべき課題でもあると思います。
ただ、学校や家庭、そして塾や習い事といった、
目的が明確に定められた場だけで子ども時代を過ごすことを思うと、
どこか気がかりな気持ちも残ります。
特別な意味や成果を求められない、
ただ一緒に過ごすだけの時間が少なくなっていくことが、
子どもたちにとってどう映るのだろうか——
そんなことを考えてしまうのです。
もう一つ、警察の力は、多くの場合、事件が起きたあとに発揮されるものです。
地域におけるやわらかな治安の維持という点でも、
中間コミュニティが、少なからず役割を果たしてきたことは、
忘れずにいてよいのではないでしょうか。