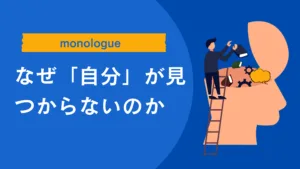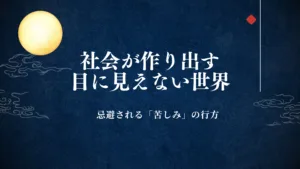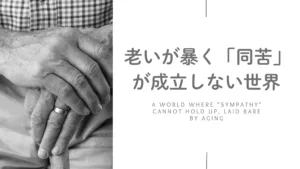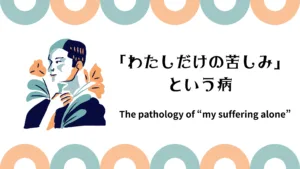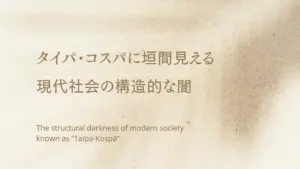はじめに
前稿では、『薔薇の名前』という作品を通じて、名と実、言葉と存在の関係について考察しました。
その中で、人々が「名」に囚われ、実を見失う瞬間にこそ、人間の苦が生じることを見ました。
今回の記事では、その象徴ともいえる劇中の一場面──「キリストの衣」をめぐる論争──に焦点を当てたいと思います。
一見、些末な神学的議論にすぎないこの場面には、宗教という制度がいかにして人の幸福から遠ざかっていくのかという、
永遠の問いが凝縮されています。
キリストの衣をめぐる論争
劇中では、修道士たちが「キリストの衣は彼の所有物か否か」という問題をめぐって激しい議論を繰り広げます。
論点はあまりに細部的で、現代の私たちから見れば無意味に思えるものです。
しかし、彼らはその問いに命を懸け、真理を守ることこそ信仰だと信じています。
ここには、信仰が制度化される過程で、目的と手段が入れ替わっていく構造がよく表れています。

お釈迦さまが説かれた「無記(むき)」の態度を思い起こすべきでしょう。
「世界は永遠か否か」「我は死後に存するか否か」―そうした問いに釈尊が答えなかったのは、
それらが苦の根源を解く助けにならないからです。
「キリストの衣」も同様に、答えること自体が迷いを深める問いだったのです。
形への執着とこころの盲点
仏説では、執著(取:upādāna)は苦の原因とされています。
外形や制度、戒律への執着は、真理の本質を覆い隠してしまいます。
『薔薇の名前』の修道士たちが議論しているのは、もはやキリストのこころではなく、
その「衣」という形をめぐる支配の問題でした。
お釈迦さまは「筏(いかだ)の譬え」でこう説かれています。
真理へ渡るために用いる思想(筏)は、岸に着いた後は手放さなければならない。
しかし人は、その筏を抱えたまま歩き続けてしまいます。

それが、宗教が信仰の手段から制度の目的へと変わってしまう瞬間なのです。
宗教としあわせの隔たり
わたしは、この論争の場面を目の当たりにしたとき、
何時の時代も繰り返される「宗教と人の幸せとの隔たり」を考えさせられたのです。

『薔薇の名前』の修道士たちは信仰の名のもとに、
実際には互いの心を傷つけ、争い、排除し合っていました。
宗教が人を救うはずのものから、人を苦しめるものに変わる。
それは中世だけの現象ではありません。
形を重んじるあまり、心の自由を見失う構図は、
現代社会における思想・道徳・政治の場にも、容易に見出すことができます。
おわりに─こころを衣とせず
『薔薇の名前』に描かれた悲劇は、宗教の本質というよりも、人間の習性そのものを映し出しています。
人は形に安心を求め、言葉に真理を閉じ込めようとします。
しかし、その瞬間に真理は言葉の外へと逃れてしまいます。
お釈迦さまが「形を離れてこころを見よ」と説かれたのは、
まさにこの人間の盲点を指してのことだったのでしょう。
宗教とは、衣をまとうことではなく、こころの裸形に立ち返ることです。
衣をめぐって争う人々の姿は、
わたしたち一人ひとりの内にある執著の影を、浮き彫りにしているように思います。
形はやがて滅びます。けれど、形に執しないこころこそ、本当の意味での衣なのです。