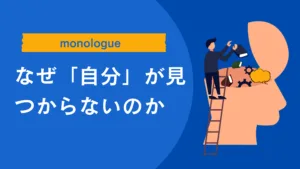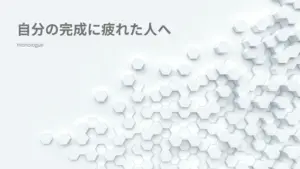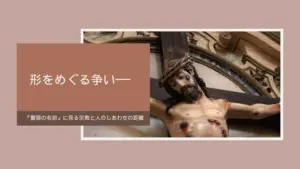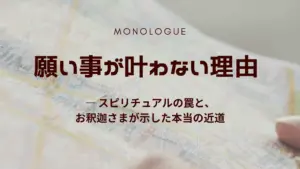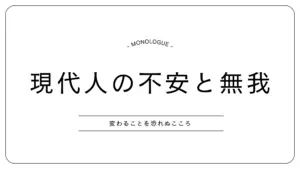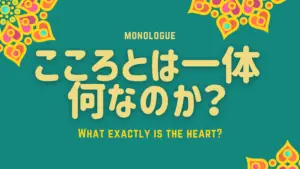はじめに
わたしが好きな映画のひとつに
主演:ショーンコネリー、監督:ジャン=ジャック・アノーの
『薔薇の名前』(1986年)があります。
この映画の原作であるウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』は、
中世修道院を舞台にした探偵譚として知られています。
この映画には、エンドロールの前に次の印象的な一文が添えられています。
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
―かつての薔薇はその名にのみ留まり、われらは裸の名を保つのみ。
題名の元にもなったこのラテン語の格言の中にこそ、作品の中心に潜む哲学的問いが凝縮されていると思っています。
存在は滅び、名だけが残る。
この一句は、言葉と現実、記号と存在の関係をめぐる深い洞察です。
そしてそれは、遠くお釈迦さまの思想にも通じる「名(みょう)と色(しき)」の問題を思い起こさせます。
今回は、少し哲学的に映画を基にしたお釈迦さまの思想について語りたいと思います。
名と実──存在を映す鏡ではなく、存在を生み出す力
お釈迦さまの思想においては、人間の存在を「名(みょう)」と「色(しき)」に分けて考えています。
名は心的・言語的なはたらき、色は物質的・現象的な世界。
両者は相互に依存しあい、どちらか一方のみでは成立しません。
この「名色(みょうしき)」の関係は、言葉と存在の根源的な結びつきを示しています。
しかし、私たちはしばしば「名」だけを握りしめ、
「色」を失ったままでも安心しようとする傾向にあります。
このラテン語の格言には、過去の薔薇を語るとき、
『私たちが目にしているのは薔薇そのものではなく、
「薔薇」という音と文字の組み合わせが喚起する観念にすぎない。』と書かれています。
すなわち、言葉は世界を映す鏡ではなく、むしろ逆で、世界を作り出す装置として働いているのです。

劇中、僧侶である主人公が生涯でただ一人想いを寄せた女性は、
名も知らぬ貧しい娘でした。
彼は、彼女の名も、生まれも、何ひとつ知りません。
それでも、彼のこころには、ただその想いだけが残っているのです。
「名さえ残らないのに、彼女の想いだけが記憶を保持し続ける」
薔薇は総称であって、薔薇そのものに名はありません。
そんな薔薇に見立てた彼女は、もはや存在しないのですが、
彼のこころの中では「想い」としていつまでも残っています。
格言の意味を“人のこころの機微”の領域まで拡張しています。
無常の理と「言葉の残存」
お釈迦さまは、あらゆるものは生じては滅し、常住するものはないとしています。
存在は流転し、どの瞬間も新しい。
これは「過去の薔薇」は、もはや世界には存在しないということです。
それでも「薔薇」という名が残り、
薔薇の香り、優美な形、様々な色合いに、わたしたちは執著します。
ここには「無常」と「記号の残存」という二つの次元が交わっています。
実体は滅びても、名が残る。
そして人はその名を通して、かつてあったものを「再構成」していきます。
それは記憶のはたらきであると同時に、
「無常を否定したい」という欲求が、こころのどこかに住み着いているためです。
名は、無常を見つめる眼を曇らせると同時に、
滅びを受け入れるための精神的な支えにもなっています。
この二重性を見極めることが、お釈迦さまの思索の出発点なのです。
3. 「空」──名辞の背後にある無の構造
お釈迦さまが言われた「空(くう)」とは、
存在が「無い」という意味ではなく、
存在が「それ自体として固定されていない」という真理を示す言葉です。
薔薇は、花弁や香り、形、時間、そしてそれを呼ぶ名など、
多くの条件(縁)によって一時的に現れているにすぎません。
それを「薔薇」と名づけるとき、
わたしたちはその複雑な縁起の過程を一語でまとめ、固定化してしまいます。
しかし、「名」はその実体を表すものではなく、
単に「指し示す音」でしかありません。
したがって、名辞は空であり、空なるものとしてしか存在しない。
この洞察は、先のラテン語の一句と重なり合います。
私たちは名辞をつかむが、そこに実体はありません。
それでも、その「空なる名」が、意味の世界を構成しているのです。
4. 言葉を超えることの意味
空が書かれてある『金剛経』にはこのようにあります。
「凡そ法は、如来が説くといえども、法ならず。ゆえに法という。」
正に禅問答の言葉ですが、要約すると次のようになります。
真理を言葉にした瞬間、それはもはや真理ではなくなる。
しかし、人は言葉を手放しては生きられません。
この逆説の中で、お釈迦さまは「沈黙」を教えたのではなく、
言葉を空として用いる智慧を示されました

言葉は実体ではない。
しかし、空なるものとして用いるとき、言葉は人を縛らない。
それは「表現」であると同時に「解放」となる。
『薔薇の名前』の一句が示すのもまた、
名と色のあわい(向かい合うものの間)を生きる人間の宿命と真の自由への可能性です。
まとめ
過去のバラは名前の中にのみ存在し、我々は名辞のみを捉える。
この自覚は、単なる懐古ではなく、認識の原点です。
私たちは名を通して世界を経験し、
名を通してしか過去と出会うことができません。
だが、その名を「実体」と思い違えたとき、苦しみが生まれてしまうのです。
名は空である。
しかし、空なる名に意味を与え、そこに思いを込めることもまた人間の性です。
お釈迦さまの智慧は、名を否定するのではなく、
名を空として抱く生き方を指し示している。
通常、人には存在に対する固執があり、
それが「空」の感得への道を大きく妨げています。
存在は滅び、名が残る。
だが、その名が空であると悟ったとき、
名の彼方に、もう一度「薔薇」が咲く。
そうすると言葉を超えた、無言の理解の世界が現れるというわけです。
例えば、縁には、人の内と外に目に見えない関係性があるだけで、カタチも意味も存在しません。
その目に見えて存在しないもの、意味がないもの(縁)から人は出来上がっています。
見方を変えれば、実体を与えられて目に見えている人は、その人自身を現してはいません。
すなわち、見えない縁を通して、人の本当の姿が浮かび上がってくる。
人はその本当の姿を見たいと、目に見える虚像にすがりついてしまいます。
このように、お釈迦さまの思想と『薔薇の名前』が交わるところに、
言葉を超えた理解への扉が開かれていると思っています。
余談ですが、調べてみると奇しくも2025年、今年の12月25日に
このウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』の完全版が刊行されるようです。