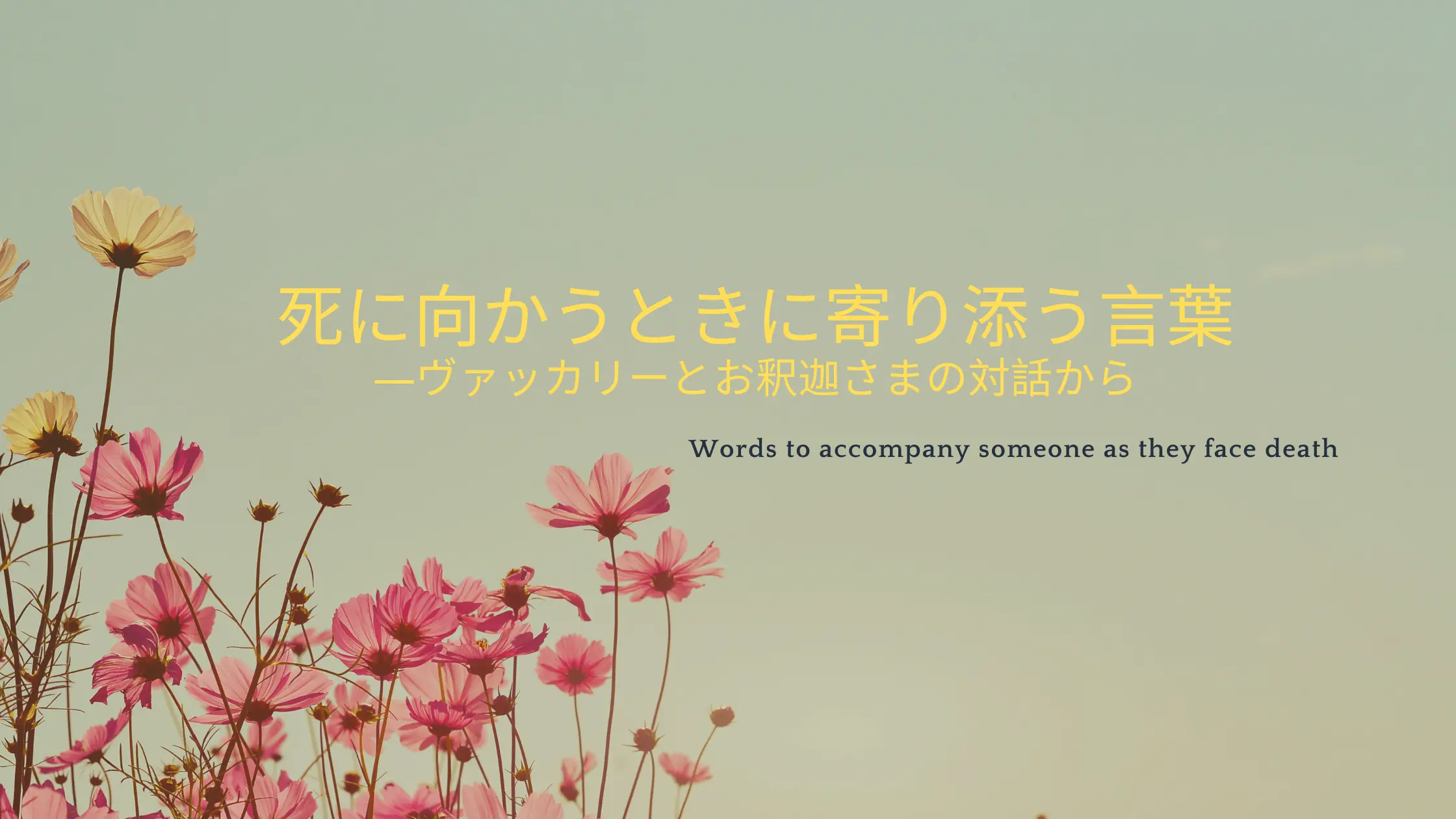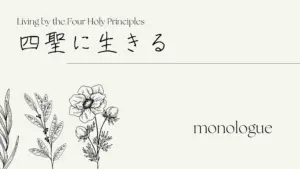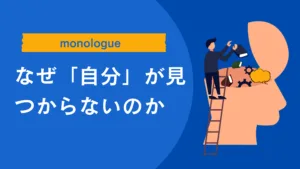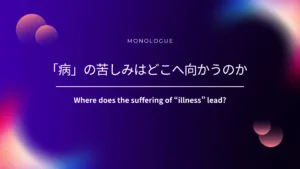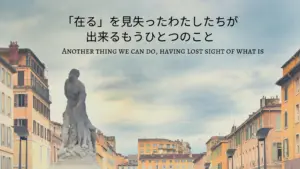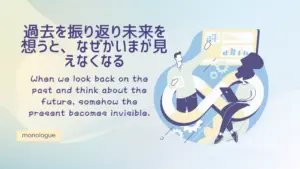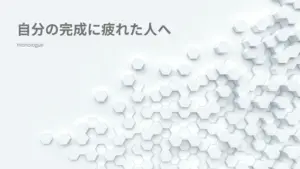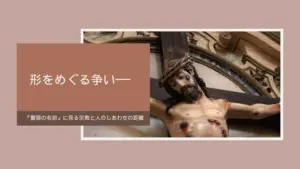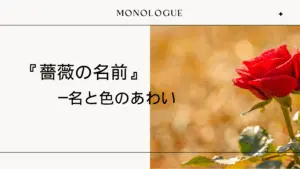はじめに
年齢を重ねると、心も体も若い頃のようにはいきません。
身体の痛みや病気、息の苦しさ、歩きづらさ……。
そうした変化は誰にも起こり、避けようのないものです。
前回の記事を作成する上で参照した古い仏典の中に、
同じように病に倒れ、死を目前にした人がいます。
名をヴァッカリーと言います。
彼は重い病床にありながら、お釈迦さまと会話をしました。
その対話の中に、現代を生きるわたしたちにも深い示唆があると思いましたので、今回の記事といたしました。
お釈迦さまが、ヴァッカリーにどのような声を掛けられたのか、
少しでも参考になれば幸甚です。
身体は自分そのものではない―老いや痛みに圧倒されないために
ヴァッカリーは弱りゆく身体を嘆きました。
しかしお釈迦さまは、こう語ります。
「この身体ばかりを見ても仕方がない。」
身体の衰えを感じると、
「自分が壊れていくようだ」と思ってしまいます。
しかし身体は自然の一部であり、
気温が変われば草木が枯れ、季節が巡れば芽が出るように、
ただ “変わる” だけのものです。

身体の変化にこころまで引きずられなくてよい。
これは、老いや病と共に生きる上で、とても大切な姿勢です。
こころは、最後の瞬間まで働き続ける―残された時間をどう使うか
身体が弱くなっても、
こころの中にはまだできることがたくさんあります。
- 大切な人に感謝を伝える
- 誰かを許す
- 怒りや後悔を少しずつ手放す
- 今日一日を丁寧に味わう
身体は老いていきますが、
こころは最後の瞬間まで変化し、変化は自分の意の範囲内です。
お釈迦さまがヴァッカリーに伝えたのは、
「いまのあなたのこころの向きが何より大切だ」
というメッセージでした。
恐れるな―恐怖は“敵”ではなく、ただのこころの動き
死を前にすれば、誰でも怖い。
それは自然なことです。
お釈迦さまもヴァッカリーにこう語ります。
「恐れなくてよい。」
しかしこれは「怖がるな」と叱ったのではありません。
「その恐れをそのまま見ていていい」という意味です。
恐怖を押し殺すのではなく、
「いま、わたしは怖いのだな」と静かに見つめる。
すると、不思議とその恐れは少しずつ沈んでいきます。

恐怖に飲み込まれない方法は、
恐怖を否定しないことなのです。
病気と「わたし」を分けると、少し楽になる
病気や痛みは確かにつらい。
でも、その痛みが「自分のすべて」ではありません。
- 痛みは痛み
- 私は私
この区別をつけるだけで、
苦しみの重さは少し軽くなります。
お釈迦さまはヴァッカリーにも、
身体の苦しみとこころの働きを切り離すよう促しています。
これは現代の心理療法にも通じる考えです。
最後に大切なのは、こころの軽さ
ヴァッカリーは死の直前、
こころの向きが澄んでいることを認められました。
それは決して“悟り”のような特別な境地ではなく、
後悔や執着を少しずつ手放していく自然なこころの変化です。
高齢期に大切なのは、
この「こころの軽さ」を育てることです。
- あのときの怒りを手放す
- 許せなかった人を少しだけ許す
- 自分を責めすぎない
- 小さな喜びを拾いあげる
- 人やモノへのこだわりを減らしていく
こころが軽くなるほど、
死は“終わり”ではなく
自然の流れの一部として感じられるようになります。
おわりに
ヴァッカリーは修行僧であり、煩悩を滅した尊者とされています。
そのため、彼とお釈迦さまの対話は、一般の人から見ると少し距離を感じるかもしれません。
しかし、どれほどこころを磨いた尊者であっても、死を前にすればこころが揺らぐ。
仏典が描くその姿は、むしろ人間的であり、私たちの日常と地続きのものです。
けれど、ただ「かわいそうに」「がんばれ」と声をかけられただけで、
死に向かう不安が消えるわけではありません。
結局のところ、死の前には特効薬も、外から与えられる“魔法の言葉”もありません。
他人の慰めが悪いわけではないものの、
私たちを本当に支えるのは外側の何かではなく、
自分のこころの向きを静かに整えていくことだけなのです。
加えて、当時のお釈迦さまの声には、文字を超えてこころを震わせる力がありました。
これは疑いようのないことです。
しかし、その肉声はもうこの世界にはありません。
だからこそ、わたしたちは残された言葉そのものに耳を澄まし、
自分自身のこころをそっと寄り添わせながら生きていくしかないのです。
わたしも死を前にすれば、ヴァッカリーと同じように動揺するかもしれません。
わたしが、その際静かに死を受け入れられるかどうかは、
この世との様々な関係性との別れ、
死が肉体の変化に過ぎないこと、
これらを如何に腑に落としめられているかにあります。