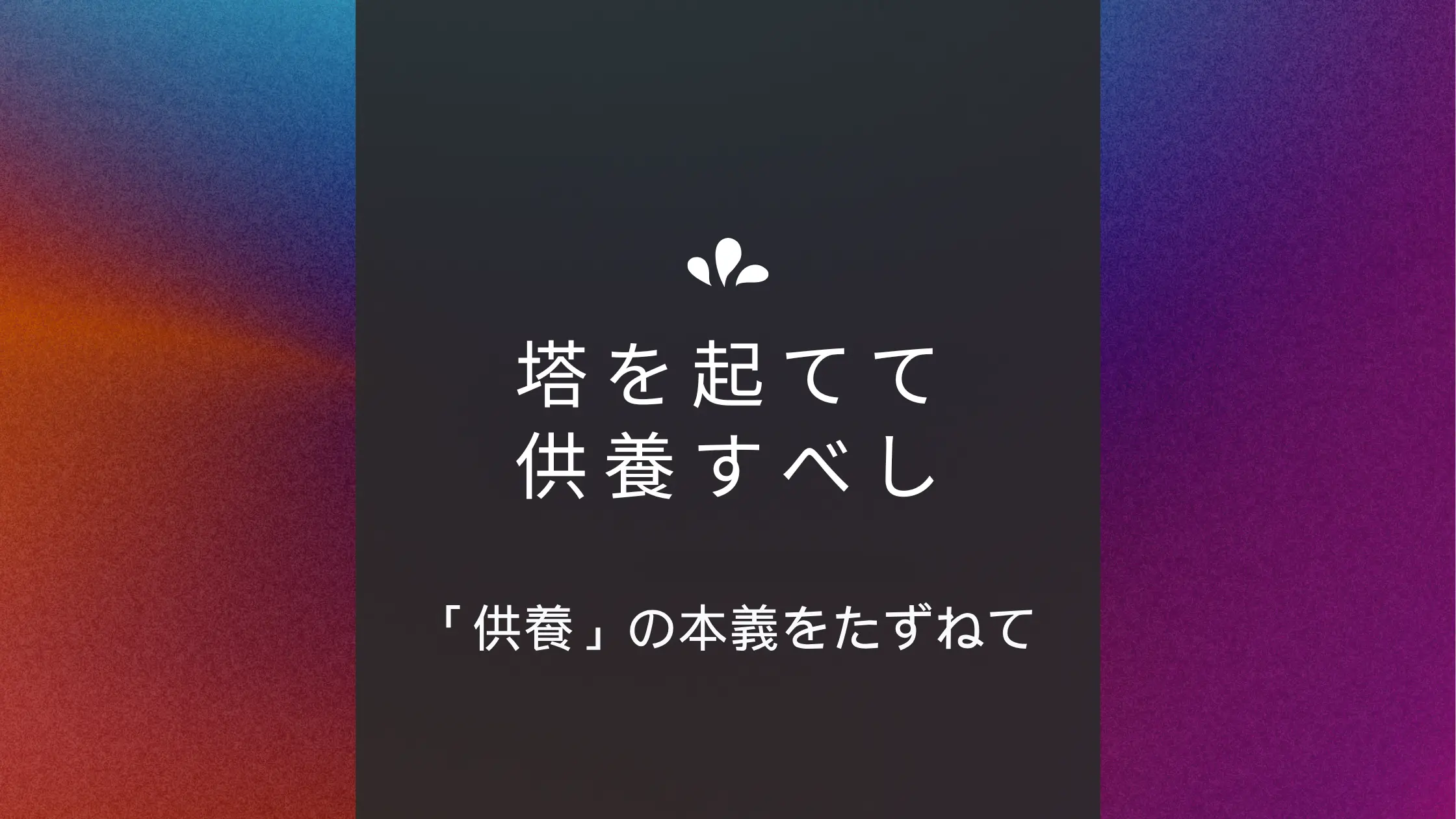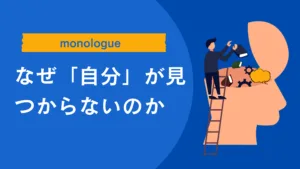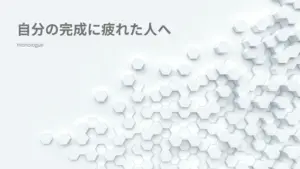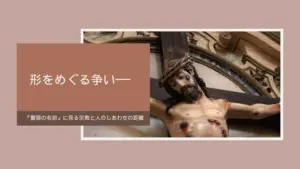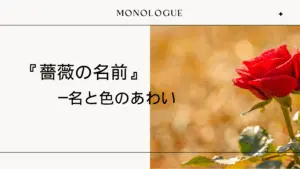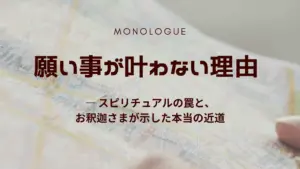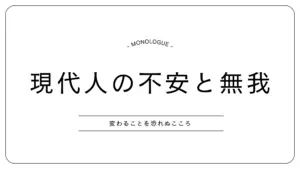以下の記事は決定的な過去生を思い出した後に、過去の記事を加筆、修正したものです。
はじめに
仏塔の形態には様々あります。
現存する仏塔の身近な例として、わたしが生まれた九州の片田舎の山のてっぺんにも、
インド・スリランカから建立された仏塔がありました。
幼かった頃、友人同士の間では「ぶっしゃりとう」と呼んでいました。
当時は異様な建築様式のせいもあってか、近寄りがたい雰囲気がありました。
日本でにおける代表的な仏塔形式と言えば、各地で見られる五重塔などが有名です。
これら各種仏塔も、南アジアの仏塔を起源にしていますが、その建立の目的は全く異なっているようです。
「塔を起てて供養せよ」
これは、お釈迦さまが入滅の直前に弟子アーナンダへ告げた言葉として伝えられています。
この一句を聞くと、多くの人は「塔=墓」や「供養=亡き人への祈り」といった、
現代的な宗教儀礼の光景を思い浮かべることでしょう。
しかし、仏典におけるこの言葉は、
単に死者を弔う儀礼を命じたものではありません。
そもそもお釈迦さまの思想に、死者そのものに言及した言葉は一切ありません。
そこには、生きる者への深い呼びかけが隠されています。
「供養」という言葉の原点
「供養」という語の原語は、サンスクリット語の pūjā(プージャー) に由来します。
この語は動詞 √pūj(プージ)から生まれ、
「尊敬する」「心を満たす」「敬意を行為として表す」という意味を持ちます。
つまり「供養」とは、
もともと尊敬と感謝を行為としてあらわすことを意味していました。
後にこの言葉が中国に伝わり、大乗仏教の流れの中で
「供(そなえる)」「養(やしなう)」と訳されていきます。
しかし、そもそも、仏を養うとは、仏を栄養するということではなく
仏の教えをこころの中で養い育てるという意味なのです。
ここにすでに、「供養」という言葉の転換点があります。
儀礼ではなく、こころの実践
お釈迦さまの時代、
「塔(thūpa)」は遺骨や遺品を納めるための単なる建造物ではなく、
法を記憶するための象徴でした。

仏教信仰者であるアショーカ王などの当時の統治者が、パキスタンのタキシラをはじめ、いくつもの仏塔を建て信奉していた痕跡が、土台のみですが遺跡として残っています。
左画像:中央の大塔を囲む形で小塔と祠が並ぶパキスタンのダルマラージカーのストゥーパ遺構
弟子たちは、塔を前にして祈るのではなく、
塔を通して「法を思い出す」ことを目的としていました。
つまり「塔を起てて供養せよ」とは、
「仏塔を建てて、わたしの言葉を思い起こしなさい」
「その教えを、あなたの生き方として養いなさい」
という意味にほかなりません。
サンガにおける供養と祭祀の実際
ここで重要なのは、この「供養」という言葉が、
お釈迦さまの組織した**初期サンガ(Saṅgha)**において
どのように理解され、実践されていたかという点です。
結論からいえば、お釈迦さま在世中のサンガには、
祭祀(yajña)や宗教的儀礼としての供養は存在しませんでした。
お釈迦さまはバラモン的祭祀を明確に否定し、
「行為の価値は外的儀礼にあらず、意志と智慧にあり」と説かれています。
「バラモンは火を祭るが、如来の弟子は心を浄めて供養とする。」
(『スッタニパータ』Sn 81–83)
「供物を投げ入れる火を求めるな、智慧と慈悲の火こそ真の供養である。」
(『テーラガーター』Thag 368)
つまり、サンガにおける供養とは、
外的な儀式ではなくこころの清浄と慈悲の行為そのものでした。
次に初期仏典における「供養」について辿ってみましょう。
初期仏典が語る「供養」
初期の仏典において、「供養(pūjā)」という語はたびたび登場します。
しかしそれは、神への祈りでも、死者の儀礼でもなく、
法への敬意と実践を意味していました。
- 『大般涅槃経(Mahāparinibbāna Sutta)』では、
釈尊の遺骨を塔に安置し供養せよと説かれますが、
それは「法を記憶し継承するための象徴」であって、
神聖視ではありません。 - 『サンユッタ・ニカーヤ』にはこうあります。
> 「如来を供養するとは、法を実践することなり。」
すなわち供養とは、法を生きることそのもの。 - 『ダンマパダ』第24章第354偈も同じ精神を示します。
> 「布施の中で最も勝れたものは、法施(法を供養)すること。」
このように、当時の供養は倫理的・実践的な意味合いを持ち、
今日のような祭祀とは無縁でした。
布施と供養──在家と僧の関係
サンガの生活は、在家信者の布施(dāna)によって支えられていました。
しかしその布施は、見返りを求める功徳ではなく、
尊敬と感謝の表現でした。
Vinaya(律蔵)にはこう記されています。
「在家が供養を行うとき、僧はそれを受け取ることによって法を示す。」
(Mahāvagga VIII, 20)
つまり、在家の行為も僧の受容も、ともに法を介した相互供養だったのです。
現代語訳でいえば─
もし「塔を起てて供養せよ」を現代語で言い換えるなら、こうなるでしょう。
「自らの中に塔を建てよ。そこに、あなたの尊ぶこころを宿せ。」
お釈迦さまが求めた「供養」は、
外にある塔を飾り立てることではなく、
内なる塔を築き上げ、そこに敬意と感謝を満たすこと。
仏典における「pūjāṃ karohi(供養せよ)」は、
「礼拝せよ」ではなく、
**「尊敬と感謝を行為として生きよ」**という本義だったのです。
仏塔供養に込められた“くびき”からの解放
仏塔(stūpa)を供養するという行為は、今日の仏教文化ではしばしば
「塔に祈る」「塔を崇拝する」
といったイメージで捉えられています。
しかし、初期仏教における仏塔は決して偶像そのものではなく、
むしろ偶像崇拝を避けるための象徴的構造物でした。
仏塔は人の形からは遠く、象徴としての意味は強い形体です。
お釈迦さまは、病身のためにお釈迦さまに会いに行けないヴァッカリーに対して、
仏典の中で次のように語られています。
「法を見る者は私を見る。私を見る者は法を見る。」
(Saṃyutta Nikāya 22:87 ヴァッカリー参照)
私(お釈迦さま)=法であると強調され、形あるものの無常をヴァッカリー尊者との会話で再確認します。
最も、仏典を例に挙げるまでもなく、お釈迦さまが形あるものに象徴的な意味を見出さなかったのは、その思想からすれば必然です。
形あるものには、そこに“我”を投影する危険性があります。
仏塔はそのために、ある意味で「無像」の象徴でもありました。
ここには、偶像崇拝(idol worship)を批判する宗教思想の系譜と響き合うものがあります。
一般的には、
「偶像崇拝の否定はイスラムの専売特許」
と思われがちですが、実際には仏教も最初期において強い否定を持っていたのです。
その否定の仕方は“力で禁じる”のではなく、
象徴を提示しつつ、その象徴にこころを縛られない方向へ導くものでした。
すなわち仏塔の目的は、
外に対象をつくって拝むことではなく、
それを通して 無常・無我・縁起を思い出す“記憶の装置” とすること。
仏塔は崇拝の対象ではなく、
執着を離れるための仕組みとして設計されています。
その意味では、
仏塔供養に込められた精神は、
「偶像崇拝を否定する」というより、より正確には
偶像崇拝の“くびき”からこころを解放するための象徴
とも言えます。
魂の否定と縁起の供養
ここで一つ、見落としてはならない点があります。
お釈迦さまが説かれた「供養」は、
魂(ātman)という恒常的存在を前提としないということです。
また、サンスクリット語における魂は、「我と同一の意味を有する」ことも見逃してはいけません。

供養とは、魂を慰めるための行為ではなく、
縁起と因果の流れを見つめ、法のつながりを生きることそのもの。
「存在は縁より起こり、縁より滅す。
その中に『我』と呼べるものはない。」
(『サンユッタ・ニカーヤ』Ⅲ, 132)
供養とは、この「我なき法則」を自覚し、
生命の流れに感謝をもって参与することです。
そこに“魂の救済”という観念はなく、
法を生きる者としての責任と敬意があるのみです。
おわりに──内なる塔を建てる
お釈迦さまが遺した「塔を起てて供養せよ」という一句は、
建造物を立てよという命令ではなく、
こころの中に法を記憶する場所を築けという、
時代を超えたメッセージです。
私たちが日々の暮らしの中で、
誰かへの感謝を思い出すとき、
過去の恩を静かに振り返るとき、
すでにその行為そのものが「供養」です。
法華経には、「仏塔は虚空にあって、多宝如来と共にお釈迦さまの久遠の魂が宿る」と説かれています。
しかし、これはあくまで法華経が描く独自の世界観であり、お釈迦さま本来の思想とは異なるものです。
塔とは、形あるものではなく、
**こころの中に立ち上がる“記憶と敬意の象徴”**なのです。
また、もし目に見える形で仏塔を建て、そこを開眼した場合、
その場所は、時空を超えて、戒律守り、お釈迦さまの法を実践していくための宣言の場。
すなわち「お釈迦さまの思想を身を尽くして実践していく場」であり
ーメルクマール”目標達成のための重要な指標や基準”という意味合いとなります。