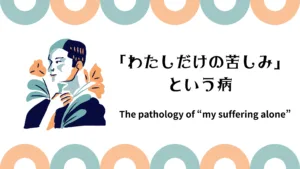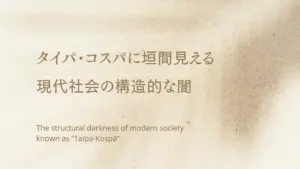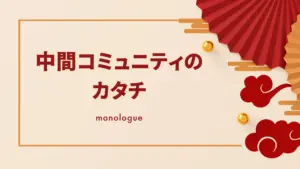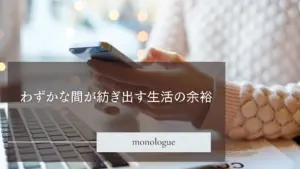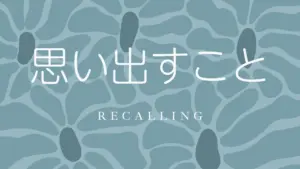はじめに
人が生きていくうえで、多かれ少なかれ「しがらみ」というものがあります。
それは、社会に覆われた目に見えないベールのようなものです。
生きにくさの要因のひとつともなっています。
では、そのしがらみとは一体誰が作り出しているのでしょうか。
また、それはどこにあるのでしょうか。
人の外にあるものなのか、それともこころの内側にあるものなのか。
あるいは、もっと深いところにある「根源」的な何かなのでしょうか。
今回は、そんな日々感じていることを、思うままに綴ってみたいと思います。
見えない壁 ― 社会が作る線引き ―
宗教、ジェンダー、思想――
こうしたテーマに触れるとき、私たちはどこかで立ち止まってしまいます。
「触れてはいけない」と感じる空気。
その空気こそが、目に見えない“壁”なのだと思います。
このブログの記事を書くときも、無意識のうちに内容を選び取っている自分に気づきます。
それは長い社会経験の中で培われた「世間への忖度」でもあり、
人として身につけてきた“安全な距離の取り方”なのかもしれません。
人生の最終カーブに差しかかる今、
触れていいものと、触れてはいけないもの――
その線引きを学んできた自分がいます。
けれど、目に見えない世界を掘り下げようとすれば、
世間の常識や理解の外に踏み込むことになるのです。
たとえ「個の時代」と呼ばれる現代であっても、
共同体の枠からはみ出すもの、性質や価値観の異なるものを
受け入れにくい風土は、まだ根強く残っています。
目に見える世界だけに生きることの危うさ
イスラム教の教えでは、人のあらゆる行為がコーランに示されているとされています。
親切をしても、その感謝は人にではなく神に捧げる――
そんな生き方は、私たち日本人には少し不思議に映るかもしれません。
それは、「目に見えない世界」を中心に据えた信仰のあり方のひとつです。
一方で、「目に見える世界」だけで生きようとする社会もあります。
すべてを法律や制度で説明し、コントロールしようとする社会です。
しかしその行きつく先は、冷たい法治の世界です。
というのも、「この世の罪がこの世で完結する」と考えるなら、
最後に人を律するのは、個人の倫理観しかなくなるからです。
けれど、価値観が多様化したことで人間性すら見失ってきた現代では、
統一した倫理を共有し続けることは極めて困難です。
結果として、「社会的に罰せられないなら何をしてもよい」――
そんな考え方が広がっていきます。
そうした風潮の中で、人々は“今この瞬間を楽しむ”ことに傾き、
精神修養や節度といった言葉は、風に流されていく。
日本もまた、アメリカが通っていった道をたどり
「わたしは誰がどう言おうとも変わらないし変われない!」として、
いずれさらに徹底した個人主義の社会へと舵を切っていくのでしょう。
その先にあるのは、自由ではなく“統制された孤立”です。
共同体の中に生きるということ
たとえば、葬式のかたち。
現代では多種多様な葬送形態が広がりをみせてはいますが、
それでも、本人が「こうしてほしい」と願っていても、
多くの場合、本人が属していた共同体の価値観がそれを上書きします。
たとえ都会であっても、SNSや職場など
小さなコミュニティには“見えない同調圧力”が存在します。
人は社会的な生き物である以上、
それらを完全に無視して生きることはできません。
だからこそ、目に見える世界と、見えない世界――
この二つのバランスを取りながら生きることが
今、求められているのだと思います。
おわりに ― 目に見えない世界が映すもの ―
ここまで読んでくださった方の中には、
単なる興味から来られた方もいれば、
目に見えない世界に少しでも理解や敬意を寄せる方もいるでしょう。
「見えない世界」とは、決して怪しいものではありません。
そこには、人の生き方を照らす知恵や導きが潜んでいます。
にもかかわらず、わたしたちはそれを“宗教的”“非科学的”と
一括りにして遠ざけてしまいがちです。
もしそれが仏教の言う「一念三千」――
”一つの念の中に無限の世界があるという思想”に通じるのなら、
この現実もまた、わたしたちのこころが映し出す世界なのかもしれません。
けれども、見えない世界にこころまで閉ざすことは、
人生の豊かさを失うことにもつながります。
目に見えない世界を垣間見るとき、
私たちはようやく、もう一つの現実に気づくのです。