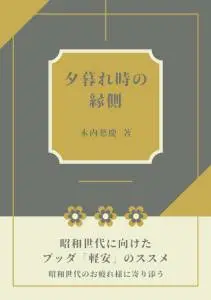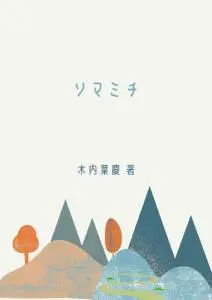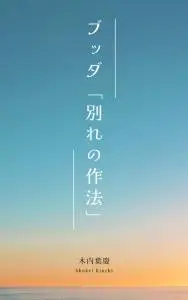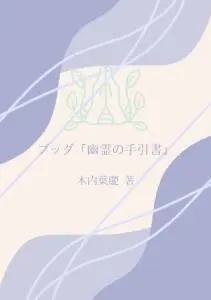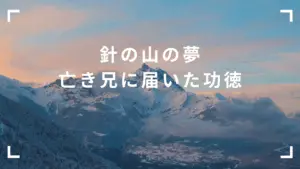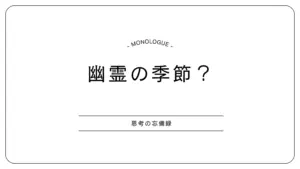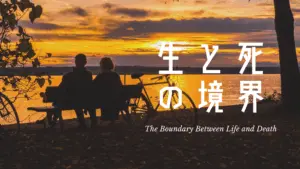はじめに
以前「この世と次の世との狭間で」という記事を投稿しました。この中で、いち大乗仏教僧侶の経験から、死後、次の世へ行くまでの簡単な行程の説明と、なかなか人が次の世界へと旅立てない様々な要因をお伝えしました。
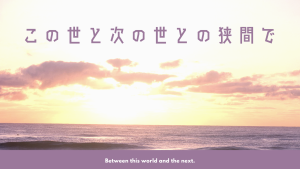
今回は、死後も自分の意識が続いているんじゃないかと何となく思っている方に、次の世について気になっているであろう大きな疑問についてお話ししたいと思います。
わたしが体験してきた目に見えない世界が、真実かどうかはわかりませんが参考になれば幸いです。
お迎え
死後意識が存続していると思っている方が、気になっているであろうひとつに、
親族、友人等、生前親しかった人がお迎えに来るのか?
があると思います。「もうすぐお迎えが来るから…」とは、その昔、お年寄りたちが集まれば、誰ともなく聞こえてくる常套句でしたね。
彼らが望むお迎えの対象は、「生前親しかった人々」が第一で、あわよくば「仏」ないしは「神」といったところではないでしょうか。
結論から言えば、残念ながら誰も迎えには来ることはないでしょう。まれに、とても短い間ですが、生前親しかった人と会うことが叶う場合があるようです。それが実現できるための条件等はわかりません。エビデンスがそもそもない上に、縁に関わる仕組みは複雑だからです。
それでは、
生前親しかった人や信仰していた神仏が、死後自分を案内してくれるのか?
というのはどうでしょう。これもこの世と次の世との間の「中陰」に限って言えば望み薄です。僧侶だった頃は、この「中陰」にある間、亡き人々と接触を試みるのですが、次の世へ何者かが道案内をしたという話しは聞いたこともないし、年忌中での経験もありませんでした。
考えてみれば、迎えに来たり、何かしら教えてくれるのでしたら、迷うこともないし、あの世と次の世の間にある「中陰」にて、数十年~数百年と留まるとは考えられません。
お迎えは来ないし、次の世の行き方さえ教えてくれそうもない。死んだらぽつねんとある自分の様子は、何とも心もとないですね。
大乗における次の世への道
大乗仏教では、次の世界へたどっていける道があるとのことでした。
「白道縁起の報土において」というお経の文言を聞いたことがある方がいらっしゃるかと思います。「白道」とは文字通り白い道であり、「報土」とは幽玄の世界を指しています。
数百年前から唱えられている経文によれば、白い道をたどるとあの世へ行けるとのことです。熱心な信仰者が見えることが出来るそうですが、詳細についてはわかりません。

万人が信仰者というわけではないので、ほとんどが死んだらどこへ行けばいいのか、そもそもどこか行かなければならないものなのかさえわからないと思います。当然「中陰」に留まる時間は長くなってしまいます。
誰しもこの世には心残りがあるし、悲しさ、口惜しさ、狼狽から不安まで、生前の人の感情は止めどもありません。中には、この世への執念から永遠とも思えるほど「中陰」に留まってしまうケースさえあるでしょう。
人は生き方も違えば死に方も様々です。白い道が見えようと何だろうと共通してある答えがあるわけではありません。答えがあるとすれば、自分のこころの中に潜んでいるとしか言えません。
人が、あの世から最終目的地として向かう先は大乗仏教においては仏界とされています。そこで、次に大乗の仏界についてほんの少し触れておきましょう。
大乗における仏界とは
大乗における仏界というのは、人が進むべき最終地点としています。仏界とは、はるかに遠いところです(距離ではなく、境涯として)。「人が進むべき」ですから人界とは道がつながっています。

人界、仏界の他、神の世界である神界があります。神界と仏界は別次元でありはっきり分かれていて、双方間につながりはありません。神界へは閉ざされていて、人界とは道筋が異なります。
その昔、戦国時代の武将の中には「死んで~の神となる」と言い残して絶命していました。どうやら、彼等の望み通りにはいかなかったようです。
人は、神界に踏み入ることができません。神は人と似た価値観を持ってはいるものの基本的な成り立ちが異なっているのです。
これまでの大乗の逸話の真偽はともかく、お釈迦さまの言葉と共通して言えることは、この世での日頃の行い言動というものが、次の世への橋渡しにも関わっていることに間違いないようです。
特殊な事例
ところで、まだ物心ついていない子供が亡くなったらどうなるの?
といった疑問があります。まだ年端も行かない子どもが亡くなってしまって、仮に死んだあとまで意識があったとしたら、その不安や迷いを想像するととてもかわいそうですね。
ところで、わたしが育った田舎では、夏のお盆の頃になると、
地蔵さんに参らんもんは、地獄へ真っ逆さま!(九州弁)
と町内の子供たちが大きな声で練り歩く、地蔵祭りが開かれていました。
物心もつかない幼い子供が亡くなると、不安で心細いその子のこころに寄り添って、お地蔵さまが道案内してくれるという土着信仰があったのです。

ーお地蔵さまにはひょっとして将来子供がお世話になるかもしれないー
地蔵祭りは、「お世話になるかもしれない子を持つ親や子供たち自身が、お地蔵さまを祀ってその労をねぎらい、みんなで敬意をはらいましょう」という趣旨から行われてきました。しかし、少子化・過疎化等で、今ではその祭りもなくなってしまっていることでしょう。

僧侶時代、わたしには幼子が亡くなった事例に遭遇しませんでした。そのため、お地蔵さんが実際迎えに来たことを確認することはありませんでした。
ただ、お地蔵さんの閉眼式の経験はありました。老健に入る予定のおばあちゃんが古家を引き払う際に、律儀にも庭に祀ってあったお地蔵さんの閉眼式をして頂いたのです。
閉眼式が終わった際、目に見えない世界の中で、4人の付き人の方々が、急いで用意してきたらしい板を乗り物代わりに肩に抱えて、身分の高そうなたれ目の老人を乗せて去っていく様子が見えました。お地蔵さんは、一般的にかわいらしい外見をしていらっしゃいますが、実際は老賢な神様のようでしたので驚いたことを覚えています。
また、余談ですが不慮の事故等で早世した人の生まれ変わりは早いと聞いています。
おわりに
わたしは、大乗仏教の僧侶だった頃、ひとの意識が死後も継続して存在していたため「魂」の存在を確信していました。
一方で、「魂」がそのまま生前の人の「我」ならば、なぜ亡き人の意識の情報は限定的にしか得られないのか疑問を抱いていました。これを「亡くなった直後は生への執著が特に強い場合が多くあるため」だとすれば辻褄が合います。
この残留思念によって、わたしは、人に「魂」という「人の本性」があると錯覚を抱いてしまっていたのです。
過去生を経験してからというもの、死後も続くという「魂の概念」とも言える考え方は、わたしの中からすっかりなくなってしまいました。そもそも「魂」という考え方にこだわっていると、我執(我見)1に陥ってしまいます。

その後、次第にわたしの中で固まってきた人の本性というのは、「縁が取り巻く無我」が個性をまとっている姿です。
執著等こころに強いわだかまりがあれば、縁は絡んだまま(転生先があれば)次の世まで持ち越されます。この世に何かしら不都合な事態を引き起こしたことがあったなら、次の世は厳しい世界の住人となるかもしれません。この天の采配としか言えない正負観に妥協の余地はありません。
「中陰」は、人が霊感で感知できる限界だと思っています。わたしが僧侶だった時、亡き人が「中陰」から先へ赴く次の世界については、まったくわかりませんでした。翻って考えれば、そもそも僧侶は我見に囚われてしまいそうな霊感に頼ってはならないことを示唆しています。
「中陰」という次元は、縁が次第に解かれ行く世界です。そこでは、現世で新たに結んだりまたは解いてきた縁が一旦清算されてどこか異次元へと送られて行きます。
「中陰」とは、大多数の人々が人だった頃の自分の縁の収束を惜しむひとときでもあるのです。
- 人には常住不変の実体があるとする誤った考え ~出典:デジタル大辞泉 ↩︎