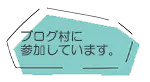はじめに
わたしは映画が好きで、近年こそほとんど観なくなりましたが、昔は映画館でも自宅でもよく映画を楽しんでいました。
映画には「死」と「生」を題材とした作品が数多くあります。先日、上記の記事を書いていたとき、ふと思い出したのが アン・ハサウェイ主演、2008年公開の『パッセンジャーズ(Passengers)』 でした。
ちなみに単数形の「パッセンジャー」だと、サバイバル系のSF映画になってしまいますのでご注意ください。
『パッセンジャーズ』とは「搭乗者たち」という意味のとおり、飛行機事故に遭った乗客たちの物語です。透明感があり、静けさと哀しみの中に美しさのある作品でした。
以後、多少のネタバレを含みますので、まだご覧になっていない方はここで一旦お止めください。
映画を観て思ったこと
この映画の趣旨は、ブルース・ウィリス主演の『シックス・センス』(1999年)にも通じるところがあります。
登場人物たちはすでに亡くなっているのですが、彼らを取り巻く親族や恩師、同僚などが、それぞれ役割を演じながら、穏やかに「死の自覚」へと導いていく──そんな構成です。
「自分が死んだことに気づかない」という設定は、浄土思想の根強い日本ではあまり受け入れられないかもしれません。
しかし、おそらく霊能者が監修しているのではないかと思うほど、わたしが霊感で見る“あの世”の世界に近いものでした。
日本の幽霊映画に多い誇張や恐怖演出に比べて、アメリカのこうした作品は、むしろ現実的な描写に重きが置かれているように感じます。
映画を思い返しながら、もう一つ心に浮かんだ出来事がありました。
わたしが出家して間もないころ、初めて「亡くなった人」と真正面から向き合った日のことです。
最初の対面
それは、叔父の通夜でのことでした。
出家してまだ日も浅く、何もかも手探りの時期でした。
葬儀社が手配したお坊さんの前で、一度自分も読経してみようと思い立ったのです。
そこで、わたしは初めて「亡くなった人」と正面から向き合うことになりました。
霊感で見た光景を、少し書いてみます。
叔父は、まだ体から抜け出ていませんでした。
わたしは静かに声をかけました。
叔父さん、あなたは死んだんですよ。
すると、叔父は驚いたように答えました。
なんてや、おれが死んだてや。(九州弁)
その後、叔父は言葉を失い、沈黙の中でただ戸惑っているようでした。
長い間、寝たきりだった叔父にとっては、「死んだ」と「眠っている」の境界がわからなかったのかもしれません。
これは時間がかかるな、と直感しました。
しかしまもなく、葬儀社のお坊さんがいらっしゃったので、わたしはその場を譲りました。
檀家寺のお坊さん
葬儀社の僧侶は、わたしの実家の檀家寺の長男さんでした。
若くして亡くなった住職(彼の父)の跡を継ぎ、若いながらも懸命に務めておられる方でした。
読経を終えると、彼は力強く手を掲げてこう言いました。
叔父は西方浄土へと飛び立たれました!
その言葉を聞いたとき、わたしの胸にふと温かいものが込み上げました。
「ああ、若くして住職を継ぎ、苦労されているのだな」と、しみじみ思ったのです。
まとめ
『パッセンジャーズ』をレンタル店で借りて観たのは、わたしがまだ働きづめの頃でした。
主人公が、自らの死を少しずつ受け入れていく過程に、なぜか涙が止まりませんでした。
それはきっと、死を「終わり」とせず、こころの成長の延長として描く視点に、わたし自身の感覚が共鳴したのだと思います。
出家して、人の世もあの世も見つめ直すようになった今、
あの若き住職が掲げた手の中の言葉——
「叔父は西方浄土へと飛び立たれました」
という一言が、妙にあの映画と重なって見えてくるのです。