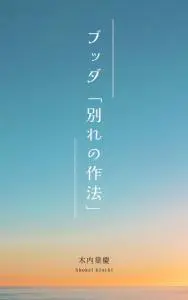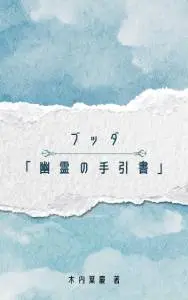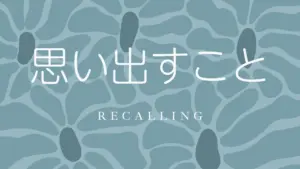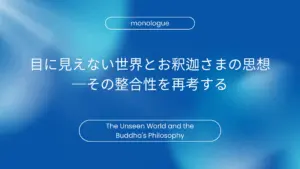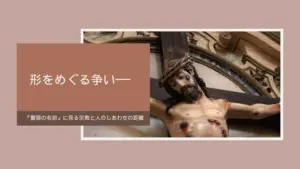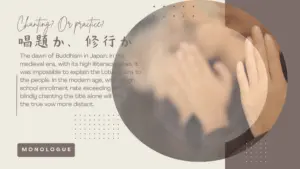はじめに
家族が疎ましい
夫(妻)と気が合わない
母(父)が嫌い
ひとりの方が気が楽
個の時代と呼ばれる今、家族の「気持ちの距離」は、年々開いていくように感じられます。
その影響か、「家族を持ちたくない」「自分の好きなものや、気の置けない人だけに囲まれて生きたい」と願う若者も少なくありません。
背景には、育った家庭環境が大きく関係している場合もあるでしょう。
自由に見える現代社会ですが、その実、息苦しさのような閉塞感が、じわじわと家庭の中にも影を落としているのかもしれません。
家庭というものは、往々にして親から子へと無意識のうちに引き継がれていくものです。
もし幼少期に、暴言や暴力が日常にあったとすれば、その「こころに刻まれたキズ」は形を変えながら次の世代へと連鎖していく——
そんな現実も、わたしたちは見逃すことができません。
今回は、「個が湧きたつ時代」において、変貌していく家族の姿について考えてみたいと思います。
社会の中の自分
冒頭でも触れたように、現代は価値観や嗜好が多様化し、
自分の趣味を軸に、居心地の良い生活スタイルを築こうとする人が増えてきました。
まるで、自分だけの小さな砦を守るように。
もちろん、ひとりで生きることを否定するつもりはありません。
けれど、人は死ぬその時まで、完全にひとりで生きることはできません。
このブログでもたびたび触れてきたように、**「縁」や「因果」**は、人が生きている限り決して断ち切られることはないのです。
人は、他者とのつながりの中で生きています。
それは、目に見える助けであったり、あるいは気づかないところで支えられていたり。
どんなに孤独を好んでも、わたしたちは常に誰かの手を借りながら生かされているのです。
もし、「自分はひとりで生きている」と感じている人がいるなら、
その「ひとり」を陰で支えている見えない多くの存在に思いを向けてみてください。
そこに気づけたとき、人生は感謝へと姿を変えます。
人が一人で生きられない理由——それは、
人が生まれ持った「縁」と「因果」を、少しずつ解きほぐしていくために生きている存在だからです。
誰かを傷つけたり、陥れたりすれば、その縁はたちまち複雑に絡まり、
ほどくことが難しくなっていきます。
そして、やがて解けなくなった縁を抱えたままの者は、
その因縁に引かれるようにして、
二度と戻れない「暗き地」へと沈んでいく——
目に見えない世界の視点から見れば、それは決して比喩ではなく、心の実相としての警鐘なのです。
家族とは
そもそも、「家族」とは何でしょうか。
近年、「親ガチャ」という、どこか乾いた響きを持つ言葉を耳にすることが多くなりました。
どんな親のもとに生まれたかで人生の大半が決まってしまう——
そんな、諦めと皮肉が入り混じった感覚を表した現代語です。
けれど、人の誕生というものは、そんな単純な確率の結果などではありません。
わたしたちの生誕の背景には、壮大な「縁(えにし)」の計画が流れています。
子は、親を“選んで”生まれてくる——。
それは偶然ではなく、因果の流れの中で自然に導かれた必然なのです。
家族という最小の共同体を成り立たせているのも、やはり「縁」と「因果」です。
それらは、前世から受け継がれたさまざまな素性(すじょう)をもとに、
互いを磁石のように引き寄せ合い、ひとつの「関係性」として結びついていきます。
ですから、どの家族に生まれ、どの土地に育つかということも、
決して偶然の出来事ではありません。
「縁」や「因果」は、人知で計ることのできない、壮大な生命のシステムの上に存在しています。
まるで遺伝子のように見えながらも、科学では説明しきれない“見えない設計図”のようなものなのです。
この世に偶然は存在しません。
親ガチャという言葉で片づけてしまえば簡単ですが、
そこには見えざる計画と必然の導きが確かに働いています。
そして、人がその計画から外れるような生き方を選べば、
必ず何らかの「反動作用」が起こります。
それは、運命の報復ではなく、
本来の道筋へと戻そうとする生命の調律なのかもしれません。
身近な例として、住職が出席された結婚式でのある出来事を紹介しましょう。
住職が何気なく新婦の角隠しの飾りを見た時、突然飾りの鶴に羽が生えてきて、今にも羽ばたいて飛び立とうとしていました。住職は、その時この結婚の破綻を確信したそうです。
後から聞いてみたところ、どうやら周りの反対を押し切っての結婚のようでした。たとえ周りの反対があっても良縁もありますが、この二人の場合はどうやら違っていたようです。
その場では、絶対口に出せないことですねw
家族関係
家族関係を支えているのは、他でもない**一人ひとりの「こころ」**です。
その前提として、家族には同じ血が流れています。
だからこそ、感情的になりやすく、ぶつかることも多いものです。
けれど、そこで働いているのは「こころ」ではなく「感情」です。
感情とは、こころが揺れたときに生まれる波のようなもの。
その波が大きくなりすぎると、やがて負の連鎖となって、家族全体を包み込んでしまうことがあります。
だからこそ、どこかでその連鎖を止める人が必要なのです。
一方、頑固で話の通じない父ちゃん、ヒステリックな母ちゃんで手も足も出せないとしたら、タイミングをみて離れるのもいいかもしれません。例え家族だからといって、何も自分のこころに罪を作ってまで、一緒にいる理由はないのです。
離れるという選択
もしも、頑固で話の通じない父親や、ヒステリックな母親に手も足も出せないような状況なら、
無理に関わり続ける必要はありません。
タイミングを見て、いったん離れるという選択も大切です。
家族だからといって、
自分のこころに罪を作ってまで一緒にいる理由はないのです。
家族の関係は、義務ではなく「縁」によって成り立っています。
縁は、近づいたり離れたりしながら、それぞれが成長するために形を変えていくものです。
離れることもまた、ひとつの修行なのです。
自分を知ることから始める
全ての出発点は、自分のこころを見定めることです。
感情の余裕のない家庭に育った経験があるなら、
同じ轍を踏まないように、自分の生き方を見直すことが大切です。
それは、「過去を断ち切る」ということではなく、
「過去を理解した上で、よりよく生きる」という方向転換です。
父や母の在り方、学校や社会の在り方に、いつまでもこだわってはいけません。
それらはあなたを形づくってきた「素材」ではあっても、あなたそのものではありません。
こころの視点を、自分を起点とした世界へとシフトチェンジしていきましょう。
思いの向きを少し変えるだけで、人生の方向も自然と変わっていきます。
まとめ
家族は、一番近い人間関係です。人間関係は近くなればなるほど、それを維持していくためには工夫が必要となります。人生を壊すのも、謳歌するのも人と人との関係が重要な要素です。
最初に出会った家族が不安定であったことは不幸ですが、といって若いうちから、自分の人生を諦めてしまうのも少しもったいないような気がいたします。
今だけ、カネだけ、自分だけ
現代の世相は、何でもかんでも短いスパンで考えてしまいがちです。流行のスピードがそれを象徴しています。狭い視野で考えてしまうと、家庭を含めた人間関係を壊していくだけでなく不幸の連鎖を続けてしまいます。
自分を振り返りながら、長い視野を持って、新たな人間関係に踏み出してみましょう。
もし、人生最初の社会でもある家族の在り方が不安定であれば、次のステップへのチャンスだと思い換えることができたら素晴らしいですね。