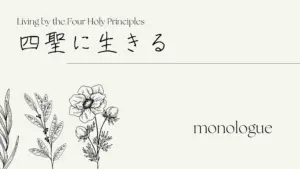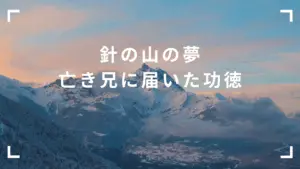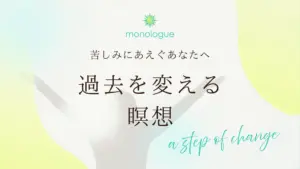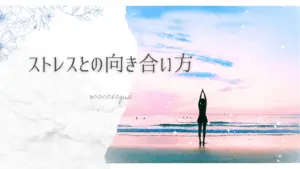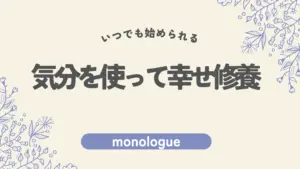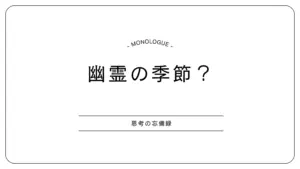はじめに
私たちは、人や物、関係、仕事、趣味など、さまざまなものに執著を持ちがちです。
子や孫をかわいいと思う気持ちが深まれば、いつまでもそばに置いておきたくなる。
お気に入りの物に対しても、嗜好の域を超えて手放せなくなることがあるでしょう。
一般的に「執著は良くない」と言われます。多くの方もそう思っているはずです。
しかし、嗜好と執著の境界は非常に曖昧で、気づかぬうちにその線を越えてしまうものです。
執著を見極めるのは難しく、いつの間にか前後左右が見えなくなる―
その状態をお釈迦さまは「無明(むみょう)」と呼びました。
とはいえ、嗜好さえ持たずにストイックに生きるのも味気ないもの。
誰も仙人のように霞を食べて生きることはできません。
人やモノへの傾倒が、やがて“生きがい”に昇華できるなら、それは人生を豊かにする力にもなります。
今回は、この「やっかいで愛おしい心の働き」――執著について考えてみたいと思います。
執著とは何か
年齢を重ねるほど、この世への名残りは深くなります。
自分という存在の愛おしさ、家族への想い、積み重ねてきた喜び。
人生を豊かに生きてきた人ほど、離れがたいものが多いでしょう。
もしそれらすべてを「執著」と言ってしまえば極端です。
誰にでも思い残しはあります。それ自体は自然な感情です。
ただし、それがこころを縛るほど強くなるとき、執著へと変わります。
念の及ぶ世界 ― 執著は次の世界へ続く
執著は、死を迎えた後の世界でも影響を及ぼします。
この世を離れて次へ進むためには、執著は大きな足かせとなるのです。
多くの人は「執著など、いざとなれば手放せる」と思いがちです。
けれども、実際には生きている間にそれを顧みず、思いの癖を積み重ねていくことで、
その“癖”が未来を形づくってしまいます。
わたしの経験上、亡くなった後の人の思いには、しばしば強い執著の念が残っています。
それが「霊」と呼ばれる、人の残像のような不安定な形でとどまることもあります。
目に見えない世界では、執著は因果を絡めとる糸のようなものです。
複雑に絡んだ縁は容易にほどけず、こころの傷として次の世界に引き継がれていきます。
つまり――
執著とは、自分のこころに傷を刻む行為なのです。
老いと執著 ― 自然な名残りと執著の違い
年を重ねるにつれ、人は自然と未練を少しずつ取り除きながら、
次の世界への準備を整えていきます。
名残りや心残りは誰にでもあります。
それは執著とは異なります。
だからこそ、目に見えない世界に触れた人々が声をそろえて言うのです。
「自分のために、執著は手放しましょう。」
執著という傷を癒すには、とても長い時間――「劫(こう)」の単位を要します。
しかも、執著は思いもよらないところに作用します。
そのひとつが、病気や事故による死です。
病身の苦悩と“痛みへの執著”
私も50代までは体が動きましたが、60を過ぎると衰えが急に進みました。
老いも病も避けられません。

現代では「ピンピンコロリ」が理想とされます。
死ぬ直前まで元気で、病に苦しまずに天寿を全うする――
人の願いはそこに集約されています。
しかし、現実はそう簡単ではありません。
多くの人が病に苦しみ、介護を受け、思うように動けずに過ごします。
そのとき人は、苦しみそのものに執著してしまうことがあります。
「なぜ自分だけが」と思う心の奥に、苦しみを手放せない“癖”が生まれるのです。
わたしの僧侶としての経験では、亡くなった後もなお、
生前の苦痛を感じ続けている意識を何度も見てきました。
死によって苦しみが消えると思うのは誤解です。
死んでもしばらくは意識が残り、「物思いにふけっているつもり」でいる場合も少なくありません。
死は、生前の苦悩を晴らすものではない。
これは、死後の世界を信じない人には受け入れがたい話かもしれません。
けれども、私が伝えたいのは、苦しみは死によっても終わらないということです。
執著を癒すために
執著とは、こころの癖です。
病や苦痛に囚われるのも、こころの中に「執著の道筋」ができてしまっているためです。
自分をかわいそうだと嘆く前に、まず自分のこころを見つめ直してみてください。
それが、ほんとうの慈悲への第一歩です。
慈悲と言うのは、他人ばかりではなく、自分自身にも通じています。
この言葉は冷たく聞こえるかもしれません。
しかし、生きる苦しみも、死後の苦しみも、
最終的には自分のこころだけが癒せるのです。
日常の中で、自分の執著の度合いに気づき、
少しずつ手放していく――
それが生も死も穏やかにする道です。

まとめ― 自分を知る努力を
中世では“楽土”を死後にしか見いだせませんでした。
けれども今の時代、わたしたちの周囲にはたくさんの喜びや生きがいの種があります。
嗜好や娯楽を上手に楽しみながらも、執著にまで至らせないこと。
それが、穏やかに生きる智慧です。
古代ギリシャの哲学者はこう言いました。
「汝自身を知れ。」
完全に自分を知るのは難しいでしょう。
けれども、知ろうとする努力――
それこそが、執著から自由になる第一歩なのです。