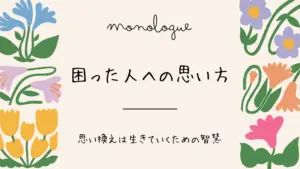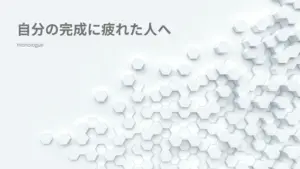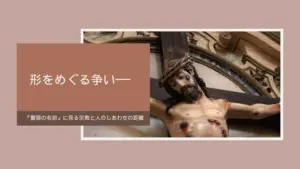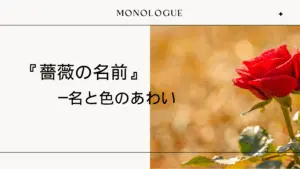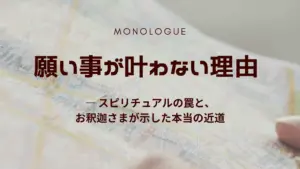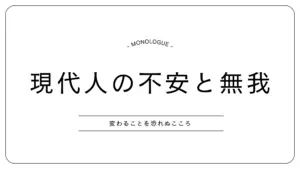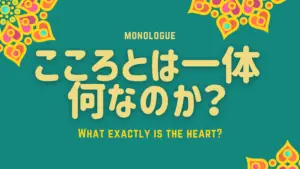若きし頃の迷走
わたしは、九州地方の片田舎で生を受けました。
若いころ、ひとつの思い込みがありました。
それは、この世界では「経済的な成功者が、学校では学べない何らかの“錬金術”を知っている」ということです。
日本は資本主義社会です。
資本主義社会で経済的成功を収める人は、人間性にも優れ、その人間性が成功の秘訣を生み出している――そう信じていました。
しかし、それは大きな誤解でした。
社会の中で見た「成功」の正体
30代の頃、電機メーカーの研究職から転職し、大学で教鞭をとりながら、行政機関の外郭団体に所属しました。
そこでは、起業家や経営者と関わる機会が多くありました。

彼らの中には、確かに知的で行動力に満ちた人物もいました。
けれど、わたしが実際に感じ取った印象の多くは――
「この人間は、どれほど自分に利益をもたらすのか」
という、相手を値踏みするような視線でした。
慢心に満ちた数々の言葉の端々から、
とても人間的に優れているとは言えない印象でした。
巧みな話術と情報操作、ギブアンドテイク。
資本主義社会の“錬金術”とは、こうした処世術のことだったのです。
人間性の成長こそが社会的成功の根底にあると信じていたわたしにとって、これは痛烈な現実でした。
その瞬間、わたしの中で「経済的成功=人間的成長」という幻想は音を立てて崩れ落ちました。
決して大げさではなく、この社会に対して、人の存在する理由さえ見失うほどの衝撃を受けてしまったのです。
真実の価値への模索
このようなわたしの価値観など、経営的な責任や労働者の雇用といった重荷を背負っている経営者たちにしてみれば、きっと理屈に満ちた青二才の戯言と映ることでしょう。
今振り返れば、社会的成功と人間の価値が関係ないことなど、誰でも知っている理屈です。
それでも若いわたしは、その現実をどうしても受け入れられなかったのです。
ただ、社会的・経済的な成功者は、人を評価する際に一番わかりやすく説得力のある目安です。当時のマスメディアでも、彼らはコメンテーター等として迎えられ、あたかもすべてを知っている者のように取り上げられていたのも、まだ青年期にあった自分が誤解した要因だったのでしょう。
なぜ、そこまで「人間性」にこだわるのか。
それは、わたし自身が「人としてどう生きるべきか」という問いに、納得のいく答えを求め続けていたからでした。
自分の性分と言ってしまえばそれまでですが、自分も人として生きて行くならば、そこを曖昧にしておきたくなかった。人間性の正体について自分を納得させるような結論がほしかったのだと思います。
資本主義社会の宿命
資本主義社会では、経済の発展が求められます。お釈迦さまも経済の発展は否定されていません。経済の発展は人の生活を豊かにして、結果として経済的な余裕が、こころの成長へ波及される可能性があるためです。
ただ、マイナスの一面もあります。
貧困や格差社会など、競争社会において利益追求などが重要視される資本主義的な価値観にはどうしても限界があります。また、人間的な価値は経済的な成功ばかりではなく、多面的である人間の価値の一面に過ぎません。
人の価値を計るためのものさしには、様々な種類があります。社会的・経済的な成功を価値とみるものさしを正しいと見る人たちは、この世にはたくさんいます。しかし、わたしの場合、それでは物足りなかったというわけです。
結局、わたしの約半生は、人の価値を計るわたしのものさしが間違っていたことを気付くための授業でした。
では、優れた人間性とは、そして人が成長する意味とは一体何なんでしょう。そこに見いだされる人の価値の正体についてもう少し考えてみたいと思います。
こころへの回帰
壮年期に入ってからも、自分の納得できる新たなものさしを探していました。
探しはじめたといっても、目的を定めて行動したわけではありません。その頃は、自分のこころの問題を先送りしてしまっていました。そのため、崩壊した価値観を抱えたまま、あたかも揺れ動く地面を漠然と彷徨うようで気持ちの悪いものでした。
結局、その心持ちのまま数年の時を経て出家することになります。
出家した寺院の住職や諸天善神に助けられながら、修行していく寺院での経験はとても貴重なものでした。社会生活におけるものの見方が、人本位の始点から、目に見えない世界からの視点へと180度変わっていきました。
そうすると、目に見えるものはその様相を変え、これまで隠れて見えていなかった人の本質を含めて、目に見えない新たな世界が見えてくるようになりました。
すると、新しい価値観が芽生えはじめていました。また、知らずに資本主義社会に完全に毒されていた自分を自覚することにもなりました。
そこで得られた結論は「人はこころのあり様」ー
分かっていたはずでもあるこの言葉が、何だかとてもこころに響いてきたのです。
不安定な気分の自分からようやく解き放たれて、しばらくこのものさし持って一息つくことができました。
こころの難しさ
目に見えないものが見えてくると、人の本性も見える様になります。人の本性が見えてくると新たな疑問が湧き上がってきました。
人というのは、特に日本人は、本音と建て前を区別して生きています。人は大体自分の本性を隠して表面を取り繕い良いことを言いがちです。

そのことについては、わたしも長い企業文化の中で分かってはいました。それが、修行を重ねていく内、本音よりもさらに深いところで、本音でさえも取り繕っている人間が、如何にこの世に多いことがわかってきたのです。
なぜかこころを濁している人ほどその傾向は強く、そんな人ほど社会では成功を収めている場合が多々あります。社会的な成功とこころのあり様は別問題という事実を改めて突きつけられたのです。
一方で、今度は僧侶として人と接するようになると、ある程度のこの世の成功を治め現状に満足している人間ほど、こころの修行からは遠いところにいることが分かってきます。
多くの成功者と評される人たちは、財や地位を失うことの不安からか、もっともっとと際限なく掘り続けていく掘削機械のように現状にしがみ付こうと欲望を追い求めていきます。
そうして、他人のこころについてはもちろんのこと、自分のこころのあり様など気づくことなく一生を終わらせていきます。
貧しく苦労の多い人生を歩んでいる人でも人間的に優れた人もいれば、社会的に高い地位にいて豊かな暮らしをしていても、人の痛みなど知ったことではないという人もいるのです。
優れた人間性と現実の生活との差
そんなこの世に対して、いみじくも、マーティン・ルーサー・キング牧師の言葉の一節が思い浮かびました。
後世に残るこの世界最大の悲劇は、悪しき人の暴言や暴力ではなく、善意の人の沈黙と無関心だ。
マーティン・ルーサー・キング牧師の演説より
キング牧師の言葉は、人の差別意識を主題に置いています。これは、人間性も含めて広義に解釈すると善意の人にも決して人間性に優れている訳ではなく、逆に悪意にさえ満ちている人もいるということです。この矛盾と憤りは、しばらく私を苦しめました。
ものさしの拡大と延長
住職には、人の思いを話すことなく伝わります。このような矛盾に悩んでいたわたしに、法話の中でこのように諭されました。
歴劫成仏(りゃっこうじょうぶつ)といって、人は数多くの人生を経験して学んでいくのですよ。
この言葉は、わたしのものさしを大きく長くさせました。
それは、人は死後も、その生きてきた証は残り続け、こころを繋ぎながら連綿と続く時系列の中にあり、この世のことなどほんの一瞬に過ぎないということです。現代、現在の成功者など、表面的な事象に過ぎないということです。
転生によって積み重ねてきたこころが今に現れている
まとめ
狭い視点で社会を見てしまっていた過去をはじめ、まったく恥ずかしいわたしの一面を紹介しましたが、突き詰めるとやはり人の価値はこころにありました。
知ることと腑に落ちることは違う
わたしは、出家後、人の本性が分かるようになったことで、人の価値を分かったと勘違いしていただけだったのです。前世から続くこころの修行の現れは、この世のその人の立ち居振る舞いや言葉、その人のかもし出す雰囲気に現れます。

いくら表面を着飾り弁を弄しても、こころの中は必ず表に現れるものです。人生に錬金術があるとすれば、こころの中に既にあります。
目に見えない世界の裁量は厳格です。成功者が成功に甘んじて人の道を踏み誤れば、それは来世からの代償に繋がってしまいます。社会的な成功者と言っても、今世における一時的な現象に過ぎないのです。
まず、人を見る目を養い、翻って自分を高めるためには、自分のこころを整えることが大切だと悟りました。培われ整えられたこころこそ人の価値の根幹なのだと、目に見えない世界を通して学んだのです。