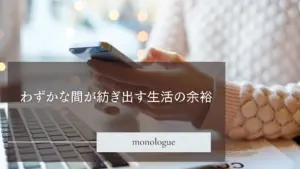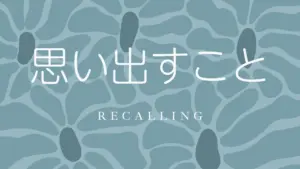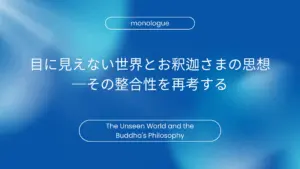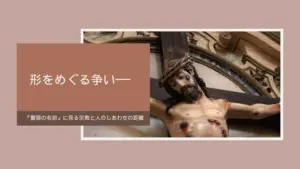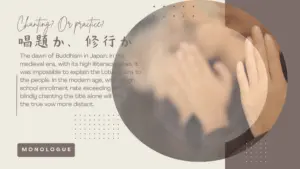はじめに
人はなぜ宗教を求めるのか——。
その意味を問い直す歴史は、何度も繰り返されてきました。
世界には様々な宗教があります。
時に弾圧され、時に弾圧し、時には争いの火種となる。
祈りのはずの宗教が、いつしか対立の象徴になってしまうこともありました。
近年では、過剰な勧誘や信仰を利用した寄付金の強要など、
宗教の名のもとに人の生活や家庭を壊してしまう事例も見られます。
平和を願うはずの宗教が、人の幸せを奪ってしまう—
これほど本末転倒なことはありません。
これまで、わたしは組織としての宗教には距離を置いてきました。
それでも、神が祀られた“場”には、言葉を超えた清浄な力がある──そのことを否定することはできません。
「宗教」という枠を超えて、“場”の意味と役割について考察してみたいと思います。
宗教における課題
多くの宗教は「教団」という形を取ります。
そこには儀典部や布教部などの独自部門がありますが、
経理や広報などの仕組みは、一般の企業とほとんど変わりません。

教団を維持するには経費がかかります。
光熱費、人件費、儀式に伴う諸費用、
そして特殊な建築構造の施設を維持するための費用——
それらは、普通の企業以上に重くのしかかります。
営利活動ができない宗教団体の多くは、
その維持を寄付に頼っています。
その過程で政治や思想団体と結びつき、理念よりも構造が大きくなり、
やがて本来の目的を見失ってしまうことも少なくありません。
もしかすると、宗教と組織という形態そのものが、
本質的に相容れないのかもしれません。
宗教において大切なこと
お釈迦さまの時代にも、バラモン教やジャイナ教、ゾロアスター教など、
多くの宗教が存在していました。
若きお釈迦さまもまた、生きる苦しみへの答えを求めて、
各地の思想家・宗教家を訪ね歩かれたのです。
教団には、さまざまな境涯の人々が集まります。
修行を志す者もいれば、悩みを抱えて寄り添う者もいる。
そこには当然、思考の差、感情のぶつかり合い、
つまり「不協和音」が生じます。
人が集まる限り、そこには必ず化学反応が起こります。
そして、神のような“高次の存在”との縦の意識を失えば、
その場は外の社会と何ら変わらなくなってしまいます。
時代が進むにつれて、縦の関係よりも横の関係が重視されるようになりました。
しかし、横の関係ばかりを頼ると、
いつしか人は「調和」を見失い、内面の軸を失っていきます。
脅しや恐怖で寄付を迫るような宗教は、
もはや「人を救う場」ではなく、
ブラック企業と何ら変わらない存在になってしまいます。
“場”というもの
人との不協和音をも受け入れられるだけの器があれば、
もはや宗教は必要ないのかもしれません。
ですが現実には、人と関わること自体が苦しいという人も多い時代です。
そんなとき、宗教を嫌う前に、
「場」というものを意識してみてください。

わたしも宗教には否定的ですが、
ある一面、そのような”場”に助けられたこともありました。
“場”とは、一見あいまいですが、
言い換えるならば、神が創り出す清浄な空気と空間です。
そこに身を置くと、自然とこころが静まり、感謝が芽生える。
その感謝の中に、人生の真理が潜んでいることに、
気づく人は多くありません。
まとめ
わたしが属していた寺院にも、多くの弟子たちがいました。
彼らはそれぞれ、育った環境も、修行の度合いも異なります。
当然、合う人もいれば合わない人もいます。
極端に言えば、会社組織と大差ありません。
ただし、決定的に違うのは——
そこには**仏塔下の「縦の関係」と、清浄な“場”**が存在していたことです。
高次の領域に、偽りはなく、真実しかありません。
その意識と感応し合う瞬間、
人はこの上ない静かな喜びを感じるのです。
日本にも、世界にも、清浄な場は数多く存在します。
そこで一度、自分を見直し、これまでの生を問うてみてください。
そして、新たな自分の起点を見出してみましょう。
ただし、その“場”は、願い事を並べ立てる場所ではありません。
そこは、欲を手放し、静かに感謝を捧げるための空間なのです。