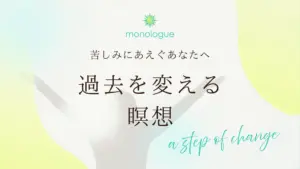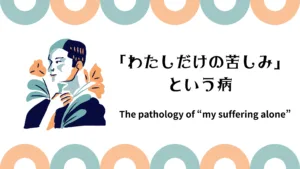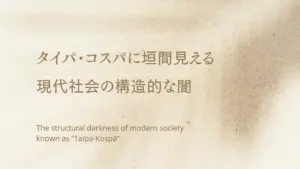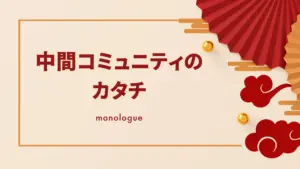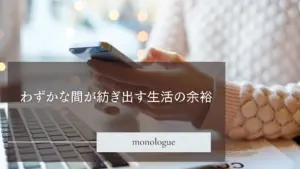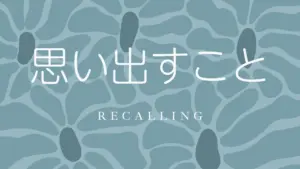はじめに
わたしたちが、同じ世界に生きているようでいて、
実はそれぞれ違う世界に生きていることを、以前の記事で触れました。
上記の記事の別の視点から見れば、わたしたちは異なる世界を生きながらも、共通する価値観を探し合いながら生きていると言えるでしょう。
わたしのブログでもたびたび登場する「神」や「霊」といった、
目には見えない世界も、これから何百年経っても、
科学の前に「眉唾もの」と言われ続けるでしょう。
それでも、人が神や霊に手を合わせるのは、
私たちが偶然ではなく、何らかの意味をもってこの世に生まれたと感じているからです。
そして、「見えない何か」を通して、
人は生きる上での共通の価値や拠りどころを見出そうとしているのだと思います。

さて、日本仏教が葬式仏教と揶揄されて数十年が経ちました。後がないと思い始めた一部の伝統宗教の中には、自身の立ち位置と原点とを見直す動きも出てきているようです。
今回は、現代日本の仏教について抱いてきた、わたし自身の最終的な論考を記してみたいと思います。
長い年月を経て、仏教という教えがどのように変質し、そして今どの地点に立っているのか。
それを見つめ直すことは、同時に「人がどう生きるべきか」という問いを見つめ直すことにもなるからです。
箱モノが信条を変えていく
「バエる」が流行るような外見至上主義の時代。
僧侶を豪華な衣装でまとい、立派で荘厳なものにしなければ人は集まりません。
宗派の分派によって貧しさの概念に解釈の違いはありますが、
雨露をしのぐだけの庵では、誰も寄り付かない時代なのです。
仏教の衰退については、過去に記事にしています。ここでは、これからの出家者の気持ちの持ち方を願い込めて書き留めています。
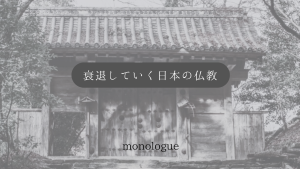
現代の仏教を見ていると、かつての精神性や清貧の理想とは違う方向に進んでいるように思えることがあります。
寺院の維持や檀家制度の維持が目的化し、僧侶自身も修行より経営に追われる。
立派な伽藍や荘厳な儀式がなければ人を惹きつけられない時代となっています。

かつて「こころを磨く道」であった仏教が、いつの間にか「形を保つ仕組み」へと変わってしまったように感じるのです。
この変化は、単なる時代の流れではなく、仏教そのものの本質を問う出来事であり、仏教はそれを時代から突きつけられています。
仏教の始まり ― 苦を見つめる知恵
仏教の原点は、言うまでもなくお釈迦さまの「苦の自覚」と「苦からの解放」です。
お釈迦さまは人間の存在そのものに苦が伴うことを見抜き、それを乗り越えるための道を示しました。
そこには、神への服従も、制度への依存もありません。
ただ、「今ここに生きる自己の在り方」を問い直す実践がありました。
しかし、お釈迦さまの没後、思想は教えとなり体系化され、数多くの宗派が生まれ、儀式が整えられていきました。
それは思想を広め、弟子たちが迷わぬようにするための知恵でもありました。
けれど同時に、“悟り”という個人的な体験が、“制度としての信仰”へと変質していく始まりでした。
何度も申し上げますが、お釈迦さまは「わたしを祈れ」とは決して言われませんでした。
それにもかかわらず、いつの間にか「祈る対象」として祀り上げられてしまった。
ここにこそ、仏教が本来の道から外れはじめた原点があるのです。
日本仏教の現状 ― 継承の困難と衰退の兆し
現代の日本では、仏教の存在感は確実に薄れつつあります。
寺院の数は全国で約7万、しかしその多くが檀家の減少と後継者不足に直面しています。
若者の信仰離れは顕著で、「葬式仏教」という皮肉めいた言葉が象徴するように、仏教が“生きるための教え”から“死を処理する儀式”へと押し込められているのが現実です。

かつて地域の中心であった寺院は、今では訪れる人も少なく、観光や文化財としての機能ばかりが注目されるようになりました。
僧侶の中には、布教よりも事業としての維持に意識を向けざるを得ない人も多くいます。
これは僧侶個人の責任ではなく、ましてや寺院の在り方の問題でもありません。
社会全体が「信仰よりも利益」「利益よりも効率」を求める構造の中で生じた歪みでもあります。
仏教批判でも信仰否定でもない
わたしは、仏教を批判したいわけではありません。
むしろ、仏教という存在を通して、人のこころの働きをもう一度問い直したいのです。
仏教の衰退は、僧侶や寺院だけの問題ではありません。
“仏教を求めなくなった社会”の姿が、そこに映っているのです。
つまり、仏教の形骸化とは、現代人の内面の形骸化でもある。
仏教は他者の救済ではなく、自己の目覚めから始まります。
わたしは、大乗仏教の僧侶として歩んできた中で、他者の救済を掲げることの難しさを思い知らされました。
救済という言葉は美しい。しかし現実には、そこに「無理」を押し込めてしまう構造があります。
人は縁起で出来上がっています。
縁起は人それぞれに悠久であり、複雑であり、誰かが他者を救うなどという考え自体が、
実はきわめて傲慢な幻想であったと気付かされました。
神力に頼ってみても、人の縁起を前にしては後手に回ってしまいます。
人ができるのは、他者の縁起の流れにそっと触れることだけなのです。
一方で、現代人の多くは、「自らを見つめる」という内的な作業を忘れ、激しく外に答えを求めるようになりました。
仏教の衰退は、単に信徒が減ったという数字の問題ではなく、「こころを耕す文化」が社会全体から失われていることの象徴なのです。
それでも仏教を求める理由
それでもなお、人が仏教を必要とするのはなぜでしょうか。
それは、仏教が「苦とともに生きる術」を教えてくれるからです。
世界がどれほど変わっても、人のこころの中には苦悩があり、迷いがあります。
仏教はその苦を否定せず、受け止め、超えていくための道を示すガイドラインを目指していました。
たとえ寺院が減っても、儀式が簡略化しても、仏教の本質は“人のこころの中”にしか存在しないはずです。
形式や制度が失われた先にこそ、お釈迦さまが開いた本来の仏教が再び息づく可能性があります。
おわりに
仏教とは、人の苦しみを見つめ、こころの奥に光を見出すための道でした。
しかしいつしか、その光を覆い隠すほどに制度が厚くなり、仏教そのものが形式に埋もれていきました。
仏教は、かたちを整えることで発展し、
かたちに執着することで衰退していったのです。
けれど、仏教の衰退を悲観してばかりもいられません。
それは、外側の仏教が崩れ、内側の本来の仏教が再び目を覚ます過程なのかもしれないからです。
形ある寺が朽ちても、お釈迦さまの思想は残る。
経が読まれなくても、こころに響く真理は消えない。
そうした仏教の静かな復興が、これからの時代に始まるのではないかと感じています。
それは取りも直さず、人間のこころの働きの表れであり、仏教の根源にあるものなのだと思います。