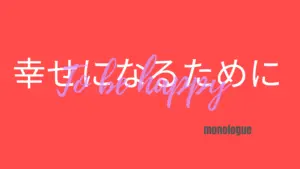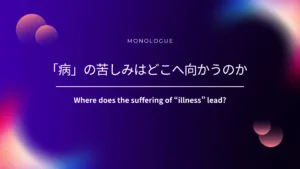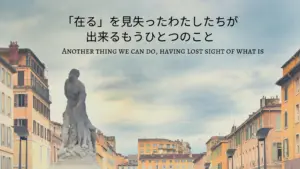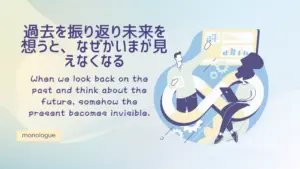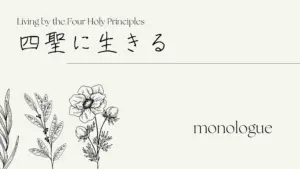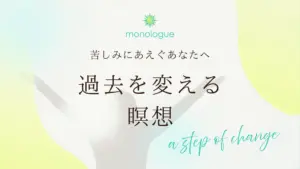はじめに
今回のテーマは気分です。わたしたちは、「今日は気分が良い」とか、「気分がすぐれない」とか頻繁に使っています。が、精神科学的には気分というあやふやな概念は存在しないかもしれません。

普段、わたしたちは気分の中で生活しています。また、気分は感情への呼び水ともなっています。一方で、外的な影響を受けやすいのも気分です。周りからの言葉や出来事をきっかけに、何も考えずに感情的に行動する人は少数ではありません。
感情の大きな起伏は、幸せを遠ざける要因のひとつです。その意味から言うと、幸せは気分と密接に関係していると言えます。
世の中には様々な価値観があります。幸福についてもご多分に漏れず、千差万別です。わたしは幸せとは平穏に留まるこころだと思っています。以下の記事で紹介しています。
気分と感情を結び付けてしまえば、幸せは遠くなっていくばかりです。この何ともつかみどころのない気分の正体を明白にして、幸せをもたらす方法を探ろうというのが本日のテーマです。
気分とは
気分の定義は難しいものです。感情が続く状態を指すこともありますが、今回のテーマである気分は、日常「何となく」思っている雰囲気にあります。人や出来事といった感情を想起させる対象が特定できないような何となくふんわりとした気持ちです。
何気に気分がいい
なんかそわそわする
気分は、そわそわとか落ち着き、もやもや、いらだちなど、つかみどころのない感情であり、いつの間にか靄(もや)のようにこころに掛かっている状態を気分と呼んでいます。厳密に言えば、少し違うかもしれませんが、この記事内ではそう意味付けしています。
また、感情的になった後、気分へと移行する場合もあります。例えば「興奮未だ冷めやらず」といった状況です。また逆もまたしかりです。「いらいらしていたら腹が立ってきた」などが例として挙げられます。
そう考えてみると、人はほとんど気分の中で生活を営んでいると言えます。そして、その気分に従って行動してしまいがちです。その時、知らない内に気分の奴隷となっていると言えます。
次に、気分主導の事例を挙げてみたいと思います。
気分優先の不都合
自動車の運転は、その時の気分が行動を支配することが度々発生します。
目で見たことをすぐに行動にしなければ事故を招いてしまう車の運転。あれこれ考えている暇はありません。車の運転というものは、目に映る変化を即行動に移さなければ事故に繋がります。運転は、その反復練習装置ともいえます。
反復練習を続けていく内に、感情や気分が運転へと直結していきます。運転席は、閉鎖された空間です。閉鎖された空間は、概して気分や感情を増幅させます。気分から感情、そして行動への連鎖作用を引き起こしてしまう絶好の環境下なのです。

そのためか、後先考えずに、あおり運転など、車を殺人兵器に変えてしまうような危険な行為をしてしまう事例が後を絶たちません。
気分の奴隷にならないためには、気分の正体を知ることです。正体がわかれば対応の仕様があるというものです。さらに、気分を左右している大本をたどってみましょう。
気分の素
業について
業(カルマ)という言葉をご存じでしょうか。気分を語る時、業は避けて通れません。
業とはスピリチュアル色が強くなりがちな用語ですので、素直に受け取ることが出来ない人がほとんどだと思います。わたしも正直、社会が生み出してきたこの言葉の持つ印象には抵抗を感じでいます。しかし、他に適合する言葉が見つからないので、今後も使用していきます。
業は、人の性格を司っている根源と言うことができます。通常、業は悪業として語られることが多いですが、もちろん善業もあります。今回の気分において、善業は問題とはなりません。
業の概念は複雑かつ単純です。複雑としたのは、形成されるまでがとても長い時間だからです。人の性格は、そう易々と現れるものではありません。どのようにして出来てきたのか想像すらできません。一般的に遺伝によるものとされていますが、後付けだとわたしは思っています。
また、単純としたのは、意外と本人はもちろんのこと、他人さえ気が付いている場合があるからです。何を考えているか分からないような静かな人もいますが、視線、動作、物腰にも自然と現れてきます。変えたい人もいるでしょうが、個性を良しとする現代では、逆に尊重したい人もいることでしょう。
わたしの場合、仏教における三毒(貪欲(貪り欲する心)、瞋恚-しんに(怒り恨む心)、愚痴(無知の心))のひとつである瞋恚(しんに)という怒りの癖を過去生からずっと持ち続けていました。お釈迦さまの弟子だった過去生においても怒りっぽかったのです。


瞋恚は個性とはいきません。これは、わたしの業のひとつです。他にもありましたが、ここでは割愛させて頂きます。
それが解消できたのは、紀元前から2600年に加えて、今世も50歳を過ぎてからです。これは、わたしが長い経験を通して得てきた知見です。業、特に三毒の解消が如何に難しいかお判りいただけるかと思います。
感情と変わる前に
外的要因が引き金となって、こころに巣くっている業が火をつけ感情を爆発させます。喜びや楽しみなど所謂ポジティブな感情も暴走してしまえば、コントロールを失ってしまうこともあります。

今世だけでこのような業を解消していくのはとても困難です。しかし、始めなければ何も変わらないのはご存じの通りです。
競技の前や緊張する場面などで、過呼吸などで積極的に気分を高めたり、深い呼吸で気分を落ち着かせたりしながら、局面を乗り切るといった方法があります。気分を活用した好例です。
このように、音楽を聴いたり、ハーブを使ったり、気分を上手に変えながら日常生活に生かすことを誰でも試みたことがあるのではないでしょうか。
業とはとても手強い怪物です。業に燻(いぶ)された気分の奴隷にならずに、逆に自分で積極的に気分を作っていくよう心掛けましょう。経験上、その努力は、長い目で見れば、きっと報われていきます。
まとめ
気分とは、とても短い時間で変化します。人は短いスパンで物事を考えれば考えるほど不幸に陥っていきます。それは、自分の持つ業が、知らない間に何度も気分を燻(いぶ)しているためです。

気分は独り歩きして、こころを隷属化し、感情という武器でこころを占有してしまいます。一過性の気分で行動することはもっとも避けたいところです。
また、喜び、楽しさといったポジティブな感情も有頂天といって感情の輪廻のひとつです。適度に味わう程度に留めたいですね。
気分を変えても、一時的ですぐに元に戻ってしまうかもしれません。元には戻るかもしれませんが、週一回の瞑想教室といっしょで、やらないよりはずっと良いのです。
大きな気分の中で、長い時間軸、高い視点から周りを見渡す余裕は、必ず人生により良い結果をもたらしていきます。気分を制御し平穏なこころを出来るだけ保てていけば、周りの状況も自ずと変わっていきます。
このように、幸せは自分で作っていくものなのです。