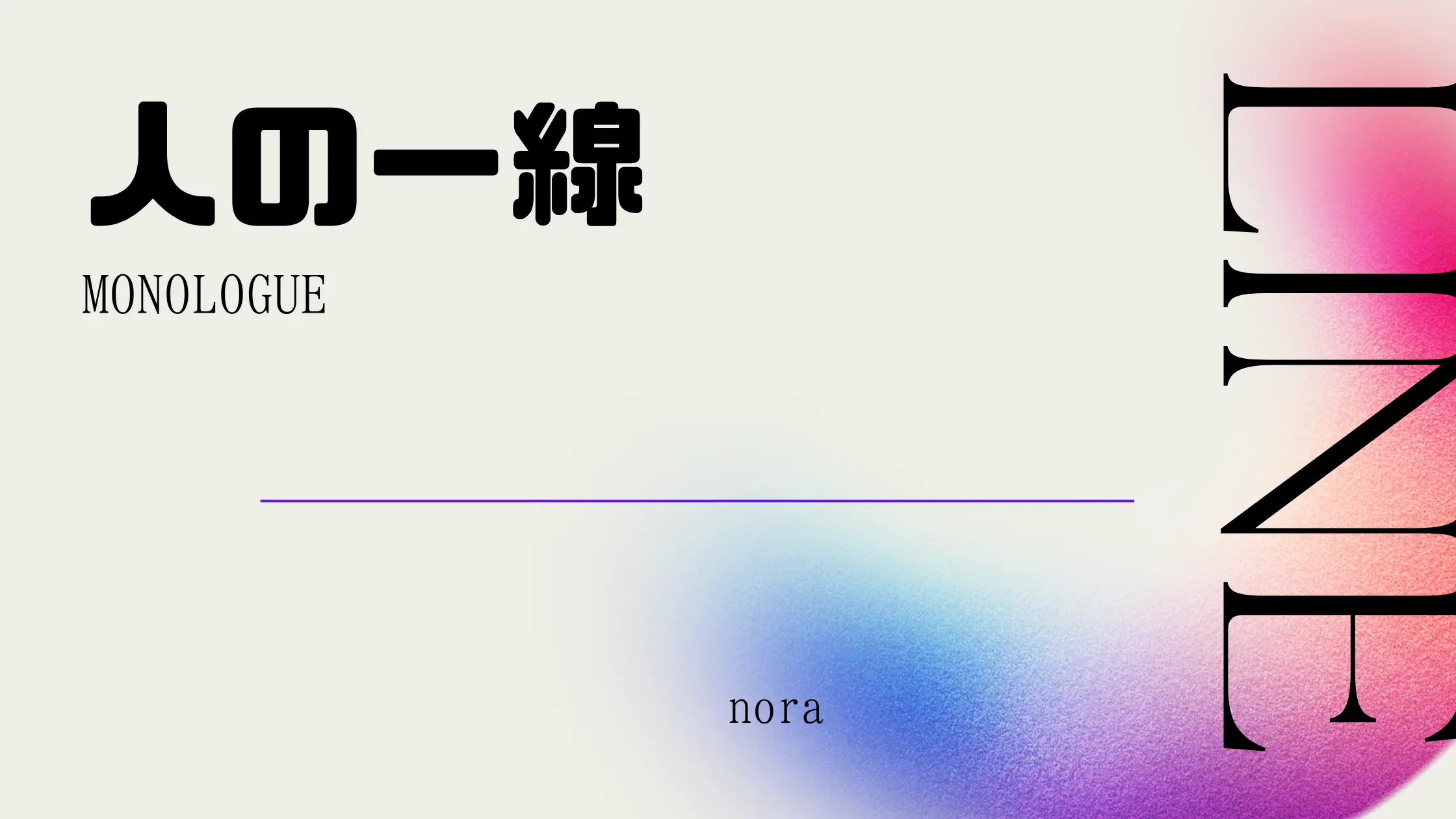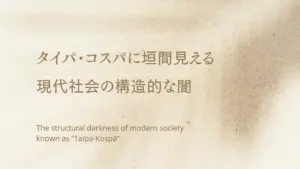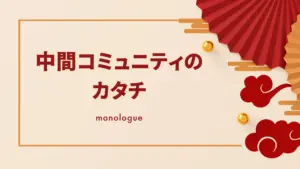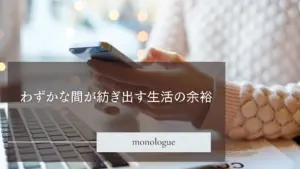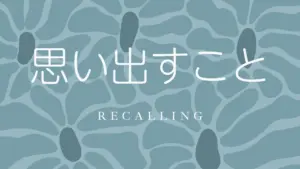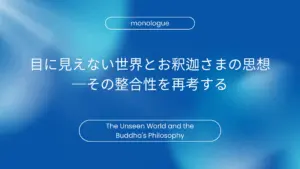はじめに
世の中には「人」と「もはや人ではない人」が存在します。「人ではない人」とは、自分で書いておきながら、なかなか鬼気迫る言葉です。
こんな強い言葉を使っていたら、わたしが傲慢で偏見に満ちた見方をしていると誤解されそうです。しかし、敢えて「人ではない人」と表したのは、他に表現が思いつかなかったためです。
今回は、「人」と「もはや人ではない人」を分けている、見えない一線についてです。
見えない線とは
見えない線とは、異性、同性間の不実な恋愛だけに留まらず、人としてして抱いてはいけない思いや、してはならない行為のボーダーラインを示したものです。また、この見えない線は、社会における合法、違法とは関係がありません。
昔から「一線を超える」という慣用句があります。この線が見えないままか、見定めて超えなかったかで来世が決まっていきます。
人ではなくなった人
すべての人は、おぎゃあと生まれた時は「人」でした。
「人と生まれるは稀なり」というお釈迦さまの言葉があります。例え、生まれいずる場所や境遇を選ぶことが出来なくとも、人として生まれることは、とても希少で貴重なめぐりあわせなのです。
「もはや人ではない人」は、見た目はどこから見ても「人」です。中には社会的な地位もあり、家族、容姿、富に恵まれている人だっています。「人ではない人」が人から外れてしまう原因は、高すぎるプライド、嗜好、行き過ぎた保身と様々ですが、根本は自分の荒ぶる煩悩を制御できなかったことにあります。
所謂「宇宙の法」に反した行為をした人とした方が、やや大げさで宗教的なニュアンスとも捉えられそうですが、わたしにとってはしっくりくる言い回しです。

外見ではわかりませんが、一度人から外れてしまう行為をしてしまうと、そのこころの底の心根が変わってしまいます。変わってしまった心根を観てみると、人ではない「別の何か」に変貌してしまっているのです。そして、そんな見えない烏合の衆とも呼ぶべき輩が、現代では溢れかえっています。
3種類の人
善い人、良い人、悪い人
この世界に生きる人間は玉石混合です。人には数限りない要素がありそうですが、その人の本性に注目して玉か石かを分けるとすれば、驚くほど単純で明確です。
人が社会生活上まとっているあらゆる仮面を削ぎ落してしまって、本性によってざっくり分けるとすれば、単純に善い人、良い人、悪い人の3つのタイプに分けられると、わたしは思っています。
良い人と悪い人の間には明確な一線があって、一線が認識できている善い人は、転生を繰り返していても決してその線を超えることはありません。
良い人が、一度線を越えて悪い人になってしまえば、所業によっては元には戻れません。まだ自分が良い人にあると思っている人は、あやふやでもこの一線を意識して、今後の行動について慎重になるべきでしょう。
「宇宙の法」というのは、この世の法律のように、審判者によって判断が変わっていくような生易しいものではありません。どんな言い訳だろうと、巧みな論理だろうと通用しない、厳格な倫理規定が横たわっています。

良い人はたくさんいて、悪い人もそれなりにいますが、善い人となるとかなり少なくなってきます。では、善い人はどんな人のことなのでしょう?
善い人とは
善い人とは、端的に言ってしまえば、次のようなこころの感性が備わっている人になります。
人の痛みを自身のことのように受け止めることができる人
一言で言ってしまいたいところですが、「慈悲」と言ってしまえば、いかにも仏教的で敷居は高くなるし、「思いやり」ではあまりに表面的です。
人の痛みを理解することは大概の人々ができています。かわいそうだと思うこともできるでしょう。それはそれで大切な感情ですが、感情と人の痛みに共感するこころの力とは全くの別です。そのため、かつてお釈迦さまが出現し、修行の意味があるのですが、一般の人々にとってはなかなか踏み込むに難しい世界です。
こころが力を付けるには、様々な経験から得られる知見や想像力、引いては人間力を養わなければなりません。

人はそれぞれ境遇を背負ってこの世に生まれてきています。縁ある人が目の前で困っていれば、手を指し伸ばすのは当たり前です。が、大切な点は、たとえ困った人々に手を伸ばすことが出来ない境遇にあっても、人の痛みを感得できるこころのあり方にあります。
善い人とは、そんなこころの力を持っている人を指します。そして、善い人には、人の一線がはっきりと観えているのです。
個人主義の台頭
個人主義は、このブログでも度々触れている西欧から雪崩のように入って来た思想です。この個人主義は、自由を拡大し、価値観の多様化を促してきました。
このような価値観の広がりには利点もあります。一方で、人の弱さは、価値観を必要以上に大きくしてしまいます。痛みを伴いそうな自分へと向かう内省は避けようとするためです。この内省を避ける癖は、やがて人の一線の存在まであやふやなものにしてしまいます。
ネット社会について
昨今、個人主義から進化してきたのが、ネット社会です。ネット社会には功罪の両面あります。人の一線から、その罪の面に注目してみましょう。
まず、ご存じのようにネット社会に参加するための要件は特にありません。メールさえあれば、老若男女誰でもいつでも参加し、様々な場所で投稿することができます。そこそこPCが使える人であれば、極端な話し、何を発言しても良いわけです。
特に昨今台頭してきたSNSは、多数の偏見が良識を凌駕する危険と常に隣り合わせの世界です。虚実を見抜けない人々が、ネット上で拡がっていく曲がった価値観に共鳴し真似をすることなど日常です。
また、周りに発言を止める者のいない自由なネット社会に向き合っていると、怒りの導火線は短くなっていきがちです。あっさりと人を貶めたり、誹謗中傷してしまい、戸惑いがありません。
このような「人の一線」を現実社会以上に簡単に越えてしまう事象は、ネット社会ならではだと思っています。

聖書の一節
このような現代の忌むべき事象をマタイの福音書から引用してみます。
彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。
上記の盲人とは身体的特徴を表したものではありません。マタイ伝での盲人とは、「神への信仰を失っている人」を指していると思われますが、わたしはこれを仏説を基に「無明にある人」と勝手に読み換えています。
無明とは「こころの曇り」です。こころの曇りは、こころの中に柱となる光が宿ってないために起こります。明るくないため、さながら盲人のように迷うのです。恐ろしいことに、人の一線など分かり様がありません。
この福音書の一文を今回の記事の主題にして言い換えてみると次のようになるでしょう。
その無明が故に人の一線を越えた者は、さらに良人を連れて共に三悪道へと落ちていく。
ところで、今回の「人の一線」について思い出したインドでの出来事があります。
インドでの出来事
昨年、インドでグルパ山という魔訶迦葉尊者の入滅地へ行ってきました。

グルパ山とは
グルパ山とはガヤ州東南に位置し、岩石が隆起して出来た低山で、ジャングルの中にポツンとあります。別名鶏足山(けいそくせん)といいますが、どう見れば鶏の足に見えるようになるのかは、結局わかりませんでした。
昔グルパ山周辺地域は、狼や虎といった猛獣が徘徊していたようですが、今ではジャングルも随分薄くなっていて、蛇くらいはいるでしょうが、人が安心して歩ける環境になっています。道路は、舗装はされていませんが山の麓まで通っています。ただ、雨で大分削られていて凹凸が酷く、ツアーなど大型バスで行くとすれば覚悟が必要です。
一匹の野良犬
グルパ山への参詣は、ガイドさんと娘とわたし3人で登山しました。
登山している間、ずっと一匹の中型犬が麓からわたしの足元に付いてきていました。最初の内は「何か食べ物が欲しいのかな?」と思っていたのです。しかし、わたしの手元には撮影カメラだけで、犬に食べ物と思われそうなものは持っていませんでした。
その犬は、わたしが立ち止まって休憩する度に、わたしの後ろから前に出てきては、後ろを振り返ってわたしを見つめていました。ガイドさんは「その犬は、あなたを知っているみたいですよ。」と言っていっていたくらいです。
立ち止まって振り返ってわたしを見つめる目元の印象からは、ガイドさんの言う通り、明らかにわたしを誰だか知っている風に見えました。

わたしは全般的に動物が苦手です。犬の表情を見極めようといった習慣は持ち合わせていません。また、インドにはたくさんの野良犬が街や村をはじめたくさんいましたが、インド滞在の一週間というもの、この犬を除いて、人に興味を持つ犬に出会うことはありませんでした。それを鑑みると、この犬の行動は異質に映りました。
重なって見える像
参拝を終えて下山の際に、犬はわたしたちを待っていました。下山をはじめてから30分ほど、もうすぐ麓に到着しようというときに、犬に重なるようにして見えない世界の現象を体験しました。以下は、その時、犬の背後から見えてきた様子です。
振り返ってわたしの目を見つめていた犬に、全身真っ黒なサリーを着た女性の姿が重なりました。
いつの間にか、目に見えない世界の中で、わたしは、グルパ山頂上付近の回廊で、後ろから彼女の肩を叩いていました。そして、「久しぶり」と声をかけていたのです。
振り返った彼女は一言も発することなく、ただわたしを懐かしんでいるようでした。
しかし、わたしにはサリーを着た女性が、誰だかわかりませんでした。
何らかの因縁が、過去生でインドに生きていたわたしと、犬になってしまったサリーの女性との間であったようです。そして、この女性は、恐らく魔訶迦葉尊者が導いたものだと思いました。それは、目に見えない世界で女性と会っていた場所が、グルパ山頂上付近、尊者が祀られている部屋へと至る細い回廊であったためです。
かつては女性であったこの犬は、わたしを2600年の間待っていたようでした。女性の「黒さ」は、こころの内に道を求める「内道」に対して外に道を求める「外道」を表しています。どうやら、過去サリーの女性は、お釈迦さまの言葉には傾倒していなかったようです。
その外道思想が起因したのか、人の一線を越えて、畜生界に落ちてしまったようでした。わたしは修行の区切りから訪印しました。犬になってしまった女性は、グルパ山で修行の区切りが出来たわたしと会うことで、わたしとの過去生での因縁を閉じることが出来たようでした。

きっと、野良犬になってしまったサリーを着た女性は、今後人に転生していくんだろうと思った次第です。それにしても、2600年とはとても長い時間です。
まとめ
もはや「人ではない」人、あるいは境界線上にいる人まで、社会的な身分、貧富に関わらずどこにでも存在しています。現代社会では人の一線はとても薄く不明瞭で、簡単に乗り越えることができてしまうようになりました。
今では使われることがなくなった言葉でひとでなしがあります。人の一線を越えたものは「人で無し」。その呼称の通り、現世ばかりでなく来世でも多くは人ではなくなってしまいます。
この世には、法律とは別に宇宙の法が流れています。代々、幼い頃から厳格さとある種の神秘性を醸し出しながら教えられてきた、最低限人として守るべき法です。
いつしか、ご近所に代表されるコミュニティーは崩壊し、親戚は集まることなく、祖父母は手の届かない遠いところへ、父母は仕事で忙しくなり、子の面倒を看るのは、ほとんどが他人という時代です。「人の一線」を根気よく伝える術も絶たれてしまいました。
一方、善い人とは、仏説では預流果に至っている人です。預流果とは転生しても三悪道(餓鬼・畜生・地獄)に落ちることのない境涯を指します。わたしたちは、この一線を学び、見つけるためにこの世に生まれてきています。
一線を学ぶことはそのまま功徳となり、亀の歩みのようでも善い人に向かうことは、平穏で幸せな人生を獲得することに繋がります。近視眼的な価値観など無視して、最後まで怠ることなく、誰もが、人としての一線を画したこころを確立していってほしいと、老婆心ながら願っています。