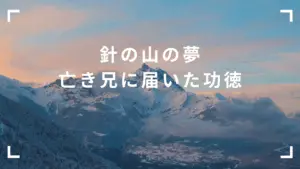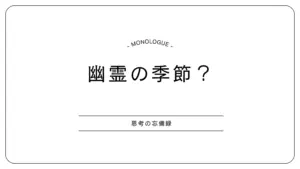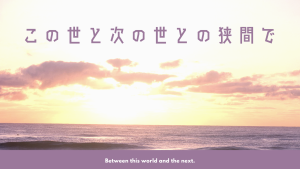はじめに
生と死を分かつものとは何か?
時々考えさせられるテーマですね。
人は、生きている以上いつかは死ぬ運命にあります。ほとんどの人にとって直近の問題ではありませんので、普段から思い考えることもないでしょう。
そんな余計なことを考えずに、ただ一生懸命生きることをお釈迦さまも望んでいらっしゃることも、わたしは分かっています。
でも、わたしの場合、目に見えない世界に接して、生死を考えさせるような印象的な場面に遭遇すると、どうしてもふと立ち止まって考えてしまうのです。
今回は、そんなわたしが、最近ふと立ち止まって考えてしまった生と死の境界について、少しお付き合い願いたいと思います。
ふたつの事例
過去にあった修行時代の研修でのこと
わたしが出家した寺院の住職がまだ若い頃、出家したばかりの修行僧たちを連れて近隣の障りの深い土地に行っては実地研修?が開催されていました。
目に見えない世界の様子を互いに感応観察できているのか、確認し共有するためです。この研修は、わたしの出家した頃には取りやめとなっていました。そこで、わたしが兄弟子から聞いた研修でのお話しを書いておきたいと思います。
兄弟子が研修を受けた場所は、近隣にある激戦を繰り広げた中世の史跡でした。そこは、敵軍に追い詰められて籠城し、末代まで祟ってやると言い残して一族郎党が討ち死にした城跡です。
兄弟子は遠くを見るような目で、「城跡の頂上付近の一帯では念が深い残像意識がうごめき漂う中、何度も何度も自分の腹を刺していた武士がいた」と話してくれました。

数年前の特集TV
突然、話しは変わります。
数年前、記憶は定かではないのですが、人知では計り知れない何かが映っている監視カメラの特集番組が放映されていました。テレビ局がネタ切れの時に繋ぎで放送枠を埋めるような海外・国内の映像を集めた番組でした。

その番組で紹介されたひとつに、アメリカの自動車スクラップ工場での監視カメラの映像がありました。その監視カメラに映っていたものは、一台のつぶされた車の運転席に乗っては降りてを何度も繰り返している黒い影でした。
潰れた車の持ち主は女性の方で、出会いがしらの衝突事故で車は大破してしまい、即死していたことがわかりました。
死後の意識について
この2つの例から、推測できることがあります。
城跡の武士の場合、何とか自らの本懐を遂げようと刀を振り続け、スクラップ車の持ち主の女性は、何とか車で家族の元に戻ろうとしていたのではないでしょうか。
この2例に共通して言えることは、武士も女性も死んだ直前の状態のまま、時間も思いも全てが止まっていることです。
人が死んでも意識があるとするならば、生と死を分けているものはいったい何なのでしょう。それは、肉体だけといっても良いかもしれません。
しかし、亡くなった後も今までの意識が続いていることなど人は知る由がありません。肉体を無くしてしまえば、記憶を含めた意識は無くなるものと信じている人々が、この世の中の大半を占めています。
人は肉体を亡くしたことで、自身を取り巻く状況は一変してしまいます。しかし、今回の2つの例を含めて、わたしが経験した死後の人の意識は、依然として自分自身は何も変わっていないと認識しているのです。
まとめ
人は死んでしまうとしばらくは、何が起こっているのか把握できるまでしばらくかかります。やがて、死んだことを認識すると、次に自分のいなくなった周りの状況や残されたものや人が気になることでしょう。
そうして、時を経るごとに、向き合うことが出来るのは自分だけであることに気が付きはじめます。自分がどのように生きてきたのかを自分に問いかけるのです。しかし、このようにして順当に、こころの変化が進むことは非常に稀です。
多くは、前述の例のような城跡の武士や事故死した女性のように、混乱し何とか現実に戻ろうとするのです。
人の死後の状況は、生前のこころに寄る
秋の夜長、肉体を亡くした剥き身の自分自身が、その場に放り出される状況を想像してみるのも良いかもしれません。